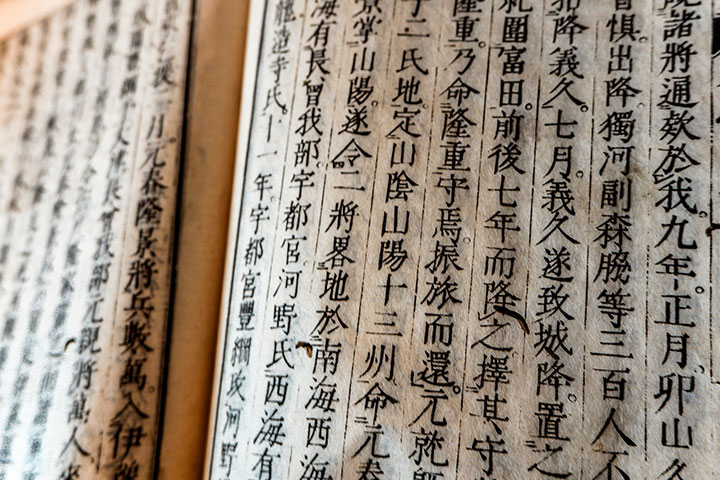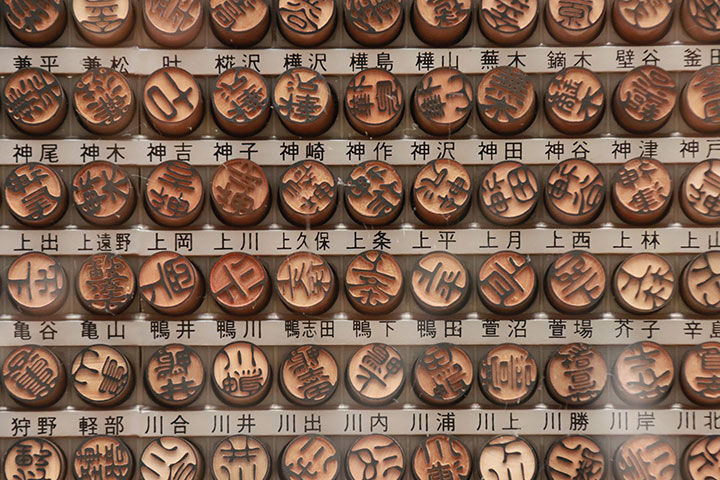結論からお伝えすると、初詣は、三が日を過ぎてしまっても問題ありません。
この記事では、初詣に最適な期間から、混雑を避けて快適に参拝できる時期と時間帯、参拝時に困らないための基本マナーを解説しています。
この記事を読めば、あなたのスケジュールに合ったベストなタイミングで、気持ちよく新年のお参りができるでしょう。
「これから初詣の予定を立てたい」「正しいマナーを知っておきたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
- 初詣はいつまでに行けばいい?基本は「松の内」の期間まで
- 初詣で混雑を避けて快適に参拝できる時期と時間帯
- 2026年の初詣で気をつけたい日取り
- 初詣は神社とお寺、どこに行くのが正解?
- 初詣の基本マナーと参拝作法
- 初詣にふさわしい服装・屋台・お賽銭のマナー
- 初詣に関するよくある質問
- 初詣はいつまでに行けばいいかを理解して、気持ちよく参拝しよう
初詣はいつまでに行けばいい?基本は「松の内」の期間まで

新年の初詣は三が日(1月1日〜3日)に行くもの、というイメージが強いかもしれません。しかし、三が日ではなく、もう少しゆとりのある「松の内(まつのうち)」が初詣の期間とされています。
この章では、初詣の期間や、その背景にある文化について解説します。
松の内とは年神様が滞在する期間のこと
「松の内」とは、お正月に門松を飾っておく期間のことです。門松を飾る風習は、新年の幸福をもたらすために各家庭にやってくる「年神様(としがみさま)」をお迎えすることに由来しています。
古くから神聖な木とされてきた松は、年神様が宿るための目印(依り代)としての意味があります。そのため、門松が飾られている松の内の期間は「年神様が家々に滞在されている期間」と考えられているのです。
このことから、年神様がいらっしゃる松の内に初詣に行き、新年のご挨拶をするのが礼儀にかなっているとされています。また、松の内は鏡開きやどんど焼き(お正月飾りを燃やす火祭り)にもつながる、正月行事の区切りとしての役割もあります。
「松の内」の期間は関東と関西で異なる
松の内の期間は地域によって異なる点には注意が必要です。一般的には、関東では1月7日まで、関西では1月15日までが松の内とされています。
関西と関東で期間が異なるのは、江戸時代に徳川幕府が将軍の命日が祝い事と重なることを避けるため、「鏡開きは11日に」とお達しを出したことに由来すると言われています。その結果、関東を中心に期間が7日までと短く、伝統を重んじた関西では15日のままになっているのです。
そのため、三が日を過ぎてしまっても、松の内の期間中であれば「初詣」となるため、問題ありません。
【一覧表】地域別・松の内の期間まとめ
松の内をいつまでとするかは、地域によって異なります。ご自身のお住まいの地域がいつまで松の内なのか、下記の一覧表で確認してみましょう。
| 地域ブロック | 主流な期間 | 補足・例外の傾向 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1/1〜1/7 | 関東と同様の7日が一般的。鏡開きは11日に行われることが多い。 |
| 東北 | 1/1〜1/7 | 青森、秋田、岩手など、一部地域では15日までの慣習も残る。 |
| 関東 | 1/1〜1/7 | 最も典型的な「7日まで」の地域。 |
| 中部(東海・北陸・甲信) | 1/1〜1/7 | 名古屋周辺は7日が多いが、地域によっては15日派も混在。 |
| 近畿(関西) | 1/1〜1/15 | 京都・大阪・滋賀などを中心に、15日までとするのが一般的。 |
| 中国 | 1/1〜1/7 | 15日までとする地域も一部あり、地域差が見られる。 |
| 四国 | 1/1〜1/15 | 関西の文化圏の影響を受け、15日までとする地域が多い。 |
| 九州・沖縄 | 1/1〜1/7 | 福岡では7日が多い。地域により8日・10日・15日・20日と多様。 |
このように、鏡開きや寒中見舞いを出すタイミングも松の内に連動します。同じ県内でも地域や家庭によって慣習が異なることもあるため、迷ったら地域の神社や自治体の案内に従うと良いでしょう。
松の内を過ぎたら小正月・節分・立春が次の目安
もし松の内までに初詣に行けなかった場合でも、まだ参拝の目安とされている期間があります。
松の内を過ぎた初詣は、以下の日取りを目安にすると良いでしょう。
| 名称 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| 小正月 (こしょうがつ) |
1月15日 | 正月行事の締めくくりとされる日。 この日に行われる「どんど焼き」でお正月飾りを神社に納めるため、参拝も良い区切りとなる。 |
| 節分 (せつぶん) |
2026年は2月3日 | 旧暦では、節分が大晦日にあたる。 節分までに「厄落とし」や「新年祈願」として参拝することも理にかなっている。 |
| 立春 (りっしゅん) |
2026年は2月4日 | 旧暦における新年の始まり。 この日を一つの区切りとして参拝するのもおすすめ。 |
また、期間にこだわらなくても、「年が明けてから最初の参拝が、その人にとっての初詣である」という考え方もあります。
時期を気にして参拝しないよりも、ご自身の都合の良いタイミングで心を込めてお参りすることが大切です。
初詣で混雑を避けて快適に参拝できる時期と時間帯

初詣の時期は、有名な神社仏閣では大変な混雑が予想されます。せっかく参拝するなら、人混みを避けて心静かにお祈りしたいと考える方もいるでしょう。
ここでは、混雑のピークを避け、快適に初詣ができる時期と時間帯をご紹介します。
・最も混むのは「大晦日深夜」と「三が日の日中」
・空いている時期なら「1月4日以降の平日」
・おすすめの時間帯は「早朝」または「夕方」
最も混むのは「大晦日深夜」と「三が日の日中」
初詣の混雑がピークに達するのは、以下の時間帯です。
・大晦日の深夜から元旦の未明にかけて(0時前後)
・三が日の日中(特に午前10時〜午後3時頃)
年越しの瞬間を境内で迎える「除夜詣り」は特に人気が高く、多くの人が集中します。また、三が日の日中は家族連れなどでにぎわう時間帯です。
明治神宮(東京)や伏見稲荷大社(京都)といった有名な神社仏閣では、入場規制が行われることも珍しくありません。
人混みが苦手な方や、静かにお参りしたい方は、この時間帯を避けて計画を立てることをおすすめします。
空いている時期なら「1月4日以降の平日」
初詣の混雑を回避したいなら、1月4日以降の平日がねらい目です。多くの人が仕事始めを迎え、正月休みが終わると参拝者の数は激減し、境内は落ち着いた雰囲気を取り戻します。
この時期ならではのメリットはたくさんあります。
・神様とじっくり向き合える:行列がないので、静かな気持ちでゆっくりと一年の抱負を誓えます。
・写真が撮りやすい:人が少ないので、美しい社殿や風景の写真を撮りやすいのも嬉しいポイント。
・お守りやおみくじをゆっくり選べる:授与所も空いているため、「どのお守りにしようかな?」とデザインやご利益をじっくり見比べながら選べます。
・駐車場や交通機関もスムーズ:車で行く人も駐車場に停めやすく、電車やバスも普段通り動いているので快適です。
特に平日の早朝に参拝すれば、待ち時間も少なく清々しい気持ちでお参りできますよ。
ただし、1月4日は多くの企業で仕事始めにあたり、社内行事としての初詣に出向く人が増える傾向があります。そのタイミングは、平日でも混み合う可能性があるので留意しておきましょう。
おすすめの時間帯は「早朝」または「夕方」
三が日中に参拝したい場合でも、時間帯を工夫することで混雑を避けられます。三が日中のお参りでは以下の時間帯がおすすめです。
・早朝(開門〜午前9時頃)
早朝の境内は参拝者も少なく、冬の澄んだ空気の中で心が洗われるような時間を過ごせます。心静かにお参りしたい方には最適な時間帯です。
・夕方(午後4時以降)
日中のピークが過ぎた夕方も人が少なくなる時間帯です。ただし、神社やお寺によっては閉門時間が早い場合があるため、事前に公式サイトなどで確認しておきましょう。
安全面を考慮すると、足元が見えにくくなる夜間の参拝は、特別な行事がない限り避けた方が良いでしょう。
2026年の初詣で気をつけたい日取り

せっかく初詣に行くなら、縁起の良い日を選びたいものですよね。一方で、カレンダーに書かれている「仏滅」などの日に参拝しても良いのか、気になる人もいるかもしれません。ここでは、参拝日を選ぶ際に知っておきたい日取りの考え方について解説します。
・縁起を気にするなら「不成就日」は避ける
・六曜(仏滅・赤口など)は気にしなくてもよい
・忌中は神社参拝を控える
・喪中は気持ちで判断しても良い
縁起を気にするなら「不成就日」は避ける
不成就日(ふせいしゅうじつ)は、暦の上で「何事も成就しない日」として、新しいことを始めたり、願い事をするのには向かないとされています。初詣も神仏への願掛けと捉えられるため、縁起を気にする方はこの日を避けると良いでしょう。
2026年1月〜2月の不成就日は以下の通りです。
・1月:1日(水)、9日(木)、17日(金)、24日(金)
・2月:1日(土)、9日(日)、19日(水)、27日(木)
ただし、不成就日はあくまで暦注(暦に記載されているその日ごとの吉兆)のひとつであり、宗教的な根拠はありません。最終的にはご自身の気持ちの持ち方次第と考えておきましょう。
六曜(仏滅・赤口など)は気にしなくてもよい
カレンダーでよく目にする「大安」「仏滅」といった六曜(ろくよう)も歴注の一つです。こちらも神道や仏教の教えとは直接関係がないので、初詣の日取りで気にする必要はありません。
「仏滅にお参りすると縁起が悪いのでは?」と心配する声も聞きますが、これはよくある誤解です。神社の包括組織である神社本庁も「六曜は日の吉凶とあまり関係がない」との見解を示しています。
むしろ「仏滅」は「物滅」として、「一度リセットして物事を始めるのに良い日」というポジティブな解釈もあります。縁起よりも、「行きたい!」と思ったご自身の気持ちを大切にすると良いでしょう。
忌中は神社参拝を控える
暦とは別に、ご家族が亡くなられた場合、一定期間、お祝い事や神社への参拝を慎む忌中(きちゅう)という期間があります。
特に神道では、死を「穢れ(けがれ)」と捉える考え方があるため、忌中の期間は神域である神社への参拝を控えるのが習わしです。そのため、忌中に当たる期間は、神社への初詣は忌中開けを待つようにします。
忌中の期間は、以下の通りです。
・神道:故人が亡くなられてから50日間
・仏教:故人が亡くなられてから49日間(四十九日法要まで)
一方、お寺への参拝は忌中でも問題ないとされることが多いため、初詣に行っても大丈夫です。ただし、宗派によって解釈が異なる場合があるため、参拝先の方針を確認すると安心です。
喪中は気持ちで判断して良い
神様への参拝を控える「忌中」の期間が終わると、次は故人を偲ぶ「喪中」の期間に入ります。喪中の初詣には「絶対に行ってはいけない」という決まりはないため、最終的にはご自身の気持ちを大切に判断して良いとされています。
ただし、喪中は門松を飾ったり、「おめでとうございます」と挨拶を交わしたりといったお祝いごとは控えるのが一般的です。
喪中の初詣は、故人を心に偲びつつ、神様や仏様に静かに手を合わせる機会と考えると良いでしょう。旧年を無事に過ごせたことへの感謝を伝え、「今年も家族が健やかでありますように」と新年の平穏をお祈りします。
初詣は神社とお寺、どこに行くのが正解?

初詣の参拝先として、神社とお寺のどちらを選ぶべきか、迷った経験をお持ちの人もいるのではないでしょうか。結論から言うとどちらに参拝しても問題ありません。
それぞれの特徴を知っておくと、より自分の気持ちに合った参拝先を選べるでしょう。ここでは、神社とお寺、どちらに初詣に行けばよいのか、考え方をご紹介します。
どちらでもOK!初詣は「神仏への感謝」を示す行事
初詣で大切なのは、「昨年一年、無事に過ごせました。ありがとうございます」と神様や仏様に感謝を伝え、「今年も健やかに過ごせますように」と新年の平和を祈る気持ちです。だからこそ、その祈りを捧げる場所が神社なのか、お寺なのか、という点に厳密なルールはありません。
実際に、初詣の参拝者数で全国トップクラスの明治神宮(東京)は神社ですし、同じく多くの人で賑わう成田山新勝寺(千葉)や川崎大師(神奈川)はお寺です。どちらも新年の祈りの場として、多くの人々に愛されています。
神社とお寺、それぞれの特徴と願いごと
初詣は神社とお寺、どちらでも良いと言われると、かえって迷ってしまう人もいるかもしれません。その場合は、それぞれの特徴や得意とする願い事に合わせて選ぶのもおすすめです。
それぞれの参拝先に適した願いごとを以下にまとめました。学業成就や病気平癒など、希望するご利益に合わせて参拝先を選ぶのもおすすめです。
| 種類 | 特徴 | 向いている願いごと |
|---|---|---|
| 神社 | 神様に自分の決意を誓い、成就を祈る場所 | 厄除け、開運招福、商売繁盛、家内安全、縁結びなど |
| お寺 | 仏様に感謝し、自分の心と向き合い整える場所 | 先祖供養、心願成就、学業成就、健康祈願など |
神社とお寺には、どちらが良い・悪いといった優劣はありません。ご自身の願いの方向性に合わせて、自然と足が向く方へお参りすると良いでしょう。
神社とお寺、両方にお参りしても問題ない
神社とお寺の両方にお参りしても、差し支えありません。神様と仏様、両方にご挨拶をすることは失礼にあたらず、むしろ丁寧なこととされています。
一般的には、「神様には新年の誓いを立てて願い事をし、仏様には旧年の感謝を伝える」という考え方から、「神社→お寺」の順で参拝するのが良いとされています。しかし、これは厳格な決まりではないため、ご自身の回りやすい順序でお参りすると良いでしょう。
もし、「最初にどこへお参りするのが良いか」と迷う場合は、まずご自身の住む地域を守ってくださっている氏神様(うじがみさま)、つまり地元の神社へご挨拶に伺うのがおすすめです。
初詣の基本マナーと参拝作法

神様や仏様を前にした際、正しい参拝作法に自信がなくて、不安に感じたことはありませんか。基本的な作法を知っておけば、より落ち着いて、心を込めてお参りできるようになりますよ。
ここでは、参拝の基本マナーをおさらいしておきましょう。
・【神社編】二礼二拍手一礼が基本
・【お寺編】静かに合掌して祈る
・鳥居・参道の歩き方
・手水舎の使い方
【神社編】二礼二拍手一礼が基本
神社での参拝の流れは、神様に経緯を示すための作法です。少し複雑に見えるかもしれませんが、基本となる二礼二拍手一礼さえ覚えておけば大丈夫です。
1.鳥居をくぐる前に立ち止まり、軽く一礼する。
2.手水舎で手と口を清める。
3.お賽銭箱の前で軽く一礼し、お賽銭を入れる。
4.鈴をやさしく鳴らす。
5.二礼二拍手一礼する。
・二礼:深いお辞儀を2回
・二拍手:胸の前で両手を合わせ、右手を少し下にずらして2回拍手
・一礼:最後に深いお辞儀を1回
6.鳥居をくぐった後、社殿の方を振り返って一礼する。
願い事をする際のポイントは「~になりますように」とお願いするだけでなく、「~という目標のために努力しますので、お見守りください」と誓いを立てる形にすることです。神様に頼りきりになるのではなく、自力では足りない部分の力添えを願う姿勢が大切です。
【お寺編】静かに合掌して祈る
お寺での参拝は、仏様やご先祖様への感謝を伝える場です。神社との大きな違いは、拍手をせず、静かに手を合わせる点にあります。仏様の前では、心を落ち着けて穏やかにお祈りすることを心がけましょう。
1.山門の前で合掌し、一礼してからくぐる。
2.手水舎で手と口を清める。
3.常香炉(じょうこうろ)があれば、その煙を浴びて身を清める。
4.お賽銭をそっと入れ、鰐口(わにぐち:銅鑼のような仏具)があればやさしく鳴らす。
5.胸の前で静かに両手を合わせ、合掌して祈る。
6.帰りは山門を出た後、本堂に向かって一礼する。
お寺は仏様の教えに触れる場所でもあります。自身の心と静かに向き合い、日々の感謝を伝える気持ちでお参りすると良いでしょう。
鳥居・参道の歩き方
神社の鳥居は、神様が住む神聖なエリアへの入口です。鳥居をくぐる前に一度立ち止まって一礼するのは、神様への挨拶の意味が込められています。
参道の真ん中は「正中(せいちゅう)」と呼ばれ、神様の通り道とされています。神様の邪魔をしないよう真ん中を堂々と歩くのは避け、左右どちらかに寄って歩くのがマナーです。
参道を横切る際には、軽く頭を下げるか、中央で一度神前に向き直って一礼してから横切るようにしましょう。帰りも鳥居を出た後、社殿の方を振り返って「ありがとうございました」の気持ちを込めて一礼すると、より丁寧ですよ。
手水舎の使い方
手水(ちょうず・てみず)は、神仏にお参りする前に、自分自身の心と身体についた穢れを洗い流すための禊(みそぎ)にあたります。一連の動作をスムーズに行えると、参拝前の心構えも整いますよ。
1.右手で柄杓(ひしゃく)を持ち、水を汲んで左手を清める。
2.柄杓を左手に持ち替え、右手を清める。
3.再び右手に持ち替え、左の手のひらに水を受け、その水で口をすすぐ。(柄杓に直接口をつけないように注意)
4.口をすすぎ終えたら、もう一度左手を清める。
5.柄杓を立てて残った水で持ち手の部分を洗い流し、元の場所に戻す。
近年は、感染症対策で柄杓を置かず、竹などから水が流れ続ける「流水式」の手水舎も増えています。その場合は、両手を洗い、手のひらの水で口をすすぐ形で清めましょう。
初詣にふさわしい服装・屋台・お賽銭のマナー

初詣を心から楽しむためには、お参りの作法だけでなく、当日の服装やお賽銭といった準備も大切です。服装やお賽銭といった周辺のマナーから、お楽しみの屋台情報までしっかり押さえておけば、心に余裕が生まれるでしょう。
ここでは、余計な心配事をなくし、晴れやかな気持ちで新年をスタートさせるためのポイントを紹介します。
服装は「清潔感・控えめ・防寒」を意識する
初詣の服装に厳格な決まりはありません。しかし、神仏に感謝を伝える神聖な場であることを念頭に、「清潔感のある控えめな服装」を心がけるようにしましょう。
・OKな服装の例:ニット、きれいめなコート、パンツスタイル、ワンピースなど
・避けたい服装の例:ジャージやスウェットなどの部屋着、ダメージジーンズ、露出の多い服(ミニスカートやタンクトップなど)
露出の多い服や派手すぎるデザインは避け、落ち着いた色合いの服装を選ぶと安心です。
また、冬の境内は、石畳や砂利道から冷気が上がってきます。インナーを着込んだり、カイロを貼ったり、厚手の靴下を履いたりして、万全の寒さ対策をしていきましょう。足元が悪い場所もあるので、ヒールよりも歩きやすく滑りにくい靴を選ぶのがおすすめです。
初詣での屋台(出店)はいつまでやっている?
たこ焼き、りんご飴、甘酒など、初詣の楽しみの一つといえば、屋台です。屋台は三が日を中心に営業しているところが多く、大きな神社やお寺なら松の内(7日頃)までにぎわっていることもあります。
ただし、小規模な神社では元日だけ、または三が日限定という場合も少なくありません。屋台の営業時間は神社の開門・閉門時間と連動していることが多いので、夜遅くに参拝すると神社も屋台も閉まっている可能性もあります。
屋台をお目当てに初詣に行く場合は、神社の公式サイトやSNSで最新情報をチェックしてから行くと確実です。
お賽銭の金額と縁起の語呂合わせ
お賽銭の金額に決まりはありません。大切なのは金額の大小ではなく、感謝の気持ちを込めて奉納することです。その上で、縁起の良い語呂合わせで金額を決める方も多くいます。
お賽銭の語呂合わせには、以下のようなものがあります。
縁起が良いとされる語呂合わせ
・5円:「ご縁がありますように」
・15円:「十分なご縁がありますように」
・45円:始終ご縁がありますように」
避けた方が良いとされる語呂合わせ
・10円:「遠縁(縁が遠のく)」
・65円:「ろくなご縁がない」
・500円:「これ以上効果(硬貨)がない」
お賽銭は神様や仏様へのお供え物ですので、投げ入れるのではなく、手のひらから滑らせるようにやさしく入れるのがマナーです。
初詣に関するよくある質問

ここからは、初詣に関するよくある質問にお答えしていきます。
初詣に行かないとどうなりますか?
罰が当たったり、不運が訪れたりすることはありません。初詣は日本の伝統的な習慣ですが、義務ではありません。「仕事がどうしても休めない」「体調がすぐれない」「小さな子どもがいて、混雑のなかへ行くのは大変」など、さまざまな樹上で初詣に行けないこともあるでしょう。
大切なのは、新しい年を迎えられたことへの感謝の気持ちです。家で神棚や仏壇に手を合わせるなど、ご自身のできる形で気持ちを表せば十分です。
2026年の初詣の吉方位はどちらですか?
2026年の恵方(えほう)は「南南東」です。吉方位とはその年の福を司る「歳徳神(としとくじん)」がいる方角とされて、その年のラッキーな方角と考えると良いでしょう。
ご自宅から見て南南東にある神社やお寺に参拝する「恵方参り」をすると、より縁起が良いとされています。参拝先に迷うのなら、吉方位を参拝先を選ぶ際のヒントとして活用してみてはいかがでしょうか?
初詣は複数回行っても大丈夫ですか?
初詣は複数回行っても問題ありません。参拝回数に制限はなく、願い事に応じて複数の神社やお寺を参拝するのも良いでしょう。また、西日本には正月に三つの神社を巡る「三社参り」という風習もあります。「A神社では仕事運、B神社では家族の健康、C神社では縁結び…」というように、願いごとに合わせてお参り先を変えるのも良いでしょう。複数回お参りしても、ご利益が薄れることはないため、安心して何度でもお参りしてくださいね。
初詣はいつまでに行けばいいかを理解して、気持ちよく参拝しよう

初詣の期間は「松の内」までが一般的ですが、大切なのは時期にこだわることよりも、新しい一年を健やかに過ごせることへの感謝の気持ちです。初詣の基本的なマナーを知っておけば心に余裕が生まれ、より穏やかな気持ちでお参りでき、清々しいスタートを切れるでしょう。
そして、新しい年は、自身の暮らし全体を見つめ直す絶好の機会でもあります。初詣で気持ちを新たにするように、毎日の暮らしの基盤である住まいを整えてみませんか?快適な住環境は、より良い一年のスタートを後押ししてくれるはずです。
お部屋探しをする際は、「ニフティ不動産」がおすすめです。
大手不動産サイトの物件情報を一括で検索・比較できるので、自分に合う条件のお部屋をスムーズに探せるでしょう。
ぜひ「ニフティ不動産」を活用し、理想の住まいを見つけてみてください。
アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ
部屋を借りる!賃貸版はこちら
住宅を買う!購入版はこちら


 風水で玄関の鏡はNG?位置、大きさ、形のおすすめと運勢上昇のポイント
風水で玄関の鏡はNG?位置、大きさ、形のおすすめと運勢上昇のポイント
 略語早わかり62選!ビジネスシーン・若者間で使われる必須略語一覧
略語早わかり62選!ビジネスシーン・若者間で使われる必須略語一覧
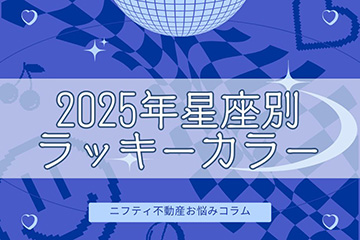 【2025年版】今年のラッキーカラーまとめ|星座別に運気が上がる色を紹介
【2025年版】今年のラッキーカラーまとめ|星座別に運気が上がる色を紹介
 【決定版】家相の基本と間取り図の正しい見方!鬼門・NG配置の対策まで徹底解説
【決定版】家相の基本と間取り図の正しい見方!鬼門・NG配置の対策まで徹底解説