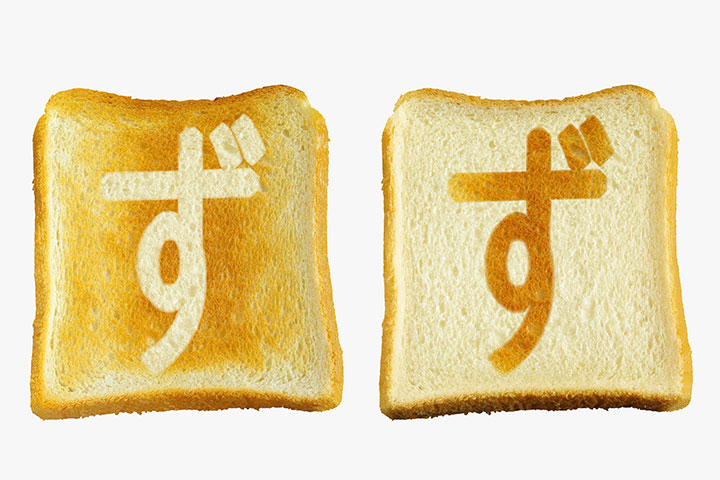新築から5年以上が経つと、そろそろメンテナンスが必要な時期に差し掛かってきます。
陸屋根は水はけが悪いので、防水工事のメンテナンスを行わずに放置していると、雨漏りが発生する危険性も。
防水効果が切れる前に、メンテナンス工事を依頼することが大切です。
そこで本記事では、防水工事の種類や費用、耐用年数について詳しく解説します。
メンテナンスが必要になる時期の目安や、効果を長持ちさせるコツ、業者選びのポイントなども取り上げるので、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
- 陸屋根とは
- 陸屋根に防水工事が必要になるタイミング
- 陸屋根の防水工事の種類と費用・耐用年数
- 陸屋根の防水を長持ちさせるコツ4つ
- 陸屋根の防水工事を自分でDIYするのはおすすめできない
- 陸屋根の防水工事で業者を選ぶときのポイント4つ
- 陸屋根の防水工事の補助金・助成金
- 陸屋根の防水工事に関するよくある質問
- 防水工事を適切に行い陸屋根を長持ちさせよう!
陸屋根とは

陸屋根の特徴
陸屋根とは、傾斜がない平らな屋根のこと。「りくやね」または「ろくやね」と読み、「平屋根」と呼ばれる場合もあります。
陸屋根は、屋上部分で植物や野菜を育てたり、洗濯物を干したりなど、スペースを有効活用できるのが魅力的。
また、屋根のメンテナンス時に足場を汲む必要がなく、簡単に作業できるのもメリットです。
最近ではデザイン性が高い陸屋根が登場し、マンションやオフィスビルだけではなく、一般住宅でも取り入れる方が増えています。
陸屋根に防水工事が必要な理由
陸屋根を採用した場合、快適な住環境を保つためには、定期的な防水工事が必要です。
陸屋根は通常の屋根のように傾斜がないため、水はけが悪くなります。
雨が降ったときに雨水が下に流れていかず、場合によっては建物の内部に染み込んでしまう可能性も。
防水工事を行っていないと、やがて雨漏りが起こってしまうでしょう。
防水工事を行えば水はけが改善するので、建物の内部が傷んでしまうのを未然に防げます。
陸屋根に防水工事が必要になるタイミング

「新築から数年経ったけど、いつ防水工事のメンテナンスを行えば良いの?」と疑問に思っている方は多いでしょう。
この章では、防水工事が必要かどうかを見極めるポイントについて解説します。
・新築から5年~10年ごとが目安
・劣化症状を確認する
以下で詳しく見ていきましょう。
新築から5年~10年ごとが目安
陸屋根の防水工事のタイミングは、新築から5年〜10年ごとです。
ただ、上記の数値はあくまで目安なので、実際のタイミングは屋根の劣化状況によって異なります。
屋根を目視して、劣化症状が現れていないか確認する方法がより確実です。
屋根を目視できない場合は、新築から5年〜10年を目安に点検を依頼しましょう。
劣化症状を確認する
先述したように、陸屋根の防水工事のタイミングは、屋根の劣化症状によって見極められます。
ここでは、代表的な劣化症状を7つ紹介します。
1.雑草が繁殖している
2.目地やコンクリートなどにひび割れがある
3.色褪せやチョーキング現象が起きている
4.雨が降ったあとに水たまりができている
5.雨漏りが発生している
6.防水層の浮き・膨れ・めくれなどがある
7.破損しているところがある
以下でそれぞれの劣化症状について詳しく解説していくので、確認しておきましょう。
1.雑草が繁殖している
陸屋根に雑草が繁殖している場合は、速やかに業者に点検を依頼しましょう。
根が防水層を突き破ると、雨漏りの原因になる可能性があります。
なお、雑草が生えているからといって、自分で抜くのは避けてください。
防水層まで根が生えていると、無理に抜けば防水層を傷つけてしまいます。
雑草は、運ばれてきた種子が排水溝周りのゴミなどに留まり、水や養分を得ると発芽します。
普段からこまめに掃除をして、清潔な環境を保つことが大切です。
2.目地やコンクリートなどにひび割れがある
目地やコンクリートのひび割れも、早急な対処が必要な劣化症状です。
目地やコンクリートがひび割れていると、防水層も破損している可能性が高くなります。
破損した箇所から雨水が侵入すると、建材が劣化したり、雨漏りが起こったりするかもしれません。
点検やメンテナンスを怠らず、ひび割れが起こる前に防水工事を行うことが大切です。
3.色褪せやチョーキング現象が起きている
塗料の色褪せや、塗膜が劣化して粉状になるチョーキング現象も、注意が必要な症状です。
上記のような症状は、防水層の劣化が進行しているときに起こります。
早急な対処が必要というわけではありませんが、メンテナンスを先延ばしにせず、なるべく早めに点検を依頼しましょう。
4.雨が降ったあとに水たまりができている
雨が降ったあとの水たまりも、メンテナンスが必要なサインです。
小さな水たまりで時間が経つとなくなる場合は、まだそれほど大きな問題ではありません。
しかし、時間が経っても水たまりが残っている場合は、防水の効果が切れている証拠です。
放置していると一面が水たまりになってしまったり、雨水が内部まで侵入してしまうかもしれません。
なるべく早く点検を依頼してください。
屋根を目視できる方は、雨が降ったあとに水たまりができていないかをこまめに確認するようにしましょう。
5.雨漏りが発生している
雨漏りが発生している場合は、すでに防水機能は失われているので、早急なメンテナンス工事が必要です。
雨漏りを放置していると、内部まで水が侵食して建材が傷んでいきます。
最悪の場合、陸屋根の全面改修が必要になるかもしれません。そうなると、工事にかかる費用も高額になるでしょう。
劣化症状がひどければ、その分メンテナンスにかかる費用も高くなります。したがって、症状が悪化する前に適切な対処をすることが大切です。
6.防水層の浮き・膨れ・めくれなどがある
防水層の浮き・膨れ・めくれも、注意が必要な劣化症状です。
浮いている部分やめくれている部分から雨水が染み込むと、やがて雨漏りが起こります。
また、浮き・膨れ・めくれなどの症状があるのが一部分だとしても、放置していると症状は全体に広がります。
陸屋根を屋上庭園や洗濯物を干す場所として利用している場合は、防水層のめくれにつまづいて怪我をしてしまう危険性もありますよ。
浮き・膨れ・めくれなどに気がついたら、症状が軽いうちにメンテナンスを依頼しましょう。
7.破損しているところがある
陸屋根の床面が破損していたら、早急に防水工事を依頼してください。
破損している箇所から雨水が侵入すると、建物自体の劣化が進行してしまいます。
放置すればするほど工事は大がかりになるので、気づいた時点ですぐに対処することが大切です。
陸屋根の防水工事の種類と費用・耐用年数

陸屋根の防水工事は、主に以下の3つの種類にわかれます。
1.塗膜防水
2.シート防水
3.アスファルト防水
ここでは、それぞれの防水工事の特徴と、費用・耐用年数について解説します。
陸屋根の防水工事を検討している方は、しっかりと確認しておきましょう。
1.塗膜防水
防水塗料を塗り、膜をつくって屋根を保護する工事方法が「塗膜防水」です。
細かい部分まで塗れるので、たとえばエアコンの室外機などがあっても、隅まで工事を施せるのが魅力です。
塗膜防水は、さらに細かく「ウレタン防水」と「FRP防水」に分類されます。
以下で詳しく見ていきましょう。
●ウレタン防水
液体状のウレタン樹脂を塗って防水層をつくる方法が「ウレタン防水」です。
ウレタン防水は、防水工事の中で最も一般的な方法だといえるでしょう。材料費が安いので、工事価格も比較的リーズナブルに済みます。
また、工程が単純なので、工期が短いのもメリットですね。
工事方法は、ウレタン樹脂を複数回塗り重ねて、上からトップコートを塗るのが基本です。工事後の重ね塗りも可能なので、メンテナンス費用も安く済みます。
さらに、異なる防水材の上からの重ね塗りも可能なので、メンテナンス時に違う方法からウレタン防水に変更しても、撤去費用がかかりません。
ただ、職人の技量によって仕上がりに差が出やすいのがデメリットです。
費用相場(1㎡あたり):4,000円~6,500円
耐用年数:8年~10年
工期:1週間程度
●FRP防水
ウレタン防水に比べて強度が高く、耐久性に優れているのが「FRP防水」です。
プラスチック樹脂にガラス繊維が混ざった「ガラス繊維強化プラスチック(FRP)」を使用して防水層を形成し、上にトップコートを塗り重ねていきます。
強度の高さはお墨付きで、新築の陸屋根や木造のベランダ床にも多く採用されているのが特徴。
特に、屋根に出入りする回数が多い方におすすめです。
ウレタン防水のようにウレタン樹脂を何度も塗り重ねる必要がないので、工期はさらに短く済みます。
ただ、施工費用やメンテナンス費用はウレタン防水に比べて高額です。
加えて、広範囲に及ぶ木造の床には施工できない可能性があるので注意してください。
費用相場(1㎡あたり):4,000円~7,500円
耐用年数:10年~12年
工期:1日~2日
2.シート防水
屋根の床面に専用のシートを貼って防水する工法が「シート防水」です。
施工費用が安く耐用年数も長いので、コストパフォーマンスに優れた工事方法だといえるでしょう。
広い面積に1度で施工できるので、アパートやマンションの屋上に採用されることが多いのが特徴。
ただ、狭い部分だとシートを貼るのが難しくなるため、室外機などの設置物が多い陸屋根には向きません。
また、風が強い地域に建物がある場合は、シートが飛ばされてしまう可能性があるので注意が必要です。
シート防水は、さらに「塩化ビニールシート防水」と「ゴムシート防水」の2つに分かれます。
以下で詳しく見ていきましょう。
●塩化ビニールシート防水
塩化ビニールでできたシートを使った工法が「塩化ビニール防水」です。
紫外線にさらされたり、衝撃を受けたりしても傷みづらく、耐久性に優れています。
また、デザインのバリエーションが豊富で、模様がプリントされているものもありますよ。
ただ、シートをうまくつなぎあわせるにはある程度の技術が必要です。施工実績が豊富で、安心して任せられる業者に依頼するようにしましょう。
費用相場(1㎡あたり):3,500円~7,000円
耐用年数:10年~20年
工期:1日~4日
●ゴムシート防水
合成ゴムでできたシートを使った工法が「ゴムシート防水」です。
ゴム素材なので柔軟性が高く、地震に強いのがメリット。昔は主流の防水工事のうちの一つでした。
ただ、シートが薄い分耐久性が下がるので、現在では他の工法を選ぶ方が増えています。
工期が短く低コストなので、「すぐに大がかりな工事はできないけど、とりあえず部分的に補修したい」という場合におすすめです。
費用相場(1㎡あたり):2,500円~7,500円
耐用年数:10年~15年
工期:1日~4日
3.アスファルト防水
もっとも歴史が長く、従来から広く使われている工法が「アスファルト防水」です。
液状に溶かしたアスファルトを、合成繊維不織布のシートに染み込ませてコーティングした「ルーフィングシート」を貼り重ねて、防水機能をより強固なものにしていきます。
広い場所への施工が適しているため、学校・大型マンション・公共施設などの屋上によく採用されているのが特徴。
人が歩行する場合は保護モルタルを貼る必要がありますが、保護モルタルを貼ると屋根が重くなるので、木造住宅には向きません。
人が立ち入らない陸屋根に採用するのがおすすめです。
アスファルト防水はさらに、「熱工法」「トーチ工法」「常温工法」の3つに分かれます。
以下で詳しく見ていきましょう。
●熱工法
200度以上の高温で溶かしたアスファルトを使用して、アスファルトルーフィングシートを積み重ねていく工法が「熱工法」です。
100年以上もの歴史がある信頼性が高い工法ですが、施工中に熱・煙・臭いなどが発生するのがデメリット。
周辺環境への配慮が必要になるため、最近ではあまり行われなくなりました。
溶かしたアスファルトは適切な温度でなければ接着力が弱くなるので、高い技術が必要になる工法でもあります。
費用相場(1㎡あたり):7,800円程度
耐用年数:15年~25年
工期:6日~10日
●トーチ工法
バーナーを使ってアスファルトルーフィングの裏面を溶かし、貼り重ねていく工法が「トーチ工法」です。
熱工法のようにアスファルトを溶融する必要がないので、煙や臭いの心配がありません。
ただバーナーを使用するので、火災のリスクがあるのがデメリットです。
近くに燃えやすいものがあると、施工できません。
費用相場(1㎡あたり):8,200円程度
耐用年数:15年~20年
工期:6日~10日
●常温工法
現在、多くの現場で採用されているのが「常温工法」です。
ルーフィングシートの裏面に、ゴムアスファルトでできた粘着層をコーティングし、複数枚を交互に貼り合わせていきます。
熱工法やトーチ工法とは異なり熱を使わずに防水層をつくるので、安全性が高いのがメリット。
ただ、熱を使用する工法よりも防水層の密着度が劣るので、耐久性が低くなるのが難点です。
費用相場(1㎡あたり):8,900円程度
耐用年数:15年~20年
工期:6日~10日
陸屋根の防水を長持ちさせるコツ4つ
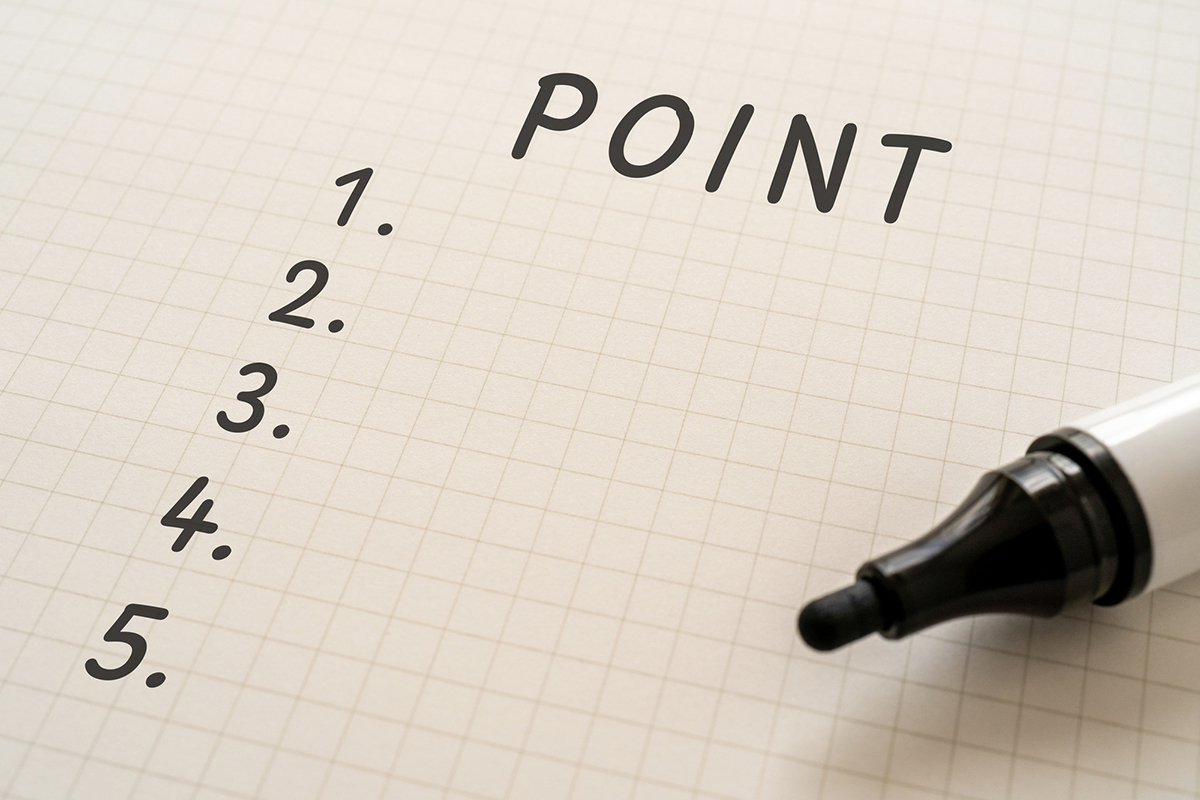
陸屋根の防水を長持ちさせるコツを、4つ紹介します。
1.排水溝(ルーフドレイン)を定期的に掃除する
2.色褪せてきたらトップコートを塗り替える
3.室外機は直接置かない
4.陸屋根の上では植物は育てないようにする
せっかくお金をかけて防水工事をしたなら、防水効果はなるべく長持ちさせたいですよね。
メンテナンスの頻度を減らすためにも、上記の4つのコツを意識して生活するようにしてください。
以下で詳しく解説していきます。
1.排水溝(ルーフドレイン)を定期的に掃除する
排水溝(ルーフドレイン)は、定期的に掃除するようにしましょう。
本来なら陸屋根に溜まった雨水は、排水溝に流れていく仕組みになっています。
しかし、排水溝にゴミや枯葉などが詰まっていると、雨水がスムーズに排出されません。
雨水が流れていかないと陸屋根に水たまりができ、防水層の劣化を早めてしまいますよ。
また、排水溝付近が汚れていると、飛んできた雑草の種子も発芽しやすくなります。
雑草の繁殖は、防水層を突き破る可能性があるので危険です。
上記のような事態を防ぐために、排水溝をこまめに掃除して、清潔な環境を保つようにしましょう。
2.色褪せてきたらトップコートを塗り替える
トップコートが色褪せてきたら、早めに塗り替えるのがおすすめです。
トップコートは、紫外線から防水層を守ってくれています。
しかし、トップコートが色褪せているということは、保護機能が失われてきている証拠。
放置していると防水層が紫外線の影響を受けるので、劣化が進んでしまいます。
トップコートの塗り替え時期の目安は、5年〜10年程度。
トップコートの塗り替えだけなら費用も安く済むので、こまめに点検を依頼するようにしましょう。
3.室外機は直接置かない
陸屋根の上に室外機を直接置くのは、できれば避けてください。
直置きしてしまうと防水層に負担がかかるので、寿命が縮まってしまうかもしれません。
室外機を陸屋根に置く必要がある場合は、ゴム板の上に設置するなどの工夫をしましょう。
4.陸屋根の上では植物は育てないようにする
陸屋根の住宅に住めば、「屋上庭園を楽しみたい」と思う方は多いでしょう。
ただ、防水機能を長もちさせたいなら、陸屋根の上では植物は育てないようにするのがおすすめです。
植物を育ててしまうと、種子が風に飛ばされて、陸屋根の床面で発芽してしまうかもしれません。
植物が床面に根を張ってしまうと、雑草と同じように、防水層を突き破ってしまう危険性がありますよ。
どうしても植物を育てたい場合は、種子や土が散らばらないように、こまめに掃除するようにしてください。
陸屋根の防水工事を自分でDIYするのはおすすめできない

陸屋根の防水工事を自分でDIYするのは、あまりおすすめできません。
防水工事は、高い技術が必要になる作業です。
もし自分で行って失敗した場合、結局は業者に工事を依頼しなければならないため、二度手間になってしまいます。
また、DIYが成功したとしても、業者に依頼するよりも見た目が悪くなってしまう可能性が高いです。
さらに、正しい下処理を行い適切な手順を踏んでいないと、本来の耐用年数よりも短くなってしまう場合も。
無理に自分で行うよりも、専門業者に依頼した方が安心です。
どうしても自分でDIYしたい場合は、施工が比較的手軽な工法である「ウレタン防水」で行うようにするとよいかもしれません。
陸屋根の防水工事で業者を選ぶときのポイント4つ

陸屋根の防水工事で業者を選ぶときのポイントを、4つ紹介します。
1.複数の業者から見積もりをとって比較する
2.保証やアフターフォローの内容を確認する
3.施工実績を確認する
4.利用者の口コミを参考にする
「仕上がりのきれいさ」や「耐用年数」は、工事を行う業者の技量によって変化します。
技術力が高く信頼できる業者を選べば、メンテナンスの頻度も減らせるでしょう。
上記の4つのポイントを意識しつつ、優良な業者を見極めてください。以下で詳しく解説していきます。
1.複数の業者から見積もりをとって比較する
はじめから1つの業者に絞るのではなく、複数の業者に見積もりを依頼するようにしましょう。
業者によって、使用する材料やサービス内容、金額などは大きく異なります。
業者を比較しないまま決めてしまうと、「もっと安くてサービス内容も充実している業者が他にあったのに」と後悔してしまうかもしれません。
また、複数の業者から見積もりをとっていれば、料金の相場感がわかります。
激安料金で手抜き工事する悪徳業者や、高額な値段を請求する詐欺業者がいても、すぐに見極められるでしょう。
信頼できる業者を見つけるためにも、必ず複数の業者に見積もりを依頼してください。
2.保証やアフターフォローの内容を確認する
保証やアフターフォローの内容を確認しておくことも大切です。
せっかく高い料金を払って工事を依頼したのに、すぐに不具合があったら、お金を無駄にしたような気持ちになりますよね。
上記のようなときに、保証制度を設けている業者に依頼していれば、保証期間内であれば無料で補修を行ってもらえます。
ただ、「自然災害による損傷には保証は適用されない」などの免責事項がある場合がほとんどなので、注意が必要です。
保証やアフターフォローの内容も事前にしっかりと確認しておき、万が一の事態に備えましょう。
3.施工実績を確認する
施工実績が豊富な業者を選ぶようにしましょう。
施工実績が多いということは、それだけ沢山の利用者から信頼されているということです。
技術力がある職人を抱えているという証にもなるでしょう。
施工実績が豊富な業者であれば、公式サイトやパンフレットなどに「施工実績〇件」などと記載している場合が多いです。
また、公式サイトや自社のSNSなどで、実際の「施工写真」を公開している業者も信頼できます。
数字や写真など、目に見える実績を確認してから工事を依頼するようにしましょう。
4.利用者の口コミを参考にする
利用者の口コミも参考にしたうえで、業者を選ぶようにしましょう。
実際に工事を依頼した人たちのリアルな意見は、何よりも参考になる情報です。
「仕上がりがきれいだった」「担当者が丁寧に説明してくれた」などの口コミがあれば、信頼できる業者だといえるでしょう。
一方で、「施工不良が見つかった」「担当者の対応が悪かった」などの口コミが寄せられている場合は、安心して工事を任せられる業者ではありません。
口コミはGoogleマップや口コミサイトなどで確認できるので、しっかりとリサーチしておきましょう。
陸屋根の防水工事の補助金・助成金

陸屋根の防水工事を行う場合、地方自治体から補助金・助成金などを受け取れる可能性があります。
防水工事や外壁塗装など、経年劣化対策のリフォームに対して、独自の支援事業を行っている自治体があるからです。
ただ、支援事業は全国共通ではなく、地方自治体によって異なります。
また、毎年決まってあるものでもなく、年度によって対象となる工事や支援額も変化します。
まずはお住まいの地方自治体に問い合わせて、支援制度の有無を確認してみましょう。
陸屋根の防水工事に関するよくある質問

最後に、陸屋根の防水工事に関するよくある質問4つに回答します。
1.コケが生えていたら防水工事は必要?
コケが生えているからといって、防水工事を行う必要はありません。
もともと陸屋根は雨水が溜まりやすいので、コケが発生することがよくあります。
コケの他にも何か劣化症状が見られたら、点検やメンテナンスを依頼しましょう。
また、コケが生えていると床面が滑りやすくなるので、こまめに除去しておくのがおすすめです。
2.陸屋根はコーキング材で防水できる?
陸屋根の小さなひび割れなら、コーキング材で補修できる可能性はあります。
ただ、コーキング材で対応可能か、防水工事が必要かの判断は、素人では難しいです。
したがって、自分で勝手に判断して、DIYで補修するのはおすすめできません。
信頼できる業者に相談するようにしましょう。
3.すでに雨漏りが起きているときの緊急対処法は?
すでに雨漏りが起きているときは、応急処置として以下を行ってください。
・家電や家具を避難させる
・雨漏りの水滴を受け止める容器を設置して、床を保護する
・湿気がこもらないように換気する
・漏水している箇所にブルーシートなどを被せて一時的に防水する
ただ、上記はいずれも一時的な処置に過ぎません。
雨漏りが発生しているということは、防水機能が失われている証拠なので、早急にメンテナンス工事を依頼しましょう。
4.新築時には防水工事はされている?
新築住宅の場合、陸屋根の床面やベランダ、バルコニーなどの水はけが悪い場所には、防水工事が施されているのが一般的です。
ただ、防水効果がどれくらい持続するのかは、材料・職人の技術・立地・環境などによって変わるので予想できません。
定期的に点検を依頼して、劣化症状を見逃さないことが大切です。
防水工事を適切に行い陸屋根を長持ちさせよう!

陸屋根を長持ちさせるには、定期的な防水工事が必要不可欠です。
防水工事を怠ると、雨水が建物内部まで染み込み、雨漏りや建材の腐食などを引き起こしてしまうかもしれません。
防水工事と一口にいっても、さまざまな工法があります。
工法によって費用やメリットが異なるので、しっかりとリサーチして、自分に合った方法を見つけることが大切です。
劣化症状が現れてからメンテナンスを依頼するのではなく、こまめに点検を依頼して、美しい陸屋根を保ちましょう。
外壁塗装の窓口は、全国4000社以上の優良店の中からユーザーの要望に沿った施工店をご紹介します。見積もりを依頼後でも料金や施工店の対応に納得がいかなければ断ることも可能なので、気軽に利用してみてくださいね。
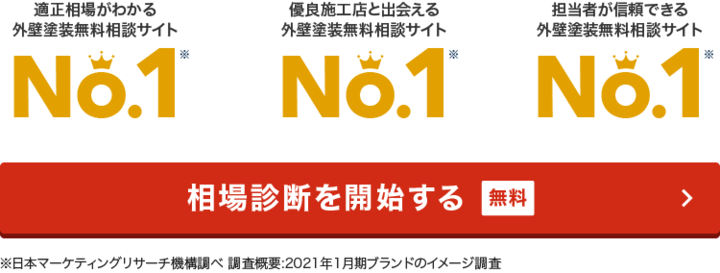
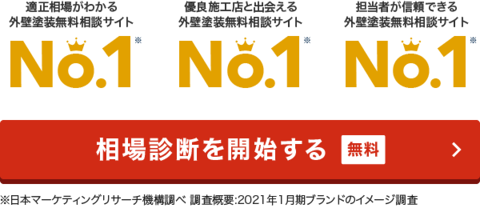
アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ
部屋を借りる!賃貸版はこちら
住宅を買う!購入版はこちら


 サイディング外壁はDIY塗装できる?手順・費用・失敗を防ぐコツを解説
サイディング外壁はDIY塗装できる?手順・費用・失敗を防ぐコツを解説
 屋根修理はDIYでできる?自分で直せる範囲と屋根材別の手順・安全対策を解説
屋根修理はDIYでできる?自分で直せる範囲と屋根材別の手順・安全対策を解説
 【2025年最新】兵庫県の外壁塗装につかえる助成金・補助金一覧!対象市町村と申請の流れを解説
【2025年最新】兵庫県の外壁塗装につかえる助成金・補助金一覧!対象市町村と申請の流れを解説
 火災保険の屋根修理は経年劣化だと対象外?条件・具体例・見分け方を解説
火災保険の屋根修理は経年劣化だと対象外?条件・具体例・見分け方を解説