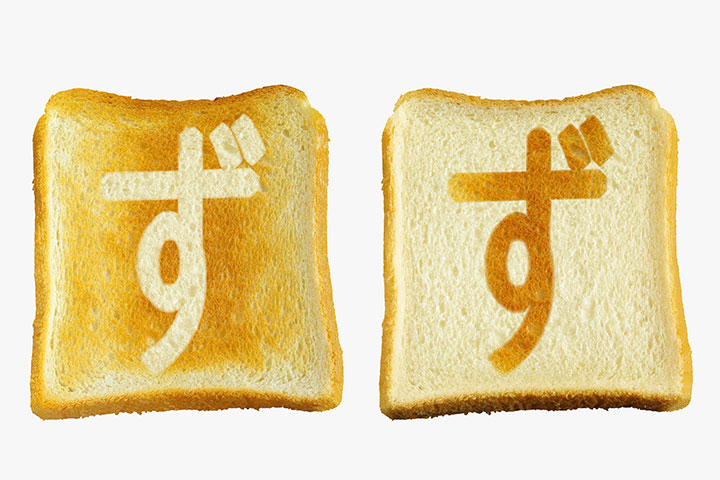「瞑想に挑戦してみたくて、具体的なやり方が知りたい」と考えている方は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、瞑想のやり方を初心者向けにわかりやすく解説します。
また、瞑想で期待出来る効果やコツ、注意点なども併せて取り上げます。
本記事を読めば、今日からでも瞑想に取り組めるようになるはず。 ぜひ最後まで読み進めてみてください。
- 瞑想とは?
- 瞑想の起源・歴史
- 正しいやり方で瞑想を行うと期待できる効果5つ
- 瞑想のやり方の前に知っておこう!代表的な瞑想の種類
- 【初心者向け】マインドフルネス瞑想のやり方
- 超越瞑想(TM瞑想)の簡単なやり方
- ヴィパッサナー瞑想の簡単なやり方
- 瞑想を継続していくコツ3つ
- やり方と一緒に把握しておこう!瞑想を行うための環境づくり
- 初心者が瞑想を行う際の注意点3つ
- Instagramから瞑想に役立つ情報を紹介
- 瞑想のやり方に関するよくある質問
- 正しいやり方で瞑想に挑戦してみよう!
瞑想とは?

瞑想とは、心を落ち着かせて自分の内側に意識を向け、脳をリフレッシュさせるトレーニング全般のことを指します。
お寺で行う「座禅」を思い浮かべるとイメージしやすいでしょう。
瞑想の別名は「メディテーション」です。メディテーションの由来は、ラテン語の「meditatio」。
「meditate」には、精神的および身体的な訓練・練習という意味があります。
仕事や家事、育児などで忙しい毎日を過ごしていると、ついつい自分の内側に意識を向けることを忘れてしまいますよね。
心に余裕がないと、不安や緊張に苛まれやすくなります。
その結果、集中力が欠如したり、パフォーマンスが低下したり、といった不具合が起こりやすくなるでしょう。
しかし、定期的に瞑想を行う習慣があれば、自分の内側に意識を向ける癖がつきます。
不安や緊張を感じていたとしても、瞑想の時間はしがらみから解放されて自由になれます。
そうすれば心に余裕が生まれるので、パフォーマンスも向上しやすくなるでしょう。
話題のマインドフルネス瞑想と瞑想の違い
医療や教育、ビジネスの分野などで最近注目が高まっている「マインドフルネス瞑想」。
「マインドフルネス瞑想と瞑想の違いって何?」と疑問に思っている方は多いでしょう。
実は瞑想にはさまざまな種類があり、マインドフルネス瞑想も瞑想の一種。
瞑想は、たとえば呼吸や体の感覚など、何らかの対象に意識を向ける場合が多いです。
しかしマインドフルネス瞑想は、「今」に意識を向けます。
食事をしながら次にやることを考えたり、電車に乗りながらスマホを操作したりするのではなく、今自分が行っている所作に集中します。
そうすることで感覚が研ぎ澄まされ、集中力や判断力が増すと考えられているのです。
瞑想の起源・歴史

瞑想の歴史は長く、インダス文明の頃まで遡ります。
モヘンジョダロ遺跡から見つかった印章の中に、人が座禅を組んで瞑想しているような図柄が見つかったそうです。
また今から2500年前頃には、ブッダが瞑想法について説いて光明を得たといわれています。
日本に瞑想が伝わったのは、6世紀半ば頃。仏教が日本に伝来したときに、瞑想も教えの一部として広まったそうです。
昔は今よりも医療が発達していなかったため、病気や死による不安が今よりも身近なところにありました。
したがって、昔の人たちにとって瞑想は、心の平安を保ち、前向きに生きていくために必要な手段だったのです。
正しいやり方で瞑想を行うと期待できる効果5つ

瞑想を行うと期待できる効果を、5つ紹介します。
1.集中力・注意力の向上する
2.ストレスの緩和
3.睡眠の質が上がる可能性がある
4.痛みの軽減効果も報告されている
5.精神疾患へのプラスのアプローチ
瞑想の習慣を日常に取り入れたいと考えている方は、チェックしておきましょう。
以下で詳しく解説していきます。
1.集中力・注意力が向上する
瞑想を日常的に行うことで、集中力・注意力が向上したという結果が報告されています。
集中力や注意力を示す指標とされているのが、「実行機能(目標を持って行動をコントロールする力)」です。
スペインにあるグラナダ大学のカセダス博士は、瞑想と実行機能の関連を調べる研究を行いました。
約1100人の被験者を対象にした調査で、「瞑想によって実行機能が改善した」という結果が得られたそうです。
実行機能が正常に働いていれば、頭と心を上手く組み合わせて使えるようになります。
複数の作業を並行して行っていたとしても、ミスなく迅速に進められるようになるでしょう。
2.ストレス緩和が期待できる
瞑想によって、ストレスが緩和される可能性があります。
人間関係や仕事、家庭問題など、現代社会で生きていると、ストレスを感じる場面は沢山ありますよね。
そのほとんどが、「考えすぎてしまうこと」からくるといわれています。
瞑想を行えば、心がリラックスした状態になり、意識を自分の内側や「今」に向けられます。
その間は感じている不安や緊張から解放されるので、心にゆとりが生まれるでしょう。
実際に、アメリカにあるハーバード大学のクーリー博士らによって行われた研究では、「マインドフルネスがストレス低減に対して有効だった」という結果が出ていますよ。
3.睡眠の質が上がる可能性がある
睡眠の質が上がる可能性があるのも瞑想の魅力です。
米国国立衛生研究所のラッシュ博士らは、瞑想が睡眠に与える効果について、約1600人を対象に調査を行いました。
その結果、「瞑想には薬物療法と同等の効果がある」と判明。
瞑想は、不眠症の対処法の一つとして広まりつつあります。
睡眠に関する悩みがある方は、寝る前の20分〜30分程度、瞑想の時間を設けてみるのも良いかもしれません。
4.痛みの軽減効果も報告されている
「瞑想を行うと痛みが軽減した」という研究結果も報告されています。
瞑想によって、痛みに集中していた注意が、呼吸や体の感覚などに向くからです。
傷や炎症が完治したわけではなくても、痛みの感じ方が変化します。
また、瞑想によって心に余裕が生まれると、不安や恐怖など、痛みに伴うネガティブな感情も和らぐ場合が多いです。
結果として、体や心にかかる負担を減らせるでしょう。
5.精神疾患にもプラスのアプローチをしてくれる
精神疾患にもプラスのアプローチをしてくれるのが瞑想です。
具体的には、以下のような症状に効果が見込めます。
・うつ病
・不安症
・パニック障害
・摂食障害
・適応障害
ただ、PTSD(ストレス障害)や重度のうつ病を患っている場合は、瞑想が逆効果になってしまう可能性もあります。
瞑想を取り入れる際は、必ず医師に相談するようにしてください。
瞑想のやり方の前に知っておこう!代表的な瞑想の種類

一口に瞑想といっても、さまざまな種類があります。
どの瞑想が合っているかは人によって違うので、瞑想の種類や特徴を把握しておくことは大切です。
この章では、代表的な瞑想8種類を紹介します。
1.マインドフルネス瞑想
2.超越瞑想(TM瞑想)
3.ヴィパッサナー瞑想
4.サマタ瞑想(集中瞑想)
5.ボディスキャン瞑想
6.禅(座禅)
7.食事瞑想
8.歩行瞑想
以下でそれぞれの特徴を解説していくので、ぜひ参考にしてください。
1.マインドフルネス瞑想
過去や未来ではなく、「今」に意識を向けるのが「マインドフルネス瞑想」です。
私たちが感じる不安の原因のほとんどが、過去や未来に関する雑念。
「あのときこうしていれば良かった」や「もしこうなってしまったらどうしよう」などと、無意識のうちにネガティブな思考に支配されている方は多いのではないでしょうか。
マインドフルネス瞑想によって「今」に意識を集中させれば、上記のような後悔や不安から解放され、心にゆとりが生まれやすくなります。
2.超越瞑想(TM瞑想)
「超越瞑想」は、インドのヴェーダ哲学に由来する瞑想です。
マントラ(特定の音や言葉)を心の中で唱え続け、深いリラクゼーション状態に入ります。
思考をコントロールしたり、集中しようとしたりするのではなく、心が自然と落ち着くのを待つのが特徴です。
3.ヴィパッサナー瞑想
「ヴィパッサナー瞑想」は、古代インドで発祥した伝統的な瞑想法です。
「ヴィパッサナー」という言葉には、「物事をありのままに見る」という意味があります。
つまり、自分の今の状態を観察することを重視するのが「ヴィパッサナー瞑想」。
静かな環境の中で、体の感覚や心の状態に意識を向けていきます。
今の自分のありのままの姿を知る作業は、心の安定に繋がるだけではなく、日常生活にも活かされていくでしょう。
4.サマタ瞑想(集中瞑想)
「サマタ瞑想」とは、仏教用語のサマタ(止)を語源とする瞑想です。
呼吸や音、光など、対象物を設けて集中し、心を落ち着かせていきます。
対象物は、雨の音やキャンドルの炎、スマホ画面で流したロウソクの映像など、取り組みやすいもので大丈夫です。
注意を向ける対象がはっきりしているので、初心者でも挑戦しやすい瞑想だといえるでしょう。
5.ボディスキャン瞑想
「ボディスキャン瞑想」とは、体の各部分に意識を向けて、感覚を観察していく瞑想法です。
呼吸からはじまり、足の指、ふくらはぎ、膝、太もも…というように、順番に意識を移動させていきます。
重さや温かさ、痛みや痒みなどを、感じたままに受け取ることが大切です。
体の感覚に意識を向けることで心の緊張がほぐれるので、ストレス軽減や睡眠の質向上などにつながりますよ。
座ったままでも、横たわった状態でもできる瞑想法です。
6.禅(座禅)
仏教の修行法の一つで、日本人に古くから馴染みがあるのが「禅」です。
姿勢を整えて呼吸に集中し、あらゆる思考や感情を手放します。
心を無の状態にすることで平穏が得られ、自己理解や内面の成長へと繋がります。
目は半眼にして視線を前方に落とすと、思考を手放しやすくなりますよ
7.食事瞑想
食べることに意識を集中させる瞑想が、「食事瞑想」です。
食材の味や食感、香りに意識を向けて、ゆっくりと食事を摂ります。
私たちは普段、テレビやスマホを見ながら食べたり、誰かと話しながら食事をしたりする場合が多いですよね。
食事瞑想で「食べる」行為だけに意識を向ければ、よりリラックスした状態で食事を楽しめるようになります。
食べ物への感謝の気持ちが育まれたり、しっかりと噛むことで満腹感が得られたり、というようなメリットもありますよ。ぜひ取り入れてみてください。
8.歩行瞑想
座って行う他の瞑想とは違い、歩きながら行うのが「歩行瞑想」です。
足の感覚や周りの環境に意識を向けて雑念を払い、心を落ち着けていきます。
一歩一歩に注意を向けて、地面の感触や前に進む感覚を大切にするのがポイント。
そうしているうちに、自然と余計な思考がなくなっていきます。
ウォーキングは運動不足解消にもなるので、精神面だけではなく身体面にも良い影響が出るといえるでしょう。
【初心者向け】マインドフルネス瞑想のやり方

今話題のマインドフルネス瞑想のやり方を、初心者向けにわかりやすく解説します。
1.リラックスした状態で座る
2.呼吸に意識を集中させる
3.思考が浮かんだら呼吸に意識を戻す
以下で詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてください。
1.リラックスした状態で座る
まずは床に座布団やクッションなどを敷き、あぐらをかいて腰掛け、良い姿勢をつくります。
あぐらが難しい方は、正座をしたり、椅子に座ったりしても構いません。
手のひらは下に向けて、膝や太ももの上に置きます。
目は伏し目がちにして、前方の床を見つめましょう。
2.呼吸に意識を集中させる
姿勢が整ったら、ゆっくりと「今の呼吸」に意識を向けていきます。
自然な呼吸を続けて、リズムを感じ取りましょう。
3.思考が浮かんだら呼吸に意識を戻す
思考が浮かんでしまったら、その思考を追わず、「考えた!」と心の中で唱えてから、呼吸に意識を戻してください。
考えてしまった自分を責める必要はありません。
浮かんだ思考に「良し悪し」などの判断を加えず、呼吸に意識を戻すことは、「今」に戻ってくる練習になります。
続けていれば、自然と「今」を感じ取れるようになるでしょう。
超越瞑想(TM瞑想)の簡単なやり方

初心者でも挑戦できる超越瞑想(TM瞑想)のやり方を、わかりやすく解説します。
1.目を閉じてリラックスした状態で座る
2.マントラを心の中で唱える
3.10分間続ける
以下で詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてください。
1.目を閉じてリラックスした状態で座る
まずは床に座布団やクッションなどを敷き、あぐらをかいて腰掛け、良い姿勢をつくります。
マインドフルネス瞑想と同様に、あぐらが難しい方は正座をしたり、椅子に座ったりしても構いません。
手のひらは膝の上に置き、リラックスしましょう。
2.マントラを心の中で唱える
姿勢がつくれたら、マントラを心の中で唱えます。
代表的なマントラを以下に記載するので、唱えやすいものや、気に入ったものを選んで実践しましょう。
・オーム…「宇宙の始まりの音」「根源的な音」などの意味がある
・ソーハム…「私はそれ」という意味があり、大宇宙との一体化を象徴する
・シャンティ…平和・静寂・平穏などの意味がある
・オム・マニ・ペメ・フム…観音菩薩の慈悲を表し、唱えれば心が浄化される
3.10分間続ける
最初は短時間でも構いませんが、慣れてきたら10分程度はマントラを唱え続けるようにしましょう。
ヴィパッサナー瞑想の簡単なやり方

初心者でも挑戦できるヴィパッサナー瞑想のやり方を、わかりやすく解説します。
1.目を閉じてリラックスした状態で座る
2.呼吸に意識を集中させる
3.身体の感覚・感情・思考などを観察する
以下で詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてください。
1.目を閉じてリラックスした状態で座る
まずは床に座布団やクッションなどを敷き、あぐらをかいて腰掛け、良い姿勢をつくります。
先述したように、あぐらが難しい方は正座をしたり、椅子に座ったりしても構いません。
手のひらは下に向けて、膝や太ももの上に置きます。
目は優しく閉じましょう。
2.呼吸に意識を集中させる
姿勢がつくれたら、呼吸に意識を向けていきます。呼吸のリズムを感じながら、自然に「吸って・吐いて」を続けましょう。
3.身体の感覚・感情・思考などを観察する
呼吸に意識を向けられたら、今度はその集中を感覚・感情・思考に移していきます。
「今自分が何を感じているのか」「今自分が何を考えているのか」を冷静に観察してください。
深く考えるのではなく、あくまで第三者のように「観察する」ことがポイントです。
続けていると、自分の感情や歯垢のパターンがわかってくるので、自己理解が深まります。
瞑想を継続していくコツ3つ

瞑想を継続していくコツを、3つ紹介します。
1.気楽な気持ちで取り組む
2.起床後や就寝前に取り入れる
3.通勤・通学時間を利用してみる
瞑想に対して「面倒くさい」「なかなかうまくいかない」などのネガティブな感情を抱いてしまうと、継続するのが難しくなります。
長く続けていくためにも、3つのコツをチェックしておきましょう。以下で詳しく解説していきます。
1.気楽な気持ちで取り組む
「毎日欠かさずやる」と力みすぎるのではなく、気楽な気持ちで取り組むのがポイントです。
義務として捉えてしまうと、「瞑想を行う」こと自体がストレスになってしまいます。
続けていると、体調や気分、仕事の忙しさなどでできない日もあるでしょう。そんなときは自分を責めるのではなく、「また明日やれば良い」と気楽に考えてください。
そうすれば、自然と日常生活に取り入れられるようになりますよ。
2.起床後や就寝前に取り入れる
初心者の方は、起床後や就寝前に行うようにすると取り組みやすいです。
ベッドの上でそのまま行えるので、日中にわざわざ瞑想の時間を設けるよりも手間がかかりませんよね。
起床後に瞑想を行うと、心が落ち着き、前向きな気持ちで1日をスタートできます。また、就寝前に瞑想を行うと、1日の疲れが癒されて、睡眠の質向上にもつながるでしょう。
数分でも良いので、無理のない範囲で取り入れてみてください。
3.通勤・通学時間を利用してみる
通勤・通学の時間を利用するのもおすすめの方法です。
さまざまな瞑想アプリがリリースされているので、活用しましょう。イヤホンで音声を聞きながら、ガイドに従って瞑想に取り組んでみてください。
瞑想アプリを利用せず、リラックスできる音楽を聞きながら、自己流で行っても構いません。
通勤・通学中に瞑想を行えば、リラックス状態に入るので、電車内で感じるストレスも緩和されるでしょう。
やり方と一緒に把握しておこう!瞑想を行うための環境づくり

瞑想を行う際の環境づくりのポイントを、5つ紹介します。
1.静かな部屋を選ぶ
2.座りやすい場所を用意する
3.照明と温度を整える
4.電子機器の電源をオフにする
5.香りにこだわるのもおすすめ
以上の5つを意識して環境づくりをすると、瞑想中に自分の世界に入りやすくなりますよ。ぜひ実践してみてください。
以下で詳しく解説していきます。
1.静かな部屋を選ぶ
瞑想を行うときは、なるべく静かな部屋を選ぶようにしてください。
雑音に邪魔されると集中力が途切れて、自分の世界に入れなくなってしまいます。
外の音がうるさい場合は、窓を閉めて行うようにしましょう。
2.座りやすい場所を用意する
座布団やクッション、椅子など、座りやすい場所を用意しましょう。
瞑想中に痛みや不快感を感じてしまうと、集中力が途切れてしまいます。
長時間正しい姿勢を保っていられるように、自分に合ったスタイルを探してください。
座るのが難しい方は、横たわった状態で行う瞑想を選びましょう。
3.照明と温度を整える
照明と温度も大切な要素です。
暗すぎず明るすぎない、自分が集中しやすい照明をつくりましょう。瞑想専用に、雰囲気がある新しい照明を買い足すのもおすすめです。
また温度も、暑すぎず寒すぎない快適な温度に整えておくようにしてください。
4.電子機器の電源をオフにする
スマホやテレビなど、電子機器の電源はオフにしておくのがおすすめです。
電子機器の明かりや着信音、バイブレーションなどは、集中を妨げます。
瞑想の間はスマホやテレビのことは忘れて、自分自身としっかり向き合うようにしましょう。
5.香りにこだわるのもおすすめ
香りにこだわるのもおすすめの方法です。
好みの香りのアロマを焚いたり、芳香剤を使用したりすれば、リラックスした状態をつくりやすくなるかもしれません。
色々な香りを試しつつ、自分がやりやすい方法を見つけていきましょう。
初心者が瞑想を行う際の注意点3つ

初心者が瞑想を行う際の注意点を、3つ紹介します。
1.姿勢にこだわりすぎない
2.雑念が浮かんでも否定しない
3.効果を期待しすぎない
「瞑想に挑戦してみたけど、なかなかうまくいかない」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
うまくできない方は、ぜひ3つの注意点を意識してみてください。以下で詳しく解説していきます。
1.姿勢にこだわりすぎない
姿勢にこだわりすぎるのではなく、「心を落ち着かせること」を重視してください。
不快感を感じる姿勢を続けていると集中力が途切れて、リラックスできない可能性があります。
体が慣れないうちは、正しい姿勢を続けられなくても仕方ありません。自分がリラックスできる姿勢であれば、模範通りではなくても大丈夫です。
座り続けるのがしんどい方は、横たわった状態で瞑想を行ってみましょう。
2.雑念が浮かんでも否定しない
瞑想中に雑念が浮かんでも、「私に瞑想は向いていないのかもしれない」などと否定しないことが大切です。
浮かんだ雑念も受け入れて、静かに呼吸に意識を戻していきましょう。
私たちは日頃、沢山のことを頭の中で考えています。したがって、いきなり瞑想を始めても、心を無の状態にするのは難しいです。
続けていくうちに徐々にコツが掴めるようになるので、最初は焦らず、自分のペースで取り組んでいきましょう。
3.効果を期待しすぎない
瞑想に効果を期待しすぎないようにしましょう。
瞑想は薬物療法とは違うので、「必ず大きな効果が出る」ものではありません。効果には個人差があり、すぐに効果を感じる人もいれば、長く続けてやっと変化を実感する人もいます。
効果を期待しすぎてしまうと、変化がない場合に挫折しやすくなりますよ。
小さな変化に気づくことを目指して、無理なく続けていくようにしましょう。
Instagramから瞑想に役立つ情報を紹介
今回は、インスタグラムから瞑想に関する投稿を3つご紹介します。
瞑想初心者あるあるをご紹介
ヨガ・マインドフルネス瞑想講師として活躍されている、yoga_naginiさんの投稿からは瞑想初心者あるあるをご紹介します。
「無」が何か分からないことや瞑想中に眠くなってしまうなど、瞑想をはじめたばかりの初心者の方にとってあるあると思うことを、分かりやすく解説しています。ぜひチェックしてみてくださいね!
瞑想のすごい効果をご紹介
risa_yoga_wellnessさんの投稿では、瞑想のすごい効果についてまとめられています。
「集中力を高めたい」「良い1日のスタートを始めたい」という方は朝起きたら、「睡眠の質を高めたい」という方は夜寝る前に瞑想を取り入れるのがおすすめ。チャレンジしてみてくださいね!
天才に共通するシータ波をご紹介
robanosekaiさんの投稿では、創造性と直感力が飛躍的に向上すると言われている「シータ波」について紹介されています。
お風呂で突然いいアイデアが思い浮かんだり、眠る直前に「あ、そうか!」と気づいたり、これはシータ波によるものなのだそう。今すぐできる簡単なシータ波法も紹介されているので、さっそく真似してみましょう!
瞑想のやり方に関するよくある質問

最後に、瞑想のやり方に関するよくある質問4つに回答します。
1.瞑想は寝ながらでもできる?
瞑想は寝ながらでも取り組めます。
特に、「今」に意識を向けるマインドフルネス瞑想や、体の各部に意識を向けていくボディスキャン瞑想などがおすすめです。
座った状態よりも横たわった状態の方がリラックスできる方は、ぜひ試してみてください。
2.瞑想の理想的な回数や時間は?
瞑想の理想的な回数は、1日に1回〜2回です。
最初は5分〜10分程度から始めて、徐々に慣れていきましょう。
長い時間取り組めるようになったら、1回20分〜30分程度を目安に行ってください。
3.1分くらいの短時間瞑想でも効果は得られる?
短時間でも瞑想を習慣化していけば、ある程度の効果は見込めます。
最初は短時間から慣らしていき、徐々に時間を延ばしていくようにしましょう。
4.カジュアル瞑想って何?
カジュアル瞑想とは、日常生活に気軽に取り入れられる瞑想のことです。
自分の普段の行動に瞑想を組み合わせて、五感で感じ取る能力を高めていきます。
たとえば、キャベツの千切りをしながら、手の感覚に意識を集めていく「千切り瞑想」や、歯磨きをしながら口や歯の感覚に意識を向けていく「歯磨き瞑想」などがありますよ。
カジュアル瞑想は気軽に取り組めるので、ぜひチャレンジしてみてください。
正しいやり方で瞑想に挑戦してみよう!

日常の忙しさから離れて、自分の内側と向き合う時間をつくる「瞑想」。
日常生活に取り入れて習慣化すれば、ストレス緩和や集中力向上、睡眠の質改善など、さまざまな効果が期待できます。
一口に瞑想といっても、種類ややり方はさまざま。自分に合った方法を見つけることが大切です。
本記事では、瞑想のやり方を初心者向けに分かりやすく解説しました。
本記事の内容を参考にしつつ、あなたも今日から瞑想に取り組んでみてはいかがでしょうか。
アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ
部屋を借りる!賃貸版はこちら
住宅を買う!購入版はこちら


 蛇の夢は金運アップや幸運の兆し?大きさ・数・色・感情など状況別に意味を紹介
蛇の夢は金運アップや幸運の兆し?大きさ・数・色・感情など状況別に意味を紹介
 【2026年最新】チンチラの飼い方まとめ!種類ごとの価格相場や寿命、なつくコツを伝授
【2026年最新】チンチラの飼い方まとめ!種類ごとの価格相場や寿命、なつくコツを伝授
 フェネックを家で飼うには?必要な費用・防音対策・温度管理まで、後悔しないための飼育マニュアル
フェネックを家で飼うには?必要な費用・防音対策・温度管理まで、後悔しないための飼育マニュアル
 ゴミ袋がやぶれた!フローリングに残る不快な臭いを取る方法
ゴミ袋がやぶれた!フローリングに残る不快な臭いを取る方法