
ここでは、
・レジリエンスの心理学的な意味
・レジリエンスの使い方
・ビジネスやその他分野でのレジリエンスとは
・レジリエンスを高めるトレーニング方法
など、現代人に必要不可欠な「レジリエンス」について、わかりやすく解説します。
- レジリエンスとは?心理学的な意味
- 「レジリエンス」の使い方・類義語
- ビジネスにおけるレジリエンスとは?
- レジリエンスの「危険因子」「保護因子」とは?
- レジリエンスを妨げる考え方のクセ
- レジリエンスを高める具体的な方法
- レジリエンスとQOLを高めよう!
レジリエンスとは?心理学的な意味

レジリエンス(resilience)とは、
・回復力
・弾力性
・しなやかさ
などを意味する英語です。
「レジリエンス」という言葉は元々物理学や工学で使われてきました。これらの分野でレジリエンスは、「物体が外力によって変形した後、元の形状に戻ろうとする性質」を指します。
その後、レジリエンスは心理学でも応用されるようになり、「逆境や困難に適応しながら成長していく能力」「精神的回復力」「精神的抵抗力」といったニュアンスで使われています。
「レジリエンス」の対義語は「脆弱性(vulnerability)」。
精神医学や精神看護、社会福祉の分野でも、レジリエンスは重要視されているよ。
「レジリエンス」の使い方・類義語

レジリエンスという言葉は名詞ですが、形容詞は「レジリエント」。
・レジリエントな人
・レジリエントな社会
・レジリエントな会社
・レジリエントなインフラ構築
といった使い方がされます。
ここでは、「レジリエントな人」について、具体例を挙げてみます。
レジリエントな人は、思考の柔軟性や感情のコントロールに長けています。そのため、ストレス下の状況でも、成長や挑戦をし続けることができます。また、周りの人との信頼関係を築くことも得意です。
一方、レジリエントではない人は、ストレスに弱く、一喜一憂しやすい傾向があります。一度失敗すると落ち込みやすく、自己肯定感も低い場合が多いので、立ち直るのに時間がかかります。
また、レジリエンスには以下の類義語があります。それぞれの違いについて整理してみましょう。
レジリエンスと「メンタルヘルス」
メンタルヘルスとは、「心の健康状態」を意味する言葉です。強いストレスや慢性的な疲労が蓄積すると、うつ病や適応障害などの精神疾患に陥る可能性があります。メンタルヘルスには、心の健康管理や精神疾患を予防する取り組みも含まれます。
一方で、レジリエンスは、困難に直面した際の「適応力」や「回復力」を示す言葉です。
どちらも精神医療に関連する言葉ですが、レジリエンスは教育やトレーニングで個人の能力開発を促す場面でも使用されます。
レジリエンスと「ストレス耐性」
ストレス耐性とは、ストレス下での心理的・精神的な抵抗力を示す言葉です。ストレス耐性が高いほど、多くのストレスに適応できます。
ストレス耐性はレジリエンスを構成する要素の1つですが、
・ストレス耐性:ストレスに対する「防御力」「我慢強さ」
・レジリエンス:ストレスフルな状況からの「回復力」「成長性」
といった意味合いがあります。
参考:ストレス耐性|厚生労働省
レジリエンスと「ハーディネス」
ハーディネスとは、「ストレスに動じない、精神的な強靭さや傷つきにくさ」で、メンタルの防御力を表す言葉です。
ハーディネスとレジリエンスは混同されがちですが、
・ハーディネス:困難に直面しても、傷つかない打たれ強さ
・レジリエンス:困難によって落ち込み傷ついても、そこから回復・適応する力
を意味します。
参考:ハーディネスを媒介して自己内省が抑うつに与える影響|科学技術振興機構
レジリエンスと「ストレスコーピング」
ストレスコーピングとは、「ストレスに対処する具体的な行動や考え方」で、ストレスを低減する技術や工夫を指します。
ストレスコーピングは、レジリエンスを発揮するためのスキルであり、
・問題焦点コーピング:ストレスの原因となっている問題に対して、解決策を見つけ出して実行する
・情動焦点コーピング:ストレスから生じる感情に対して、気晴らしや考え方を変えることで気分を調整する
などの具体的な手段で、ストレスに対処します。
レジリエンスは、困難を乗り越えて成長していく「総合的な力」であり、ストレスコーピングは、その過程で用いる「具体的な方法」を意味します。
レジリエンスは、単純に心の強さや精神力、忍耐力と思われがちだけど、レジリエンスを高めるためには、知恵と工夫が不可欠だよ。
ビジネスにおけるレジリエンスとは?

ビジネス分野でのレジリエンスは、
①不確実で変化する世界情勢や事象に対して、
②企業組織が柔軟・迅速に対応して、
③事業を持続・成長させていくこと
を表します。
レジリエンスがビジネス分野で注目を集めたきっかけは、2013年のダボス会議(世界経済フォーラム年次総会)で「レジリエント・ダイナミズム」がテーマに掲げられたことでした。
レジリエンスはその後、組織やシステムにおける強靭性を示す言葉として、ビジネス以外の分野でも幅広く使われるようになりました。
参照:世界経済フォーラム年次総会2013 レジリエント・ダイナミズム|World Economic Forum
ビジネスシーンにおけるレジリエンス
●レジリエンス経営
企業におけるリスクマネジメント:リスク管理体制の整備・強化
●災害レジリエンス
BCP(事業継続計画):災害やテロ、パンデミックなどの緊急時に、柔軟に事業を継続・復興すること
●サプライチェーン・レジリエンス
SCM(サプライチェーン管理):原材料調達が困難になったときに、すぐに代替策をとって最適化すること
●サイバー・レジリエンス
サイバー攻撃やシステム障害などの脅威に備えて、セキュリティや復旧対策を整備すること
●従業員のレジリエンス
METI(健康経営):経営的視点から従業員の健康管理を考えて、戦略的に実践すること
従業員のレジリエンスの具体例
・ストレスチェックやハラスメント対策などによって、職場での心理的安全性を高める
・個々の従業員のレジリエンスを高めることで、企業組織の健全性・成長性を向上させる
参考:健康経営|経済産業省
レジリエンスがビジネスで重視される理由
●予測しづらいビジネス環境に適応できる
現代は「VUCA時代」(社会やビジネスにおいて先を見通すことが困難な時代)と表現されています。そのため、どんな状況にあっても柔軟に対応できるレジリエンスは、企業組織・事業の安定性や継続性を担保する要素として、期待が寄せられています。
●困難が成長の糧となる
レジリエンスを高めると、それまでストレスと感じていた事象が、個々の成長を促すことにつながります。
・苦手な業務や新しい課題を克服する→新たな気づきや自信となる
・仕事上で他者と意見がぶつかる→互いの主張を理解し合い協調することで、より強固な信頼関係が結ばれる
その他分野でのレジリエンスの意味
●子どもの教育におけるレジリエンス
子どもは学校生活において、
・学校トラブル(いじめ・学級崩壊)
・学校生活の中断(災害・感染症流行による学級閉鎖)
などで、心にストレスがかかります。
そのため、子どもの教育現場ではレジリエンス教育(しなやかな適応力や成長力を育む教育)が求められています。
●SDGsにおけるレジリエンス
SDGs(持続可能な開発目標)の中にも「レジリエンス」が多数登場します。
「持続可能な開発のための2030アジェンダ」において、レジリエンスは「強靭性・強靭さ」と表されました。
参照:我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ
また、国内外の各機関において、レジリエンスは以下のように定義されています。
| 機関名 | レジリエンスの定義 |
|---|---|
| UNDRR(国連防災機関) | ハザードの影響に適時・効率的に抵抗、吸収、順応、変形、回復する能力 |
| 世界銀行 | ショックやストレスに直面しても、長期的な見通しを崩すことなく、生活水準を維持または転換させ、変化に対応する能力 |
| OECD(経済協力開発機構) | 長期的なストレス、変化、不確実性に直面した際に、構造や生活手段を積極的に適応・変革させながら、ショックを吸収・回復する能力 |
| 内閣官房 | 大規模自然災害時に、人命を守り、経済社会への被害が致命的にならず、迅速に回復する「強さとしなやかさ」を備えた国土、経済社会システムを平時から構築していくこと |
| JICA(国際協力機構) | 予期せぬ事態が起きたときに、早く立ち直れること、復元力、強靭(きょうじん)性、弾力性 |
参考:「レジリエンス社会の実現」に関する検討の経緯及び今後の方向性|経済産業政策局
それぞれでレジリエンスの細かい表現は異なりますが、「状況の変化に対し、適応・転換しながら回復する能力」という部分は共通しています。
●経済学におけるレジリエンス
経済のグローバル化で、一部地域の経済危機が全世界に波及するようになりました。そのため、経済学ではレジリエンスを、
①様々な事態を想定して、
②被害をできる限り最小化し、
③被害から迅速に回復する力
として、重視しています。
レジリエンスの「危険因子」「保護因子」とは?

レジリエンスは、「危険因子」と「保護因子」によって発揮されると考えられています。ここでは、これら2つの因子について簡単に解説します。
レジリエンスの「危険因子」とは?
レジリエンスの危険因子とは、レジリエンスの対象となるストレスや課題、逆境を意味します。
レジリエンスの危険因子には、以下のものが考えられます。
危険因子の具体例
・人間関係・家庭環境の不和
・病気
・貧困
・災害・戦争
・犯罪被害 など
危険因子をできるだけ減らして、レジリエンスを高めるには、
・様々な事象に幅広く興味・関心を持つ
・負の感情に囚われず、自らコントロールする
・将来への夢や目標を持ち、未来志向を心掛ける
などの対策が有効です。
レジリエンスの「保護因子」とは?
保護因子は、ストレスから立ち直ることができる要素を表します。
「逆境」である危険因子を「乗り越えられる」のが保護因子であり、防御因子とも呼ばれています。
レジリエンスの保護因子には、以下のものが該当します。
保護因子の具体例
・個人の性格・経験・能力
・周囲の人々との関係性・支援 など
有効な保護因子を増やすことは、レジリエンスを高める要因になります。
逆に、「自分はレジリエンスが低いな」と感じる人は、これらの保護因子が不足していないかチェックしてみましょう。
レジリエンスを妨げる考え方のクセ

ここでは、心の柔軟性を損ない、レジリエンスを妨げる2つの考え方についてお話しします。
ABC理論
「ABC理論」とは、
・A(Adversity)=出来事
・B(Belief)=考え方(認知・解釈)
・C(Consequence)=結果(感情・身体反応)
のことで、人は起こった出来事(A)を、自らの受け取り方(B)で解釈して、その結果、感情・身体反応(C)が引き起こされると考える理論です。
ABC理論では、同じ出来事であっても、認知や解釈によって、受け取り方が変わります。例えば、以下のようなネガティブな考え方をしていると、心の回復が遅くなってしまうでしょう。
A:出来事
職場の会議で、自分のアイデアが却下された
B:考え方
自分は否定された
C:感情
「この職場に自分は不要な人間だ。」
「上司や同僚が無能なせいで、自分が正当に評価されない。」
A-C理論
「A-C理論」は、出来事(A)と感情(C)が直結するという考え方です。
A-C理論では解釈(B)が存在しないため、自分で変えられる要素がなく、感情をコントロールできません。そのため、困難な出来事に対して、受け身な姿勢にならざるを得ません。
レジリエンスを高める具体的な方法

ここからは、レジリエンスを高める具体的な方法について紹介します。
ABCDE理論
「ABCDE理論」は、1955年に臨床心理学のアルバート・エリス博士が提唱した心理療法です。この理論を用いることで、自分の感情をコントロールしやすくなり、思考を変えることができます。
ABCDE理論では、以下の2つの概念が登場します。
・D(Dispute)=反論(自分の捉え方への疑問・反論)
・E(Effect)=効果(新しい信念・人生哲学)
自分の考え方(B)が正しいか、反論(D)を加えると、結果として感情(C)が変わり、よりよい効果(E)を得ることができるという論理です。
先ほどの具体例で、ABCDE理論を実践してみましょう。
A:出来事
職場の会議で、自分のアイデアが却下された
B:考え方
自分は否定された
D:Bに対する反論
今回は過半数の賛同を得られなかった
C:感情
「指摘された点を改善すれば、次回はもっとよい提案ができるな。」
E:効果
仕事へのモチベーションが上がり、ポジティブに取り組める
このように、出来事は変えられなくても考え方を変えることで、物事を多面的かつポジティブに捉えられるようになります。ABCDE理論を日常生活で実践できれば、レジリエンスを高めることができるでしょう。
レジリエンスの6つの要素
また、レジリエンスを高めるのに必要な要素として、アメリカ・ペンシルバニア大学のカレン・ライビッチ博士が、以下の「レジリエンス・コンピテンシー」を提唱しています。
①自己認識
例)自分の長所短所を知っている・自分の軸がある
②自制心(セルフコントロール)
例)マインドフルネスや瞑想を生活に採り入れている
③精神的柔軟性
例)物事を多面的・本質的に捉えられる
④現実的楽観性
例)自分ができることや優先事項を的確に把握して、前向きに取り組める
⑤自己効力感
例)「自分はできる」という自信がある
⑥つながり
例)周囲の人と助け合える関係性を築いている
レジリエンスの高い人の具体的な状態
・成功体験に基づいた自信がある
・信頼できる仲間がいて、いつでも助け合える
・安定した職業や金銭的余裕がある
・常に新しいことに興味をもち、勉強していて知識がある など
レジリエンスのチェックシート
レジリエンスは、考え方や習慣、行動を見直すことで、少しずつ改善できます。
まずは、以下のチェックリストを試してみてください。
●マインドセット
▢失敗や困難に向き合い、学びを得ようとしている
▢物事を多面的に見ている
▢他人からの評価よりも、自分ができることに集中できている
▢自分の強みを活かそうと努力している
●習慣
▢毎日小さな目標を立てて、達成感を味わっている
▢運動や趣味などでストレス発散ができている
▢毎日質のよい睡眠が充分にとれている
▢自分の価値観を大切に行動している
●つながり
▢困ったときに相談できる家族や友人がいる
▢周囲のサポートを素直に受け入れられる
▢感謝の気持ちを表現できる
次に、これらの中で改善したい項目を一つ選びましょう。
ここでは、例として「毎日質のよい睡眠が充分にとれている」を取り上げます。
最後に、選んだ項目について、1ヶ月間で達成できる計画を具体的に書き出してみてください。
| ステップ | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| ① | 改善したい項目 | 毎日質のよい睡眠が充分にとる |
| ② | 1ヶ月間の達成目標 | 毎日7時間以上・0時までに寝る |
| ③ | 具体的なスケジュールを立てる | ・22時:入浴する ・22時半:ストレッチをして、ハーブティーを飲む ・23時:間接照明にして、瞑想する ・23時半:部屋を暗くして、布団に入る |
| ④ | リマインダー | スケジュールに沿ってアラームを設定する |
| ⑤ | 週に一度点検・調整する | ・日曜の夜に、達成できた日数をメモする ・達成できなかった原因を書き出して、対策をとる |
| ⑥ | モチベーション維持の工夫 | カレンダーに〇をつけて、達成度を可視化する |
レジリエンスとQOLを高めよう!

ここまで、レジリエンスを高めるトレーニング法を紹介してきました。レジリエンスを鍛えれば、より強くしなやかに、時代の変化を乗り越えることができます。
また、レジリエンスはワークライフバランスの改善にも影響するので、ビジネスパーソンはこれを機にレジリエンスの向上に取り組んでみましょう。
そして、ワークライフバランスと同時に、QOL(生活の質)を見直すこともおすすめします。
ニフティ不動産では、住みたいエリアや沿線・駅ごとに、150以上のこだわり条件の中から厳選した物件を検索できます。通勤時間を短縮できる、自分のライフスタイルにあった物件をお探しの方は、ぜひニフティ不動産を活用してみてくださいね。
アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ
部屋を借りる!賃貸版はこちら
住宅を買う!購入版はこちら


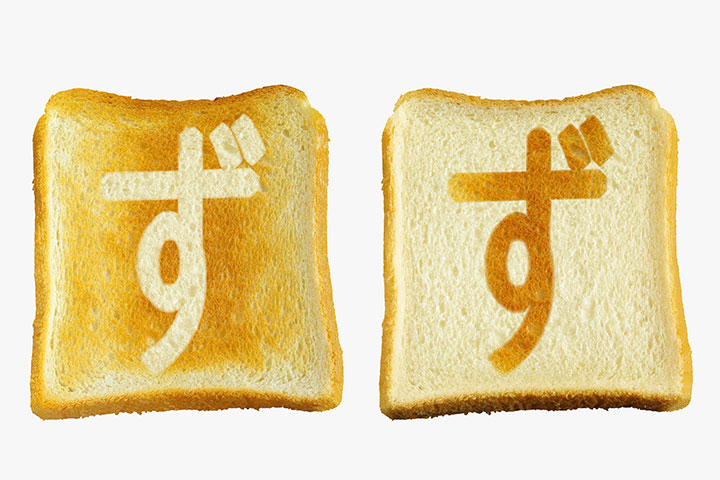 ずから始まる言葉は?絵しりとり・クロスワードで使える134選
ずから始まる言葉は?絵しりとり・クロスワードで使える134選
 蛇の夢は金運アップや幸運の兆し?大きさ・数・色・感情など状況別に意味を紹介
蛇の夢は金運アップや幸運の兆し?大きさ・数・色・感情など状況別に意味を紹介
 【2026年最新】チンチラの飼い方まとめ!種類ごとの価格相場や寿命、なつくコツを伝授
【2026年最新】チンチラの飼い方まとめ!種類ごとの価格相場や寿命、なつくコツを伝授
 フェネックを家で飼うには?必要な費用・防音対策・温度管理まで、後悔しないための飼育マニュアル
フェネックを家で飼うには?必要な費用・防音対策・温度管理まで、後悔しないための飼育マニュアル









