
「ヤドカリの飼育に挑戦してみたい」と考えている方もいるのではないでしょうか。
ヤドカリは比較的丈夫で、飼いやすい生き物です。
しかし、飼育方法をしっかりと把握していないと、ヤドカリを早く死なせてしまうかもしれません。
そこで本記事では、ヤドカリの飼い方を初心者向けにわかりやすく解説します。
値段や寿命、飼育する際の注意点についても取り上げるので、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
- ヤドカリは何類?どんな生き物?
- ヤドカリの特徴・生態
- ペットとして人気が高いヤドカリの種類と値段相場
- ヤドカリの販売場所
- ヤドカリを飼育するなら必要なアイテム
- ヤドカリの水槽の作り方
- ヤドカリは何を食べる?代表的な餌を紹介!
- ヤドカリの飼い方のポイント
- ヤドカリの寿命とかかりやすい病気
- ヤドカリを飼育する際の注意点
- インスタグラムの投稿からかわいいヤドカリを紹介!
- ヤドカリに関するよくある質問
- 初心者でも飼いやすいヤドカリをペットとして迎え入れてみよう!
ヤドカリは何類?どんな生き物?

まずは、ヤドカリの基本情報について見ていきましょう。
ヤドカリはなんの仲間?
ヤドカリは、「十脚甲殻類」に属する生き物です。
十脚甲殻類とは、頭と胸が甲で覆われており、脚が10本ある生き物のこと。
ヤドカリは貝殻を背負っているのでわかりづらいですが、エビやカニの仲間です。
貝殻を脱ぐと、エビと同じような体の形をしています。
ヤドカリは、海底や岩場、干潟などさまざまな場所に生息しており、種類も豊富。
世界には約800種類、日本だけでも200種類以上のヤドカリが存在するといわれています。
ヤドカリの英語・漢字表記
ヤドカリの英語表記は、「hermit crab」です。
日本語訳すると「隠者の蟹」という意味になります。
貝殻で体を隠して生活する姿から、この名前がつけられました。
また、ヤドカリを漢字で表記すると、「宿借」または「寄居虫」となります。
ヤドカリの特徴・生態

飼育するなら把握しておきたいヤドカリの特徴・生態を紹介します。
1.生息地が幅広い
2.脚が10本ある
3.大きさはさまざま
4.臆病な性格である
5.夜行性である
6.雑食である
7.エラ呼吸である
8.腹部が右にねじれている
9.貝殻を住処にして定期的に引越しする
10.天然記念物に指摘されている
以下でそれぞれを詳しく解説していくので、目を通しておきましょう。
1.生息地が幅広い
ヤドカリの生息地は幅広いです。日本を含む、世界中の海に分布しています。
また海だけではなく、河川と海水が接触する汽水域に生息しているヤドカリもいますよ。
主な生活場所は、海岸や岩場、干潟や海底など。
ヤドカリと聞くと暖かい地域に生息しているイメージがあるかもしれませんが、東北地方など寒い地域で暮らしている北方系のヤドカリも存在します。
2.脚が10本ある
脚が10本(5対)あるのがヤドカリの特徴です。
ハサミ脚が2本(1対)と歩脚が8本(4対)あります。
ただ、歩脚のうちの4本(2対)は貝殻の中に隠れているので、外からはなかなか見えません。
貝殻の中に溜まったゴミを掻き出したり、貝殻を支えたりするのに役立っています。
3.大きさはさまざま
ヤドカリの大きさは、種類によってさまざまです。
体長1cm程度の個体もいれば、体長7cmを超える種類もいます。
一般的には、海水生のヤドカリは小型で、陸生のヤドカリは大きい傾向にあります。
4.臆病な性格である
個体差はありますが、ヤドカリは一般的に臆病な性格をしています。
何かに驚くと、貝殻に閉じこもって出てこなくなることもしばしば。
ヤドカリが安心して過ごせるように、静かな環境を用意してあげることが大切です。
必要以上に触るのもヤドカリのストレスになるので、なるべく避けましょう。
5.夜行性である
ヤドカリは夜行性なので、日が沈んで暗くなってから活動を始めます。
昼間は隠れて体を休めていることが多く、明るい光が苦手です。
水槽は直射日光が当たらない場所に設置し、布などを被せて光から守ってあげるようにしましょう。
6.雑食である
ヤドカリは雑食なので、基本的には何でも食べる生き物です。
野生のヤドカリは、しらすやエビなどの小魚、海藻、砂や泥に含まれる有機物などを食べて生活しています。
またヤドカリは、魚の死骸や他の生き物の食べ残しなども食べます。
そのため、「海の掃除屋」と呼ばれる場合もありますよ。
7.エラ呼吸である
ヤドカリといえば砂浜をトコトコと歩くイメージがありますが、実はエラ呼吸の生き物です。
貝殻の中に少量の水を溜めて、その水でエラ呼吸を行います。
したがってヤドカリは、乾燥した環境では生活していけません。
飼育下でもヤドカリがのびのびと呼吸できるように、ヤドカリや床材にこまめに水をかけてあげるようにしてください。
8.腹部が右にねじれている
普段は貝殻に隠れていて見えませんが、ヤドカリの体は、腹部が右にねじれた形をしています。
右巻きの巻貝を住処にする場合が多く、それに合わせて体の形が変化したといわれています。
ヤドカリを飼育すれば、貝殻を脱いだ姿を目にする機会もあるかもしれません。
9.貝殻を住処にして定期的に引越しする
貝殻を住処にしているヤドカリですが、一生同じ貝殻を使い続けるわけではありません。
体が成長するたびに新しい貝殻を探して、定期的に引っ越しをするという不思議な習性があります。
ヤドカリにとって貝殻は、命を守る大切なアイテムです。腹部のデリケートな部分を守り、エラ呼吸に必要な水を蓄えています。
したがって、自分が生き抜いていくためには、自分に合った貝殻を背負っておく必要があるのです。
引っ越しの時期が近づくと、次の貝殻を吟味するかわいらしい姿も見られますよ。
10.天然記念物に指定されている
ヤドカリの中の「オカヤドカリ」という品種は、天然記念物に指定されています。
かつては釣り餌として人気があったオカヤドカリ。しかし、1970年頃に小笠原諸島で個体数の減少が確認されたため、天然記念物に指定されました。
現在では、採取許可業者による捕獲は認められています。ただ、個人が砂浜を訪れた際に、ヤドカリを捕獲して持ち帰る行為は法律違反です。
ヤドカリを飼育したい場合は、ペットショップや海水魚ショップなどで購入しましょう。
ペットとして人気が高いヤドカリの種類と値段相場
ペットとして人気が高いヤドカリの種類を、5つ紹介します。
1.オカヤドカリ
2.ムラサキオカヤドカリ
3.ナキオカヤドカリ
4.ホンヤドカリ
5.ケアシホンヤドカリ
先ほど、世界には約800種類のヤドカリが存在するとお伝えしましたが、ペットとしての飼育に向いているヤドカリはごく一部です。
この章では、その中でも特に人気が高い5種類を取り上げます。
ヤドカリの飼育を考えている方は、お気に入りの子を見つけてみてください。
1.オカヤドカリ

「オカヤドカリ」は、天然記念物に指定されている陸棲のヤドカリです。沖縄の砂浜などでよく見かけます。
飼育水をあまり必要としないので、初心者でも飼育しやすいのが特徴。水の中に入れると溺れて死んでしまうので、間違えて水中で飼育しないように気を付けてください。
体長は約6㎝程度で、体色は褐色。目の付け根が黒く、ハサミ脚の先端が白っぽくなっています。
天然記念物に指定されているので、沖縄の砂浜で捕獲するのは法律違反です。ペットショップや海水魚ショップで購入しましょう。
販売価格は300円〜1,000円程度です。
2.ムラサキオカヤドカリ

オカヤドカリの仲間で、紫色の体色をしているのが「ムラサキヤドカリ」です。オカヤドカリと同様に天然記念物に指定されています。
非常にポピュラーな品種で、砂浜で見かけるヤドカリのほとんどはムラサキヤドカリ。目の付け根が白く、目の先端は黒くて大きいのが特徴です。
体長は6㎝程度で、陸棲。オカヤドカリとは違って発音器を持っているので、ストレスや危険を感じると「ギチギチ」と鳴きます。
販売価格は300円〜1,000円程度です。
3.ナキオカヤドカリ

鳴き声をあげることで知られているオカヤドカリの仲間が「ナキオカヤドカリ」です。
ムラサキヤドカリと同様に発音器を持ち、ストレスや危険を感じると「ギチギチ」と鳴きます。
見た目もムラサキヤドカリと非常によく似ていますが、目の柄で見分けられます。ナキオカヤドカリの目の付け根には白黒の模様が入っているように見えますが、ムラサキヤドカリには模様はありません。
ペットショップではムラサキヤドカリと混同して売られている場合があるので、ナキオカヤドカリを飼育したい場合は、目の柄をチェックしましょう。
オカヤドカリ・ムラサキヤドカリと同様に天然記念物に指定されており、販売価格は300円〜1,000円程度です。
4.ホンヤドカリ

「ホンヤドカリ」は日本近海で最もよく見かける水棲のヤドカリです。
体長は約1㎝程度と小柄。砂浜ではなく岩場のあたりを住処にしています。
体色は深緑色で、脚の先端に白い帯があるのが特徴。左右のハサミ脚は同じ大きさではなく、右側の方が少し大きくなっています。
個体数が多く入手しやすいので、ペットショップなどでの販売価格は数匹で数百円程度。天然記念物に指定されていないので、自然採取も可能です。
ただ、陸棲のヤドカリと比べると飼育難易度は上がります。
5.ケアシホンヤドカリ

ホンヤドカリの仲間ですが、体色が明るい緑色をしているのが「ケアシホンヤドカリ」。脚や甲などが細かい毛で覆われているのも特徴的です。
また、第一触角と第二触角が鮮やかなオレンジ色で、緑の体色との対比が美しいところも人気の秘訣。
販売価格は比較的安く、数百円程度です。
ただし、ケアシホンヤドカリはホンヤドカリよりも食欲が旺盛で、水質の悪化に弱い傾向にあります。
飼育難易度がホンヤドカリよりもさらに上がるので、特徴や飼い方をしっかりと理解したうえで飼育する必要があるでしょう。
ヤドカリの販売場所

「ヤドカリはどこで手に入れれば良いの?」と疑問に思っている方に向けて、入手場所を解説します。
ペットショップ・海水魚ショップ
ヤドカリの最も一般的な入手場所が、ペットショップや海水魚ショップです。
大きめのペットショップや海水魚ショップなら、レアな品種のヤドカリにも出会えるかもしれません。
飼育に必要なアイテムも同時に購入できるので、ヤドカリを飼うのが初めての方には、ペットショップや海水魚ショップがおすすめです。
通販
楽天市場などのインターネット通販でも、ヤドカリを購入できます。
なかなか見かけないレアな個体も販売されていますよ。
ただ、配送中にヤドカリに負担がかかってしまう可能性はあります。
自然採取には要注意
ヤドカリを自然採取する場合は、充分に注意を払いましょう。
天然記念物に指定されているヤドカリを間違えて持ち帰ってしまうと、法律違反になります。
特に、オカヤドカリの仲間には要注意です。飼育したい場合は浜辺で採取するのではなく、店舗や通販で購入するようにしましょう。
ヤドカリを飼育するなら必要なアイテム

ヤドカリを飼育するなら必要なものを、12アイテム紹介します。
・飼育容器(水槽)
・サンゴ砂などの床材
・隠れ家
・複数の貝殻
・水皿
・飼育水または海水
・比重計
・フィルター
・エアレーション
・ヒーター
・温度計
・ガジュマル
「ヤドカリを飼うのが初めてで、何を用意すれば良いかわからない」という方は、まずは上記の12アイテムを用意しておきましょう。
以下で詳しく解説していきます。
飼育容器(水槽)
ヤドカリの住処となる飼育容器を用意しましょう。
プラスチック製の虫かごでも代用できますが、床材として砂を使用するので、強度が高いガラス製の水槽がおすすめです。
水槽が小さいとヤドカリにストレスがかかるので、余裕のある大きさのものを選びましょう。
大きさの目安は以下の通りです。
・1匹飼育→横幅30cm~45cm程度
・複数匹飼育(4匹程度まで)→横幅60cm程度
過密飼育は、脱皮の失敗などを招きます。ヤドカリの健康維持のためにも、のびのびと過ごせる環境を用意してあげてください。
また、ヤドカリの脱走を防ぐために、必ず蓋が付いた飼育容器を選ぶようにしましょう。
サンゴ砂などの床材
足場には、床材として砂を敷き詰めましょう。
特にオカヤドカリの場合は、砂に潜る習性があります。脱皮時に体を守ったり、乾燥を防いだりするためです。
したがって砂は、体長の2倍〜3倍の深さになるように敷き詰めるようにしましょう。
砂の種類は問いませんが、メンテナンスのしやすさや見た目の美しさから、サンゴ砂を選ぶ方が多いです。
隠れ家
オカヤドカリは臆病な性格なので、身を隠せる場所が必要です。
また、ホンヤドカリはオカヤドカリに比べると物怖じしませんが、脱皮時に岩陰に隠れたりします。
隠れる場所がないとヤドカリがストレスを感じてしまうので、必ず隠れ家を設置してあげましょう。
隠れ家は、登ったり降りたりするアスレチックとしても活躍してくれますよ。
オカヤドカリにはトンネルや流木など、ホンヤドカリにはサンゴやライブロックなどがおすすめです。
複数の貝殻
貝殻はヤドカリにとって、命を守る大切なアイテムです。いつでも引っ越しができるように、複数の貝殻を入れておきましょう。
もし気に入った貝殻がないと、ヤドカリが引っ越しできず、成長が止まってしまう可能性があります。最悪の場合は貝殻を脱いでしまい、命を落としてしまう危険性も。
したがって、好みの貝殻が見つかるように、さまざまな種類の貝殻を入れておくのがおすすめです。
複数匹を同じ水槽で飼育する場合は、貝殻の好みが重なってしまう可能性があるので注意しましょう。
水皿
陸棲のヤドカリを飼育する場合に必要なのが、水皿です。海水用と真水用の2つの水皿を用意してください。
オカヤドカリなどの陸棲のヤドカリは、貝殻に水を溜めてエラ呼吸しています。水分補給がうまくできないと、水が不足して窒息してしまうかもしれません。
常に新鮮な水を取り入れられるように、水皿の水は切らさないようにしましょう。
水皿は、ヤドカリが貝殻ごと浸かれるくらい深さがあるものを選んでください。
また、ヤドカリが水皿をひっくり返してしまう可能性があるので、重量があるものがおすすめです。
飼育水または海水
陸棲のヤドカリの場合は飼育水が、水棲のヤドカリの場合は海水が必要です。
飼育水は、カルキ抜きをしたものをスプレーボトルに詰めておくのが良いでしょう。床材やヤドカリに水を吹きかけてあげれば、乾燥を防げます。
海水は、海から水を調達できれば良いですが、海辺に住んでいないと難しいですよね。市販されている「人工海水の素」を使用すれば、簡単に海水を再現できるのでおすすめです。
比重計
水棲のヤドカリを飼育する場合は、比重計が必要です。
比重計とは、液体や固体の密度を測定する器具のこと。人工海水を作る際に使用します。
人工海水の比重の目安は、1.020〜1.024です。
フィルター
水棲のヤドカリを飼育する場合は、必須ではありませんが、フィルターがあると便利です。
餌の食べ残しやフンなどの汚れを取り除いてくれるので、きれいな水を長期間保てます。
水槽の水替えは、労力がいる作業です。フィルターを設置すれば、お世話にかかる手間を削減できますよ。
水槽とフィルターがセットになっている商品もあるので、ぜひ検討してみてください。
エアレーション
エアレーションも必須ではありませんが、水棲のヤドカリを飼育する場合にあると便利です。
エアレーションとは、水に酸素を送り込んでくれる器具のこと。
水棲のヤドカリは水中でも呼吸できますが、水中にある酸素が足りていないと、酸欠になってしまいます。
エアレーションを設置していれば、酸欠が起こる心配がありません。
水棲のヤドカリを飼育する場合は、フィルターと一緒に購入を検討しましょう。
ヒーター
冬場はヒーターを設置して、水槽を温めてあげてください。
飼育適温を維持できていないと、ヤドカリの体にダメージを与えてしまいます。
水中で使用できる投げ込み式のヒーターや、水槽の下に敷くパネルヒーターなど、さまざまな種類があるので、使いやすいものを選びましょう。
温度計
常に飼育適温を維持するために、温度計は必ず購入しておきましょう。
ガジュマル
ヤドカリはガジュマルが大好きなので、水槽に入れてあげると喜びます。
上り下りして遊んだり、上で昼寝したり、葉を食べたりしますよ。
また、ガジュマルの木を設置すれば、水槽の見た目も華やかになります。
ただし、ヤドカリは有機溶剤に弱い生き物です。ガジュマルは、無農薬かどうかを確認してから購入するようにしましょう。
ヤドカリの水槽の作り方

「ヤドカリを飼育するのが初めてで、水槽の作り方がわからない」という方に向けて、簡単に手順を紹介します。
陸棲ヤドカリの場合
陸棲ヤドカリの場合は、水槽を水で満たす必要がないので比較的簡単です。以下の手順に沿って、飼育環境を整えていきましょう。
1.水槽・砂・隠れ家などの小物を洗う
2.洗ったものを天日干しする
3.水槽の底に砂を敷き詰める
4.隠れ家やガジュマルなどの小物を設置する
5.ヤドカリを中に入れる
砂は、ヤドカリが充分に潜れるくらい深めに敷き詰めましょう。
水棲ヤドカリの場合
つづいて、水棲ヤドカリの水槽の作り方を紹介します。以下の手順に沿って行いましょう。
1.水槽・隠れ家などの小物を洗う
2.底に砂を敷き詰めて、小物を設置する
3.人工海水を作って水槽に入れる
4.フィルターやエアレーション、ヒーターなどを設置する
5.ヤドカリを中に入れる
水は、ヤドカリが潜れる程度の深さがあれば大丈夫です。
ヤドカリは何を食べる?代表的な餌を紹介!

ヤドカリは雑食なので、基本的には何でも食べます。栄養が偏らないように、以下のようなものをローテーションして与えるようにしましょう。
・ヤドカリ専用フード
・シラスなどの小魚
・ヤドカリゼリーやザリガニゼリー
・ガジュマルの葉
・果物
・野菜
・穀類
・海藻
・ポップコーン
野菜や果物、海藻などは、味付けされていないものを与えるようにしてください。
ヤドカリが餌を食べないときは、ワンパターンなメニューに飽きてしまっている可能性があります。飽きがこないように、メニューにバリエーションを持たせてあげましょう。
また、以下のような食材はヤドカリの体に良くないので、与えないようにしてください。
・タマネギ
・ネギ
・加工食品
・味付けされているもの
・添加物が多いもの
ヤドカリの健康を守るために、飼い主さんがしっかりと栄養管理を行いましょう。
ヤドカリの飼い方のポイント

ヤドカリの飼い方のポイントを、4つ紹介します。
1.温度管理をしっかりと行う
2.湿度管理をしっかりと行う
3.床材は常に湿らしておく
4.清潔な環境を保つ
ヤドカリを飼うのが初めての方は、まずは上記の4つのポイントをおさえておきましょう。
以下で詳しく解説していきます。
1.温度管理をしっかりと行う
水槽内の温度管理をしっかりと行いましょう。
ヤドカリはもともと暖かい地域に生息する生き物なので、冬の寒さが苦手です。温度が18℃以下になってしまうと、動きが鈍くなり、最悪の場合は死に至る危険性もあります。
ヤドカリの飼育適温は25℃前後です。冬はヒーターを使用したり、暖房がついた部屋に水槽を設置したりして、意識的に温めるようにしてください。
また、暑すぎても体調を崩す原因になります。夏場の直射日光などにも充分に注意しましょう。
2.湿度管理をしっかりと行う
温度と同様に重要なのが湿度です。乾燥しているとエラが乾いてしまい、呼吸できなくなってしまいます。
ヤドカリが過ごしやすい湿度は60%以上です。霧吹きをこまめに使用して水槽内の乾燥を防ぎ、快適に過ごせる環境を作ってあげましょう。
湿度計を設置して、水槽内の湿度管理を行うのがおすすめです。
3.床材は常に湿らしておく
床材の砂は常に湿らせておくようにしましょう。
ヤドカリは、砂の中に潜る習性がある生き物です。長いと数ヶ月程度は潜ったままで、出てこない場合もあります。
そのため、砂の中に潜っているときも湿度を維持できるように、砂を湿らせておく必要があるのです。
ヤドカリが潜ったまま出てこなくても、無理に取り出そうとせず、砂を定期的に湿らせて見守ってあげましょう。
4. 清潔な環境を保つ
こまめに掃除して、水槽内を清潔に保つようにしてください。
不衛生な環境は、ヤドカリの不調や病気を引き起こします。また、フンや食べ残しの放置は悪臭やカビの原因にもなりますよ。
フンや食べ残しを見つけたら、その都度取り出すようにしましょう。
また、月に1回程度は水の交換や砂の洗浄を行ってください。
水の交換は、古い水を3分の1程度捨てて、その分新しい水を注ぎ足します。全ての水を交換してしまうと、急な環境の変化でヤドカリが弱ってしまうので注意してください。
ヤドカリの寿命とかかりやすい病気

ヤドカリの寿命は、種類によって大きく異なります。
一般的には、オカヤドカリの仲間は10年〜30年程度、ホンヤドカリの仲間は3年〜4年程度生きるといわれていますよ。
長生きと健康のためには、日頃からしっかりと飼育環境を整えてあげることが大切です。
水質の悪化や乾燥は、ヤドカリの不調や感染症、脱皮不全などを引き起こします。水槽内をこまめに掃除して、適切な温度と湿度を保つようにしましょう。
ヤドカリを飼育する際の注意点

ヤドカリを飼育する際の注意点を、5つ紹介します。
1.触りすぎるとストレスを感じる
2.室内で殺虫剤は使用しない
3.混浴は慎重に行う
4.直射日光は避ける
5.水を入れすぎない
注意点を把握しないまま飼育してしまうと、ヤドカリに大きなストレスを与えてしまうかもしれません。
しっかりと確認しておきましょう。 以下で詳しく解説していきます。
1.触りすぎるとストレスを感じる
ヤドカリは、犬や猫のように飼い主になつく生き物ではありません。また、臆病な性格の個体も多いので、むやみに触りすぎるとストレスを感じてしまうでしょう。
ストレスは、寿命を縮める原因にもなります。必要以上に触るのは避けて、そっと見守りながら魅力を堪能してください。
2.室内で殺虫剤は使用しない
ヤドカリの水槽がある部屋で、殺虫剤を使用するのは避けてください。
殺虫剤には、「ピレスロイド系」という成分が入っている場合が多いです。「ピレスロイド系」には魚毒性があるので、ヤドカリが突然死んでしまう可能性があります。
ヤドカリの長生きと健康のために、薬剤散布には充分な注意を払いましょう。
3.混浴は慎重に行う
「他の生き物とヤドカリの混浴を楽しみたい」という方も多いでしょう。しかし、生き物によってはヤドカリを攻撃してしまう可能性があるので、慎重に行う必要があります。
たとえば、ヒトデやカニは肉食傾向が強い種類が多いです。
また同じヤドカリでも、餌が足りていなかったり、大きさが違いすぎたりすると、喧嘩や共食いが起こってしまうかもしれません。
混浴は、互いの性質をよく検討してから行うようにしましょう。
4.直射日光は避ける
ヤドカリの水槽を、直射日光が当たる場所に設置するのは避けましょう。
ヤドカリは夜行性なので、昼間の明るい光が苦手です。直射日光が当たるとストレスを感じて、体が弱る原因になるかもしれません。
また直射日光が当たると、水槽内の温度が上がりやすくなります。温度が30℃を超えてしまうと、ヤドカリが思うように動けなくなりますよ。
直射日光が当たらない、温度を維持しやすい場所に水槽を設置するようにしましょう。
5.水を入れすぎない
水棲のヤドカリを飼育する場合、水槽に水を入れすぎないように注意してください。
水棲ヤドカリは水辺の生き物ですが、水の量が多すぎると溺れてしまう危険性があります。
水深は、ヤドカリが潜れる程度の深さがあれば充分です。水を交換するときは、入れすぎないように意識するようにしましょう。
インスタグラムの投稿からかわいいヤドカリを紹介!
インスタグラムの投稿からかわいいヤドカリを紹介します。
ヤドカリを飼ってみたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
アサリに紛れるヤドカリさんたち
アサリと一緒に暮らしているヤドカリさんたちを、yuka811118117さんの投稿から紹介します。
仲良くできているかな〜?
色んな柄の貝殻があって華やかで、見ていると何だか癒されてきますね…!
自然採集したヤドカリさん
あどけない表情をしているように見えるヤドカリさんを、drop_of_the_sea4さんの投稿から紹介します。
神奈川県の某所で自然採集したそう。貝殻の形が可愛くて、センスが良いですね〜!
これからどんな貝殻に引っ越ししていくのか楽しみです。
オカヤドカリのえだ豆と大豆さん
okydchan.s2さんの投稿から、オカヤドカリのえだ豆さんと大豆さんの紹介です。
えだ豆・大豆という名前がしっくりくる、かわいらしい見た目をしていますね〜!
この写真は、連れてきたばかりの頃のものだそう。okydchan.s2さんのアカウントでは、その後の成長記録も見れますよ。
気になる方はチェックしてみてください。
ヤドカリに関するよくある質問

最後に、ヤドカリに関するよくある質問3つに回答します。
1.ヤドカリのオスとメスの見分け方は?
ヤドカリのオスとメスは、生殖孔の位置で見分けるのが一般的です。
ヤドカリのオスの場合、生殖孔は最も後ろにある脚のつけ根に開きます。
一方でメスは、前から3番目にある脚のつけ根に生殖孔が開きます。
よく目を凝らさないとわからない違いですが、気になる方は確かめてみてください。
2.ヤドカリとイソギンチャクは関係が深いって本当?
海に行くと、ヤドカリの貝殻に引っ付いているイソギンチャクを見かける場合が多いでしょう。これは、ヤドカリとイソギンチャクが相互共生できる生き物だからです。
ヤドカリは、イソギンチャクをあえて自分の貝殻につけることで、天敵から身を守ります。
一方でイソギンチャクは、ヤドカリの貝殻に引っ付くことによって、自分だけでは移動できない場所にまで移動できるようになります。
結果として、より多くの餌にありつけるようになるのです。
上記のように、ヤドカリとイソギンチャクは互いに助け合って生活しています。
3.ヤドカリとタラバガニが似ているって本当?
カニの王様として有名なタラバガニ。しかし実は、生物分類学上ではカニの仲間ではなくヤドカリの仲間です。
ズワイガニなどのカニは、「短尾類」に分類されます。一方でタラバガニは、ヤドカリと同じ「異尾類」に分類されます。
両者の違いは脚の数です。短尾類には10本(5対)の脚がありますが、異尾類は5対目の脚が退化しており、甲羅(貝殻)の中に隠れています。
したがってタラバガニは、味はカニそのものですが、外見はヤドカリに似ている生き物だといえるでしょう。
初心者でも飼いやすいヤドカリをペットとして迎え入れてみよう!

貝殻を背負ってトコトコ歩く姿がかわいいと人気の「ヤドカリ」。お世話の内容は比較的簡単なので、ペットを飼うのが初めての方にもおすすめできる生き物です。
広い飼育スペースを必要とせず、大きな鳴き声をあげることもないので、マンションやアパートに住んでいる方でも飼育に挑戦できるでしょう。
陸棲のヤドカリなら10年〜30年程度は生きるので、長い期間を共に過ごせるのも魅力的ですね。
ヤドカリに興味がある方は、本記事の内容を参考にしつつ、飼育を検討してみてください。
アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ
部屋を借りる!賃貸版はこちら
住宅を買う!購入版はこちら


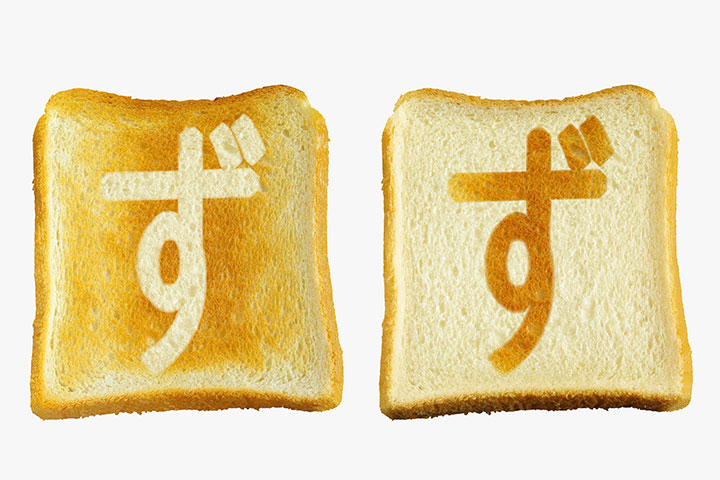 ずから始まる言葉は?絵しりとり・クロスワードで使える134選
ずから始まる言葉は?絵しりとり・クロスワードで使える134選
 蛇の夢は金運アップや幸運の兆し?大きさ・数・色・感情など状況別に意味を紹介
蛇の夢は金運アップや幸運の兆し?大きさ・数・色・感情など状況別に意味を紹介
 【2026年最新】チンチラの飼い方まとめ!種類ごとの価格相場や寿命、なつくコツを伝授
【2026年最新】チンチラの飼い方まとめ!種類ごとの価格相場や寿命、なつくコツを伝授
 フェネックを家で飼うには?必要な費用・防音対策・温度管理まで、後悔しないための飼育マニュアル
フェネックを家で飼うには?必要な費用・防音対策・温度管理まで、後悔しないための飼育マニュアル








