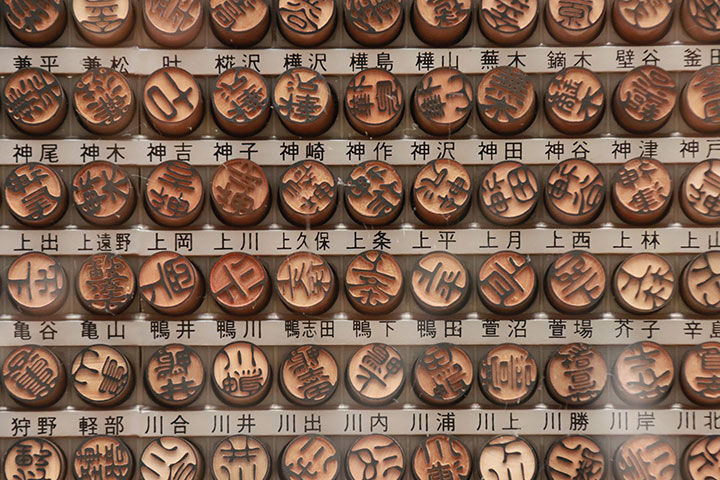そこで本記事では、カブトムシの飼い方を初心者向けにわかりやすく解説します。
必要なアイテムや飼育の注意点についても取り上げるので、本記事を読めば、カブトムシを迎え入れる準備が整うはず。
カブトムシに興味をお持ちの方は、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
- カブトムシってどんな生き物?
- 飼い方の前に知っておきたい!カブトムシの主な特徴4つ
- ペットとしての人気が高いカブトムシの種類と費用相場
- カブトムシの飼育に必要なもの
- カブトムシの餌
- カブトムシの幼虫から成虫になるまでの育て方
- カブトムシの成虫の飼い方のポイント
- カブトムシの寿命と病気
- カブトムシを長生きさせるコツ
- カブトムシの飼い方の注意点
- インスタグラムの投稿から魅力的なカブトムシを紹介!
- カブトムシの飼い方に関するよくある質問
- カブトムシの飼い方をしっかりと把握して家族に迎え入れてみよう!
カブトムシってどんな生き物?

カブトムシとは、昆虫綱>甲虫目>コガネムシ科に分類される生き物の総称です。
日本を含む東南アジアに広く分布しています。
「昆虫の王様」といわれており、クワガタと並んでペットとしての人気が高いのが特徴。
比較的育てやすいので、昆虫を初めて飼育する方にもオススメです。
日本では夏になると、山や森など自然が多い場所で見かける機会が多くなります。
飼育したいなら自然から採取する方法もありますが、昆虫ショップに足を運べば、レアな品種に出会えるかもしれません。
飼い方の前に知っておきたい!カブトムシの主な特徴4つ

飼育するなら知っておきたいカブトムシの特徴を、4つ紹介します。
カブトムシを飼いたいと思っている方は、把握しておきましょう。
1.広葉樹の近くに生息している
カブトムシは、落葉広葉樹の近くに生息している場合が多いです。
具体的には、以下のような木が当てはまります。
・コナラ
・クヌギ
・ミズナラ
・クリ
夏の雑木林に行けば、野生のカブトムシと出会える確率は高いでしょう。
成虫は樹液を求めて幹に集まり、幼虫は腐葉土や堆肥の中で過ごします。
2.夜行性である
カブトムシは、一般的には夜行性であるといわれています。
餌となる樹液が、夜や朝方に分泌される場合が多いからです。
また、カブトムシは体が黒いので、昼間は太陽の光を吸収しやすく、体力を消耗してしまいます。気温が高い時期でも体力を温存できるように、日が沈んでから活動を始めるのです。
ただ近年、昼間に活動するカブトムシがいるという研究結果も報告されています。
基本的には夜行性ですが、餌となる樹木の状態や気温などによって、活動パターンは変わると考えておきましょう。
3.活動時期は6月~8月
カブトムシが成虫になって活動する時期は、6月〜8月です。
しかし中には、9月中頃まで生きる個体も存在します。
雨が降っているときは活動しないので、カブトムシを見つけたいなら雨上がりがおすすめです。
夏前までは幼虫の状態で、腐葉土などを食べて土の中で生活しています。
4.オスには角がある
カブトムシの最大の特徴といえば、大きくて立派な「角(つの)」。
角があるのは主にオスで、メスにはない場合が多いです。
角はカブトムシにとって、自分の力を表す象徴です。
大きな角を持つカブトムシの方が、メスから人気があるといわれていますよ。
角は主に、オス同士で喧嘩するときに使われます。
相手の体の下に角を入れてすくい上げ、相手を投げ飛ばす姿は、まるでプロレスを見ているよう。
自分の体重の10倍以上の重さまで持ち上げられるといわれています。
ペットとしての人気が高いカブトムシの種類と費用相場
ペットとして人気が高いカブトムシの種類と値段相場を、5つ紹介します。
1.ヤマトカブトムシ
2.ヘラクレスオオカブト
3.アトラスオオカブト
4.ネプチューンオオカブト
5.コーカサスオオカブト
以下でそれぞれを詳しく解説していくので、お気に入りのカブトムシを見つけてみてください。
1.ヤマトカブトムシ

日本で最もポピュラーな品種は「ヤマトカブトムシ」です。
山や森林の中で見かけたことがある方は多いでしょう。
体長は、オスが40mm〜80mm程度、メスが30mm〜60mm程度と比較的小柄。
初めて昆虫を飼育する方でも挑戦しやすいカブトムシです。
日本の気候に適しているので、特別な設備を用意しなくても飼育できます。
ペットショップやホームセンター、昆虫ショップなどで販売されており、値段は500円〜600円です。
2.ヘラクレスオオカブト

世界最大のカブトムシとして知られているのが「ヘラクレスオオカブト」です。
体長はオスが60mm〜180mm程度、メスは50mm〜90mm程度。
オスは非常に長い角を持っており、メスにも短い角があります。
中南米の標高が高い地域に生息しているため、野生のヘラクレスオオカブトは日本には存在しません。
圧倒的な存在感で人気が高い品種なので、販売価格も比較的高額。
ペットショップや昆虫ショップなどでは、成虫が5万円〜10万円程度で販売されています。
幼虫の場合は安価に手に入りますが、初心者には飼育が難しいので、成虫を購入する方法がおすすめです。
3.アトラスオオカブト

外国産のカブトムシの中で、値段が比較的安くて購入しやすいのが「アトラスオオカブト」です。
ペットショップや昆虫ショップでは、1,000円〜5,000円程度で販売されています。
アトラスオオカブトは、マレー半島やインドシナ半島などの東南アジアに生息しているカブトムシ。
気性が荒い傾向にあるので、喧嘩を防ぐためにも、単独飼育がおすすめです。
頭角と胸角で合計3本の角を持つところも、アトラスオオカブトの特徴だといえるでしょう。
4.ネプチューンオオカブト

大きな角を持ち、迫力のある見た目で人気を集めているのが「ネプチューンオオカブト」です。
角は体と同じくらいの長さで、胸角の下にオレンジ色の毛が生えています。
見た目に反して大人しい性格なので、初心者にもおすすめできるカブトムシです。
野生のネプチューンオオカブトは、コロンビアやペルーなど、アンデス山脈周辺の熱帯雨林に生息しています。
夏場の高温や冬場の低温は苦手なので、しっかりと温度管理をしてあげる必要があるでしょう。
5.コーカサスオオカブト

世界最強のカブトムシといわれている「コーカサスオオカブト」。
3本の迫力のある角を持ち、闘争心も強いカブトムシです。
オスは体長100mmを超える個体も多く、昆虫愛好家から人気を集めています。
生息地は、スマトラ島やジャワ島などの標高が高い地域。
気性が荒いので、1ケースに1頭で飼育するのがおすすめです。
値段は大きさにもよりますが、6,000円~15,000円程度で販売されています。
カブトムシの飼育に必要なもの

カブトムシの飼育に必要なものを、9アイテム紹介します。
・飼育ケース(虫かご)
・昆虫マット(床材)
・隠れ家
・餌入れ・水入れ
・朽ち木・樹皮
・登り木
・保温・保湿用品
・霧吹き
・ピンセット
他にも必要なものは色々と出てきますが、まずはこの9アイテムを揃えておくとよいでしょう。
以下でそれぞれを詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてください。
飼育ケース(虫かご)
カブトムシの家となる飼育ケースを用意しましょう。
カブトムシは品種によって体の大きさが違うので、個体に合わせて余裕のある虫かごを用意してあげてください。
1匹飼育の場合は横幅15cm〜20cm、2匹〜3匹飼育の場合は横幅30cm程度が目安です。
昆虫用プラスチックケースを購入する方が多いですが、水槽でも代用できます。
また、カブトムシは力が強く飛べる昆虫なので、脱走対策もしっかりと行いましょう。
ストッパーつきの蓋がついている飼育ケースがおすすめです。
昆虫マット(床材)
昆虫マット(床材)は、カブトムシの飼育には欠かせないアイテムです。
カブトムシが潜って隠れる場所になったり、幼虫の餌になったりもします。
また、床材に水分と栄養を与えておけば、カブトムシを乾燥から守れますよ。
市販されている昆虫マットか、昆虫用の腐葉土を用意しましょう。
園芸用の腐葉土には、農薬が含まれている可能性があるので避けてください。
隠れ家
必須ではありませんが、カブトムシが安心して身を隠せる隠れ家があった方が良いでしょう。
自然に近い環境を再現することで、カブトムシがリラックスして過ごせます。
適度な温度を保ちやすい木片や、コルクバークがおすすめです。
カブトムシが身を隠す場所を選べるように、いくつか用意しておくのもおすすめです。
餌台・水入れ
快適に食事や水分補給ができるように、餌台や水入れを用意しましょう。
餌台は、昆虫ゼリーを固定できるように、中央部分が丸くくり抜かれているタイプのものがおすすめです。
餌台は、隠れ家や登り木の役割も果たしてくれますよ。
朽ち木・樹皮
飼育ケースの中には、床材にプラスして、朽ち木や樹皮を敷き詰めておくのがおすすめです。
幼虫にとっては餌に、成虫にとっては布団代わりになります。
朽ち木や樹皮は、なるべく市販のものを選ぶようにしてください。
森林や公園などで拾ってきた朽ち木・樹皮には、害虫がいる可能性があるので危険です。
登り木
なるべく野生に近い環境を再現できるように、登り木を設置しましょう。
カブトムシが自由に登ったり隠れたりできるので、快適に過ごせるようになりますよ。
また、カブトムシがひっくり返ってしまった際にも、登り木があれば、自力でつかまって起き上がれます。
保温・保湿用品
カブトムシの健康と長生きのためには、温度と湿度を適切に保つことが大切です。
気温や環境を整えるために、以下のような保温・保湿用品を揃えておくと、急な気候の変化にも対応できます。
・ヒーター
・加湿器
・保水ジェル
・温度計
・湿度計
霧吹き
乾燥を防ぐために、霧吹きを用意しておくと便利です。
昆虫マットや床材が乾かないように、定期的に霧吹きを吹きかけましょう。
ただし、水浸しの状態や結露はカブトムシの体に良くありません。
適度な湿度を維持できるように加減してください。
ピンセット
必須ではありませんが、ピンセットがあると便利です。
餌を摘んだり、飼育ケースの中を掃除したりするときに使います。
また、幼虫から飼育する場合は、シリコン製の柔らかいピンセットを用意しておくのがおすすめです。
カブトムシの餌

カブトムシには、昆虫ゼリーを与えるのが一般的です。
栄養バランスに優れているので、カブトムシの健康と長生きにつながります。
日持ちするので管理しやすいという点もメリットですね。
りんごやバナナなどの果物も好んで食べますが、腐りやすいので要注意。
昆虫ゼリーを中心に与えて、たまに果物で変化をつけるくらいの割合がおすすめです。
また、乳酸飲料や飲料ヨーグルトなども代用食になります。タンパク質や糖分などに必要な栄養素を効率的に摂取できますよ。
カブトムシの幼虫から成虫になるまでの育て方

カブトムシは、成虫の期間よりも幼虫の期間が長い昆虫です。
幼虫の期間は約8ヶ月。それに対して、成虫の期間は約3ヶ月です。
「カブトムシを幼虫から育ててみたい」という方に向けて、幼虫から成虫までの育て方を解説します。
カブトムシの幼虫の育て方
卵から孵化したカブトムシの幼虫は、「一齢幼虫」と呼ばれます。
それから脱皮を繰り返し、「二齢幼虫」「三齢幼虫」へと成長していきます。
健康的な発育のためには、しっかりと栄養を摂ることが大切です。
カブトムシの幼虫は、土の中で栄養を摂りながら育ちます。
幼虫が充分に栄養を摂取できるように、腐葉土や昆虫マットを10cm以上は敷き詰めるようにしましょう。
また幼虫の飼育は、温度管理や湿度管理も大切です。
温度20℃〜25℃、湿度60%〜70%を保てるように、霧吹きやヒーターを使用して調整してください。
蛹化(ようか)・羽化(うか)
土の中で充分に栄養を摂れていれば、孵化してから7ヶ月〜8ヶ月頃に蛹化(ようか)が始まります。
幼虫の活動が減り、腐葉土(床材)の中に潜って動かなくなってくると、蛹化が始まるサインです。
このときに幼虫は、腐葉土の中に「蛹室」という空間を作ります。
蛹室は、幼虫が安全に蛹化するために必要な空間です。
したがってこの時期には、腐葉土や幼虫にはなるべく触れないようにして、静かに見守るようにしましょう。
そして、蛹になってから20日〜30日ほどで、羽化が始まります。
羽化が終わると、成虫になったカブトムシが蛹室から出てきます。
カブトムシの成虫の飼い方のポイント

カブトムシの飼い方のポイントを、4つ紹介します。
1.温度管理をしっかりと行う
2.湿度管理をしっかりと行う
3.餌が切れていたら補充する
4.昆虫マットはこまめに交換する
初めてカブトムシを飼育する方は、まずは上記の4つをしっかりと意識するようにしましょう。
以下で各ポイントを詳しく解説していきます。
1.温度管理をしっかりと行う
飼育ケース内の温度管理をしっかりと行うようにしましょう。
カブトムシは夏に活動する昆虫ですが、暑さに強いというわけではありません。
直射日光を避け、ケース内の温度を30℃以下に保てるように管理しましょう。
飼育適温を維持するためにも、温度計は必ず設置するようにしてください。
また冬場は、18℃以上の場所で飼育するのが理想です。
寒さが厳しくなってきたら、ヒーターなどを使用して温めてあげるようにしましょう。
なお、飼育適温はカブトムシの種類によって異なるので、迎え入れる前に確認しておくようにしてください。
2.湿度管理をしっかりと行う
温度管理と同様に、湿度管理もしっかりと行うようにしてください。
カブトムシは乾燥した環境が苦手な生き物です。
霧吹きや保水ジェルなどのアイテムを使用して、昆虫マット(床材)の表面を常に湿らせておくようにしましょう。
理想的な湿度は、60%〜70%程度です。
3.餌は定期的に交換する
こまめに餌の残量を確認して、餌を切らさないようにしてください。
食べる餌の量は個体によって異なります。カブトムシによっては、なかなか餌がなくならない場合もあるでしょう。
しかし、餌がまだ残っていても、3日〜4日に1回は新しいものに交換するようにしてください。
暑い時期は餌が傷みやすいからです。
昆虫ゼリーではなく果物を与える場合は、さらに痛むスピードも早くなります。
変色などが見られたら、すぐに飼育ケースから取り除くようにしましょう。
4.昆虫マットはこまめに交換する
昆虫マットや腐葉土は、汚れているのを見つけたらすぐに交換するようにしましょう。
不衛生な環境は、カブトムシの体調不良や感染症につながります。
また、汚れたまま放置していると、悪臭の原因にもなりますよ。
定期的にマットの状態を確認して、常に清潔な環境を保つようにしましょう。
カブトムシの寿命と病気

カブトムシの平均寿命は個体や飼育環境にもよりますが、1年程度です。
そのうちの7ヶ月〜8ヶ月程度は幼虫の姿で過ごし、成虫になってからは3ヶ月〜4ヶ月程度で生涯を終えます。
しかし中には、冬になっても生き続けるカブトムシも存在しますよ。
カブトムシの健康と長生きのためにも、以下のような病気に注意するようにしましょう。
1.体内寄生虫 症
2.菌感染症
3.ダニの寄生
4.栄養不足
以下でそれぞれを詳しく解説していくので、目を通しておいてください。
1.体内寄生虫症
カブトムシの体内に寄生虫が棲みつくことによって起こる病気が、「体内寄生虫症」です。
食欲不振・体重減少・活動量の低下などの症状が出ます。
寄生虫は、餌や床材などを通して体内に侵入する場合が多いです。
餌や床材は信頼できる店舗で購入し、事前に寄生虫の有無を確認するようにしてください。
森林や公園の腐葉土には寄生虫がいる可能性が高いので、床材として使用するのはおすすめできません。
また、不衛生な環境も寄生虫の発生につながります。こまめに飼育ケース内を掃除して、清潔を保つように心がけましょう。、
2.菌感染症
カブトムシは、菌感染症にかかりやすい昆虫でもあります。
菌感染症にかかると、動きが鈍くなったり、体の一部が黒ずんだり、異臭がしたりします。
菌感染症は、不衛生な環境が原因で起こる場合がほとんど。
昆虫マットが汚れていればこまめに交換して、清潔な環境を心がけるようにしましょう。
また菌感染症は、体にできた傷が原因で起こる場合もあります。
傷を見つけたら、速やかに消毒してください。
3.ダニの寄生
犬や猫と同じように、カブトムシにもダニが寄生します。
ダニが寄生すると、体を痒がったり、活動量が低下したりします。
ダニの発生も不衛生な環境が原因で起こる場合が多いので、飼育ケース内をこまめに掃除するようにしてください。
専用のダニ駆除剤や、ダニの発生を防ぐ昆虫マットなども販売されているので、購入を検討してみると良いでしょう。
4.栄養不足
栄養が不足していると、体力の低下や成長不良などの症状が出ます。
必要な栄養素を過不足なく摂取できるように、昆虫ゼリーを与えるようにしましょう。
適度にりんごやバナナなども組み合わせて、栄養のバランスをとってください。
また、水分不足にならないように、適切な湿度を保つようにしましょう。
カブトムシを長生きさせるコツ

カブトムシを長生きさせるコツは、今までの章でも解説してきましたが、主に以下の5つです。
・温度を適切に保つ
・湿度を適切に保つ
・栄養管理を徹底する
・飼育ケース内を定期的に清掃する
・病気を予防する
カブトムシの寿命は成虫になってから2ヶ月程度だといわれていますが、上記の5つを心がけていれば、冬になるまで長生きしてくれる個体も存在します。
少しでも長い時間を共に過ごせるように、上記のポイントを意識するようにしましょう。
カブトムシの飼い方の注意点

カブトムシの飼い方の注意点を、6つ紹介します。
注意点を把握しないまま飼育してしまうと、最悪の場合はカブトムシの死に至る可能性もあるので、しっかりと確認しておきましょう。
1.幼虫は素手で触らない
幼虫の間は、カブトムシを素手で触るのはやめましょう。
手についている雑菌が原因で、幼虫が命を落としてしまうかもしれません。
手袋をつけた状態で触ったり、スプーンですくったり、柔らかいピンセットでつまんだりするようにしてください。
2.脱走対策をしっかりと行う
脱走対策をしっかりと行うようにしてください。
カブトムシは飛べる虫なので、蓋がない飼育ケースだと簡単に脱走してしまいます。
また、蓋が付いていたとしても何かの拍子に開いてしまう可能性があるので、蓋にストッパーがついているものがおすすめです。
カブトムシの命を守るために、しっかりと対策しましょう。
3.屋外で飼育しない
カブトムシを屋外で飼育するのは避けましょう。
外に飼育ケースを置くと、ダニ・コバエ・アリなどが寄ってくる可能性があります。
また屋外だと、温度や湿度の管理も難しいです。
カブトムシの健康維持のために、室内に飼育ケースを置いて管理するようにしてください。
4.直射日光に注意する
飼育ケースは、直射日光が当たらない場所に設置するようにしましょう。
直射日光が当たると、飼育ケース内の温度やカブトムシの体温が上がりやすくなってしまいます。
飼育適温を維持できていない状態が続くと、カブトムシが弱り、寿命が短くなってしまうかもしれません。
直射日光が当たらない、急激な温度変化を防げる場所に飼育ケースを置くようにしましょう。
5.静かな環境を用意する
カブトムシはストレスに弱い生き物です。
昼間でもゆっくり休めるように、なるべく静かな環境を用意してあげるようにしましょう。
窓際は外の物音が聞こえやすく、直射日光も当たるので、あまりおすすめできません。
音や振動が少ない、静かな部屋に飼育ケースを置くようにしてください。
6.複数匹を同じ虫かごで飼育しない
「絶対にできない」というわけではありませんが、複数匹を同じ虫かごで飼育するのはおすすめできません。
中には気性が荒いカブトムシもいるので、喧嘩が起こる恐れがあるからです。
喧嘩が原因で怪我をしてしまうと、体も弱ってしまいます。
複数匹飼育したい場合は、カブトムシの数の分だけ飼育ケースを用意してあげるのがおすすめです。
インスタグラムの投稿から魅力的なカブトムシを紹介!
インスタグラムの投稿から、wildbeetle.shopさんの魅力的なカブトムシを紹介します。
なんとこの写真のカブトムシさん、12月に入っても頑張って生きてくれていたようです。
カブトムシの寿命は成虫になってから3ヶ月〜4ヶ月程度といわれているので、このカブトムシさんは特に長生き。
家にお迎えしたら、1日でも長く生きてほしいと思いますよね。
飼育環境をしっかりと整えて大切に育てれば、このカブトムシさんのように、冬を迎えてくれるかもしれません。
カブトムシの飼い方に関するよくある質問
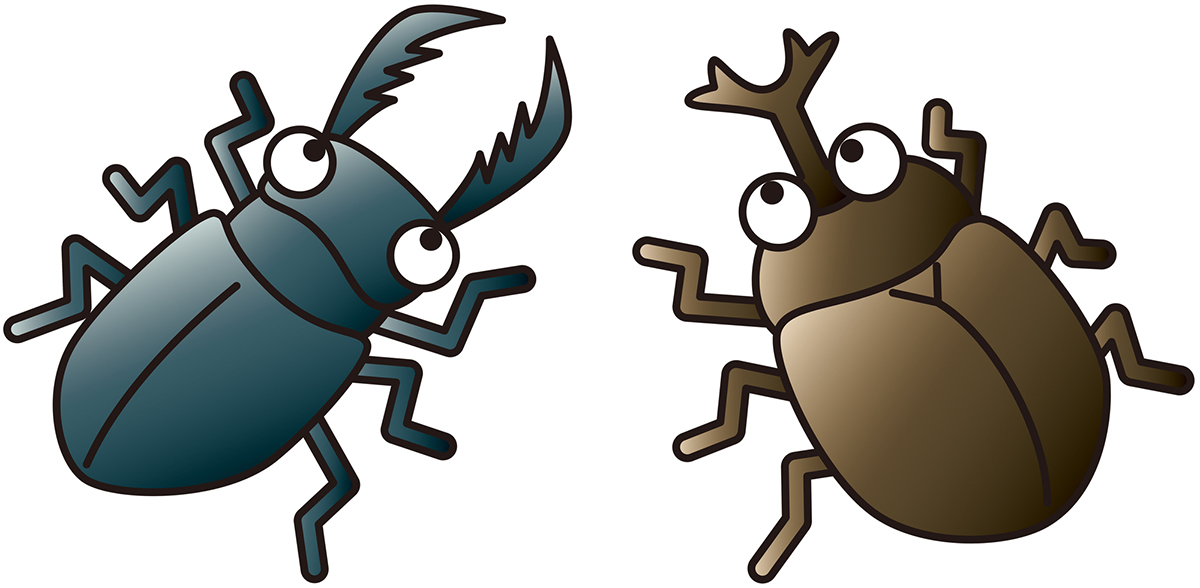
最後に、カブトムシに関するよくある質問5つに回答します。
カブトムシの入手方法は?
カブトムシの主な入手方法は以下のとおりです。
・ペットショップ
・昆虫ショップ
・ホームセンター
・インターネット通販
珍しい品種のカブトムシを探している場合は、昆虫ショップに足を運ぶのがおすすめです。
カブトムシの繁殖は可能?
カブトムシの繁殖は可能です。
産卵のピークは、7月〜8月頃。オスとメスを同じ飼育ケースに入れれば、1週間ほどで産卵が始まります。
産卵は腐葉土や昆虫マットの中で行われますが、すぐに卵を探さないようにしてください。
卵が傷つくと、無事に孵化できません。
8月〜9月頃になると卵が孵化して、幼虫期間が始まります。
ただし、カブトムシは1度に20個〜50個の卵を産みます。全ての卵の面倒を見きれない場合は、繁殖させるのはやめましょう。
カブトムシに与えてはいけないものは?
カブトムシには、スイカ・メロン・きゅうりなどの水分量が多い果物・野菜は不向きです。
下痢を起こしたり、尿の量が増えたりする可能性があります。そうなると飼育ケース内を清潔に保つことが難しくなるので、感染症の原因にもなります。
また、樹液と似ていますが、はちみつにも注意が必要です。糖分が高すぎるのでカブトムシの体には適していません。
クワガタとカブトムシの違いは?
似ているように思えるクワガタとカブトムシですが、実はクワガタに生えているのは角ではありません。
ハサミのような一対の大あごを持っています。
角も大あごも、餌を奪い合う際に武器として使用する点は同じです。
また、カブトムシは「コガネムシ科」に属しますが、クワガタは「クワガタムシ科」に属しているので、そもそも分類が異なります。
カブトムシは国産と外国産のどちらがおすすめ?
初心者におすすめなのは、国産のカブトムシです。日本の気候に適しているため、基本的には常温で飼育できます。
外国産のカブトムシは、国産のカブトムシよりも細かい温度管理が必要になります。
特に冬場の低温には注意が必要です。
迎えたいカブトムシの特性を理解して、快適な飼育環境を整えてあげましょう。
カブトムシの飼い方をしっかりと把握して家族に迎え入れてみよう!

初心者でも比較的簡単に飼育に挑戦できる「カブトムシ」。
広い飼育スペースを必要としないので、マンションやアパートに住んでいる方にもおすすめできる昆虫です。
幼虫の頃に迎え入れれば、成長とともに変化していく姿も楽しめますよ。
カブトムシに興味をお持ちの方は、本記事の内容を参考にしつつ、迎え入れる準備を進めてみてはいかがでしょうか。
アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ
部屋を借りる!賃貸版はこちら
住宅を買う!購入版はこちら


 風水で玄関の鏡はNG?位置、大きさ、形のおすすめと運勢上昇のポイント
風水で玄関の鏡はNG?位置、大きさ、形のおすすめと運勢上昇のポイント
 略語早わかり62選!ビジネスシーン・若者間で使われる必須略語一覧
略語早わかり62選!ビジネスシーン・若者間で使われる必須略語一覧
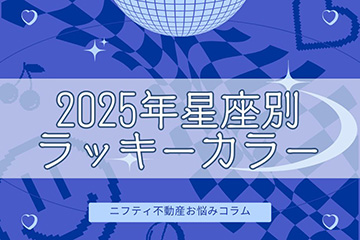 【2025年版】今年のラッキーカラーまとめ|星座別に運気が上がる色を紹介
【2025年版】今年のラッキーカラーまとめ|星座別に運気が上がる色を紹介
 【決定版】家相の基本と間取り図の正しい見方!鬼門・NG配置の対策まで徹底解説
【決定版】家相の基本と間取り図の正しい見方!鬼門・NG配置の対策まで徹底解説