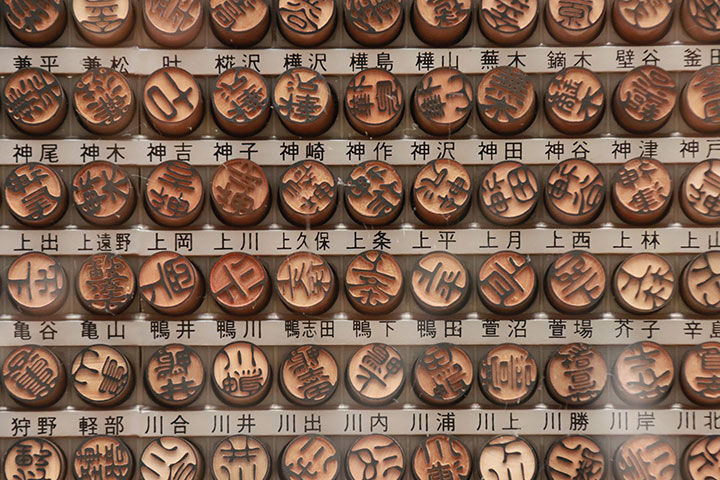日本に住んでいると、「氏神様」や「氏神神社」という言葉をよく耳にしますよね。
しかし、氏神様とは具体的にはどんな神様のことを指すのか、しっかりと理解している方は少ないのではないでしょうか。
そこで本記事では、氏神様にまつわるさまざまな事柄について詳しく解説します。
氏神神社を調べる方法や正しい参り方についても取り上げるので、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
- 氏神様とは?現代における氏神と氏子の意味合い
- 氏神様の本来の意味合い
- 氏神様と産土神様の違い
- 氏神神社と崇敬神社の違い
- 地元の氏神様を簡単に調べる方法5つ
- 氏神様の正しい参り方のポイント3つ
- 氏神様に関するよくある質問
- 氏神様とは地域を守る大切な存在!引っ越ししたら挨拶に行こう
氏神様とは?現代における氏神と氏子の意味合い
「氏神様」とは、地域を守ってくださっている神様のことを指します。
したがって「氏神神社」とは、自分が居住している区域を守ってくださっている「氏神様」を祀っている神社のことです。
そして、その氏神様や氏神神社を信仰している人々のことを「氏子(うじこ)」と呼びます。
「氏神神社の氏子になるためにはどうすれば良いの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、明確な条件はない場合が多いです。
「その地域に住み、神社のお祭りに参加すれば氏子になれる」と考える地域もあれば、「子どもがお宮参りをすれば、氏神様に氏子として認めてもらえる」という考え方が根付いている地域もありますよ。
その地域に昔から住んでいる人に尋ねるなどして、地域の慣習に従いましょう。
氏神様の本来の意味合い

「地域を守ってくださる神様」として親しまれている氏神様ですが、もともとは異なる意味合いを持っていました。
本来は、氏神様とは「血縁的な関係がある一族が祀っている神様」のことを指します。祀っている神様というのは、一族のご先祖様や守護神などのことです。
古代の日本では、一族が同じ土地に住み、その土地の範囲内で子孫を残していくのが一般的でした。
つまり、現代よりも土地と一族の関わりが深かったため、「一族が祀っている神様=その土地を守ってくださる神様」と考えられていたのです。
しかし、時代が流れるにつれて核家族化が進み、一族が同じ土地に住む慣習も薄れていきました。
それに伴って氏神様が持つ意味合いも変化し、「地域を守ってくれる神様」だと捉えられるようになったということです。
氏神様と産土神様の違い

産土(うぶすな)とは、自分が生まれた土地(出生地)のことです。したがって産土神様とは、自分が生まれた土地を守護している神様のことを指します。
前章で、「氏神様とは、一族が信仰している神様のことを指していた」とお話しました。
つまり古代の日本においては、血縁的な繋がりによる信仰の対象が氏神様で、地縁的な繋がりにおける信仰の対象が産土神様だったということです。
しかし、時代が流れるにつれて氏神様の意味合いが変化したので、産土神様は氏神様と混同されるようになりました。
現代では、2つの言葉は同じ意味で使われる場合が多いです。
氏神神社と崇敬神社の違い

先述したように、氏神神社にはもともとは血縁的な意味合いがありましたが、現代では地縁的な意味合いが強くなっています。
一方で崇敬神社とは、血縁的・地縁的な繋がり以外で、個人的に信仰したいと考える神社のことです。
たとえば東京に住んでいる人が、三重県にある伊勢神宮を氏神神社にすることはできません。しかし、伊勢神宮を崇敬神社として信仰するのは問題ないということです。
地元の氏神様を簡単に調べる方法5つ

「今住んでいる地域の氏神様がどこの神社に祀られているか知りたい」と考えている方に向けて、氏神様を調べる方法を5つ紹介します。
1.Googleマップで近くの神社を調べる
2.インターネットで検索する
3.神社庁に問い合わせる
4.長く住んでいる人に聞く
5.近所の神社で聞いてみる
氏神様をお参りしたい方は、ぜひ参考にしてください。以下で詳しく解説していきます。
1.Googleマップで近くの神社を調べる
Googleマップなどの地図アプリを使って、自宅の近くにある神社を調べましょう。
ただし、自宅の近くにあるからといって、氏神神社であるとは限りません。実際に訪れてみたり電話で問い合わせたりして、神社に確認する方法がおすすめです。
2.インターネットで検索する
インターネットで「〇〇(地名) 神社」などと検索してみましょう。検索結果に、自宅付近にある神社がいくつか出てくるはずです。
ただ先述したように、自宅近くにあるからといって氏神神社であるとは限らないので、最終的には神社に確認をとるようにしてください。
3.神社庁に問い合わせる
最も確実で簡単なのが、神社庁に問い合わせる方法です。
東京都の代々木には、全国にある約8万社の神社をまとめる神社本庁があります。そして、各都道府県にも神社庁があり、各地域の氏神神社を取りまとめています。
神社本庁のホームページには、各都道府県の神社庁の電話番号が記載されていますよ。電話で問い合わせを行えば、すぐに氏神神社を教えてもらえます。
電話での問い合わせに抵抗がある場合は、まずは居住地の神社庁のホームページを確認してみてください。氏神神社を調べられる便利な検索ページなどが設けられているかもしれません。
4.長く住んでいる人に聞く
その地域に長く住んでいる人に聞くのも一つの方法です。神社にお参りする習慣がある人なら、氏神神社がどこにあるかも知っているでしょう。
町内会などで交流する機会があれば、ぜひ聞いてみてください。
5.近所の神社で聞いてみる
近所の神社に足を運んで聞いてみる方法もおすすめです。
神職に就いている人なら、その地域の氏神神社がどこかを把握しているはず。訪れた神社が氏神神社じゃなかったとしても、氏神神社の情報を教えてくれるでしょう。
氏神様の正しい参り方のポイント3つ

最後に、氏神様の正しい参り方のポイントを3つ紹介します。
1.引っ越してきたら氏神様に挨拶をする
2.初詣や七五三などの節目には訪れる
3.大切なのは頻度よりも気持ち
「氏神神社にはいつお参りに行けば良いの?」と疑問に思っている方は、ぜひ参考にしてください。
1.引っ越してきたら氏神様に挨拶をする
新しい土地に引っ越しをした場合は、その地域の氏神神社にお参りに行くようにしましょう。
氏神様は、その地域を守ってくださっている神様です。「初めまして。これからよろしくお願いします。」という気持ちを込めて挨拶に行けば、氏神様と良い関係を築いていけるようになるでしょう。
2.初詣や七五三などの節目には訪れる
氏神様をお参りする頻度やタイミングなどに決まりはありません。とはいえ、日頃からお世話になっている神様なので、何かの節目にはお参りに行くと良いでしょう。
具体的には、以下のようなタイミングがおすすめです。
・初詣
・厄年の厄払い
・安産祈願
・お宮参り
・七五三
・成人式
人生の節目には氏神神社を訪れて、自分や家族の健康・幸せを願いましょう。
3.大切なのは頻度よりも気持ち
氏神神社をお参りする頻度は、自分のペースで決めてOK。ただし、多ければ多いほど必ず良いというわけではありません。
大切なのは頻度よりも気持ちです。毎日訪れたいと素直に思えば、毎日参拝するのも良いですし、毎日は大変だ…と感じるのであれば自分の気持ちが向くペースでお参りをしましょう。
氏神神社を訪れた際は、日頃の感謝をまっすぐに伝えるようにしましょう。
また、参拝のタイミングも特に決まりはないので、自分が「神様に気持ちを伝えたい」と思ったタイミングで訪れてみてください。
氏神様に関するよくある質問
氏神神社が遠い場合、近所の別の神社で参拝してもいい?
まずは氏神神社に感謝を伝え、日常の参拝は通いやすい崇敬神社を併用しましょう。
お祓いの初穂料はいくら包めば良い?
厄払いは5,000〜10,000円が一般的ですが、神社の案内があればそちらを優先します。
氏神様とは地域を守る大切な存在!引っ越ししたら挨拶に行こう

地域を守る大切な存在である氏神様。あなたやあなたの家族の幸せ・健康を願って、いつも見守ってくれているはずです。
住んでいる地域の氏神神社がどこか知りたいときは、Googleマップやインターネット検索、神社庁のホームページなどを参考にしましょう。
初詣や七五三などの人生の節目には、氏神神社を訪れて、日頃の感謝を伝えてみてはいかがでしょうか。
アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ
部屋を借りる!賃貸版はこちら
住宅を買う!購入版はこちら


 風水で玄関の鏡はNG?位置、大きさ、形のおすすめと運勢上昇のポイント
風水で玄関の鏡はNG?位置、大きさ、形のおすすめと運勢上昇のポイント
 略語早わかり62選!ビジネスシーン・若者間で使われる必須略語一覧
略語早わかり62選!ビジネスシーン・若者間で使われる必須略語一覧
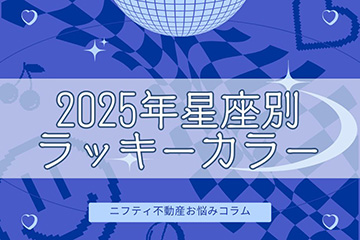 【2025年版】今年のラッキーカラーまとめ|星座別に運気が上がる色を紹介
【2025年版】今年のラッキーカラーまとめ|星座別に運気が上がる色を紹介
 【決定版】家相の基本と間取り図の正しい見方!鬼門・NG配置の対策まで徹底解説
【決定版】家相の基本と間取り図の正しい見方!鬼門・NG配置の対策まで徹底解説