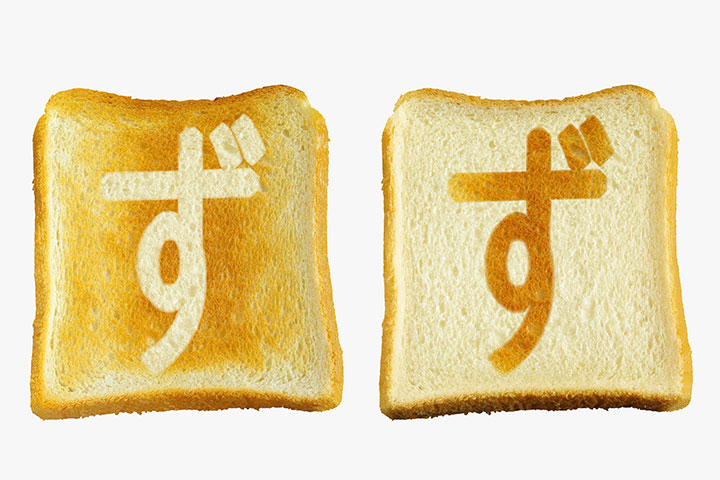お正月の定番料理として、昔から日本人に親しまれてきた「おせち」。おせち自体にはもちろん、具材の一つひとつにまで大切な意味が込められています。
そこで本記事では、おせちを食べる意味について詳しく解説。具材の意味一覧や重箱への詰め方も紹介します。
本記事を読めば、知っておきたいおせちに関する知識が身につきますよ。
ぜひ最後まで目を通してみてください。
- お正月におせち料理を食べる意味は?
- おせち料理の由来
- おせち料理の五段の重箱の意味・詰め方
- おせち料理の具材の意味一覧
- インスタグラムの投稿から魅力的な手作りおせち料理を紹介!
- おせち料理の意味に関するよくある質問
- おせち料理の意味を知ってお正月をお祝いしよう!
お正月におせち料理を食べる意味は?
お正月に日本の食卓を華やかに彩るおせちですが、単なる「美味しい料理」ではありません。
「新年を無事迎えられたことをお祝いし、今年1年の豊作や家族の健康・安全を願う」という大切な意味が込められています。
日本では昔から、「元旦には年神様が山から降りてきて、家々を訪れる」と考えられてきました。
年神様とは、1年間分の福徳を運んでくる来訪神のこと。その年神様を丁寧にもてなすことで、幸せが訪れると信じられています。
その年神様をもてなす料理が、おせちや鏡餅。
年神様へお供えするおせちを一緒に食べることで、年神様が運んできた福徳を授かれる、という風に考えられているのです。
したがって、お正月に食べるおせちは、これから始まる1年間を健康で幸せに過ごすために必要不可欠な存在だといえるでしょう。
おせち料理の由来

おせち料理の起源は、平安時代にまで遡ります。
平安時代には、唐の暦に基づく節目の日に、健康と長寿を願う宮中の行事「節会(せちえ)」が開かれていました。
その節会の際にふるまわれていた料理が、「御節供(おせちく)」です。
平安時代の人々は、御節供を神様にお供えしたり、皆で一緒に食べたりして楽しんでいました。
その風習が残り続け、江戸時代ごろには元旦の料理として庶民にも親しまれるようになります。
表記の仕方も「御節供」から「御節」に変わり、「おせち」と呼ばれるようになりました。
つまりおせちは、平安時代からの長い歴史をもつ、日本の伝統的な料理だということです。
おせち料理の五段の重箱の意味・詰め方

おせちといえば、華やかな重箱に詰めるイメージがありますよね。
年神様に失礼がないように、普段とは違った容器に詰めて盛大にお祝いします。
重箱は五段積み重ねるのが一般的ですが、それぞれの重に意味が込められています。
ここでは、一の重から五の重までの意味と詰め方を詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてください。
一の重:祝い肴
おせちを食べるときに最初に開けるのが、1番上にある「一の重」です。そのため、一の重には祝いの場にふさわしい、縁起が良いものを詰めます。
中でも欠かせないのが「祝い肴」。「祝い肴」とは、以下の3つの料理のことを指します。
・関東…数の子、黒豆、田作り
・関西…数の子、黒豆、たたきごぼう
上記のように、関東と関西ではおせちの内容が少し異なります。祝い肴は「三種の祝い肴」と呼ばれる場合もあり、おせちには欠かせない存在です。
二の重:口取り・酢の物
上から2段目にあるのが「二の重」です。二の重も縁起が良いものを詰めるのは同じですが、特に「喜び」や「財産」などの意味が込められたものを詰めていきます。
具体的には、「口取り」と「酢の物」を詰めるのが二の重です。
・口取り…見た目が華やかで甘い味付けの料理(例:伊達巻、くりきんとん)
・酢の物…酢に浸した料理(例:紅白なます)
「口取り」と「酢の物」は日持ちしやすいという特徴があります。
三の重:海の幸・焼き物
上から3段目にあたるのが「三の重」です。おせちのメインとなる海の幸や焼き物を詰めます。
出世祈願の意味を込めて、出世魚である「ぶり」や高級食材の「海老」、めでたいと言われる「鯛」などを詰めるのが一般的。
「一風変わったおせちを作りたい」という方は、家族の好みに合わせて食材を選び、個性的な三の重に仕上げてみるのもおすすめです。
与の重:煮物
上から4段目にあたるのが「与の重」です。四は死を連想する言葉なので、「四の重」ではなく「与の重」と表記します。
与の重には筑前煮や煮しめなど、野菜を使った煮物を詰めるのが一般的。
煮物は沢山の具材を一緒の鍋で煮込むので、「家庭円満」のイメージにつながるからです。
ただ最近では、お子さんの好みに合わせて、洋風や中華風の料理を詰める家庭も多く見られます。
作りたいおせちのイメージに合わせて、詰める料理を考えていきましょう。
五の重:空箱
一番下の段が「五の重」で、「控えの重」と呼ばれる場合もあります。
五の重には、「年神様から福をいただく場所」という意味が込められています。
いただいた福をしっかりと受け取れるように、五重には料理を詰めず、空箱にしておきましょう。
おせち料理の具材の意味一覧
おせち料理は重箱だけではなく、具材一つひとつにまで意味が込められています。
込められた意味を知っていれば、おせち料理をより楽しめるようになるでしょう。
ここでは代表的な具材の意味を紹介するので、参考にしてください。
1.祝い肴
まずは、一の重に詰める「祝い肴」に込められている意味を紹介します。
黒豆

「まめ」という言葉には、健康・丈夫・元気という意味があります。
つまりおせちには、「まめに働けるように」「まめに暮らせるように」と無病息災を願って黒豆を詰めるのです。
関東では、「シワが寄るまで長生きできますように」という意味を込めて、あえてシワが出るように黒豆を煮るのが特徴。
一方で関西では、シワがないことを「不老長寿」の象徴だと捉え、シワがない艶やかな黒豆を食べます。
数の子

おせちの数の子には、子孫繁栄の意味が込められています。
数の子は、ニシンの卵の塩漬けです。ニシンは一度に多くの卵を産む魚なので、昔から子宝の象徴だと考えられています。
上記のような意味から、「沢山の子宝に恵まれますように」「血筋が途切れることなく子孫が繁栄していきますように」という願いを込めて、おせちに数の子を詰めるようになりました。
たたきごぼう

おせちのたたきごぼうには、「家の繁栄」や「家業の安定」「豊作」などの意味や願いが込められています。
ごぼうは地中深くに根を張る野菜です。その様子から「家や家業が地に根付いて安定する」というイメージが浮かぶので、上記のような意味や願いがつけられるようになりました。
また、たたきごぼうは柔らかく煮たごぼうをたたき、身を開いて作る料理です。開いたごぼうを食べることは、「新年の運を開く」ことにもつながるとされています。
田作り

おせちの田作りとは、カタクチイワシの稚魚を乾燥させて、炒って甘辛く味付けした料理のこと。「五穀豊穣を願う」という意味が込められています。
イワシは昔、田んぼの肥料として使用されていました。肥料の中でもイワシは高級なので、「良いお米ができますように」と特別に願いを込めて撒かれていたそう。
その風習がおせちにも反映されて、五穀豊穣を願う料理として田作りが生み出されました。
2.口取り
次に、二の重に詰める「口取り」に込められた意味を紹介します。
伊達巻き

おせちの伊達巻には、「学業成就」の願いが込められています。
伊達巻といえば、巻物のような形が印象的ですよね。この巻物のような形が書物を連想させるので、伊達巻は「知性の象徴」だと捉えられています。
また、卵をたっぷりと使用して作るのが伊達巻です。卵自体が繫栄や円満の象徴でもあるので、伊達巻には「子孫繁栄」や「家庭円満」の意味も込められています。
紅白かまぼこ

紅白かまぼこは、紅と白にそれぞれ別々の意味が込められています。
・紅のかまぼこ…魔除け、慶び
・白いかまぼこ…清浄、神聖さ
つまり、紅白のかまぼこを食べると、「邪気を払い神聖な気持ちで新年を迎えられる」ということです。
また、かまぼこの半円形は日の出を連想させるので、昔から縁起物として親しまれています。
栗きんとん

おせちの栗きんとんは、「金運上昇」の象徴です。
黄金に光る栗きんとんを見ると、小判や金塊のイメージが思い浮かびますよね。
お正月に金色の食べ物を食べることで、昔の人は「財産や富を得られますように」と願ったのです。
また、栗は「勝ち栗」と呼ばれる場合もあり、戦の勝利を引き寄せる縁起物として重宝されてきました。
そのため、栗きんとんには「勝負運向上」の意味も込められています。
昆布巻き

おせちの昆布巻きには、子孫繁栄の願いが込められています。
昆布は「子生(こぶ)」と表記される場合もあり、子孫繁栄を意味する縁起物だからです。
また、昆布巻の中身にはニシンが使われることが多く、卵を多く産むニシンは子宝の象徴でもあります。
つまり昔の人々は、お正月に昆布巻きを食べて「子宝に恵まれますように」と願ったのです。
3.酢の物
次に、同じく二の重に詰める「酢の物」に込められた意味を紹介します。
紅白なます

おせちの紅白なますは、「一家の平安や平和」を願って食べられる料理です。
紅白なますとは、細く切った大根と人参を酢漬けにしたもののこと。
地中にしっかりと根を張る大根や人参を食べることで、家や家業が安定すると考えられているのです。
また、紅白なますは色合いがお祝いの水引に似ているので、めでたいものの象徴であるとも捉えられています。
酢ダコ

おせちの酢ダコには、「1年間幸せに過ごせますように」という願いが込められています。
タコには、「多幸(たこ)」という漢字が当てられるからです。
また、タコが口から真っ黒な墨を吐いて天敵から逃げる姿は、まるで「苦難を煙に巻いている」ようにも見えます。
上記のような理由から、酢ダコは縁起が良いものとされているのです。
チョロギ

おせちのチョロギには、「健康長寿」の願いが込められています。
チョロギとは、中国原産のシソ科の植物です。おせちには、梅漬けにして使われるのが一般的。
チョロギは漢字では、「長老木」「長老喜」などと表記されます。
このことから、健康長寿を願う食材としておせちにも使われるようになりました。
4.海の幸・焼き物
次に、三の重に詰める「海の幸・焼き物」に込められた意味を紹介します。
鯛(たい)

おせちの祝い魚として使われることが多いのが鯛です。
「めでたい」と語呂合わせができるので、昔から縁起が良い魚として親しまれてきました。
また、鯛は頭から尾びれまですべて食べられる魚なので、「最初から最後まで成し遂げられる」という意味で捉えられる場合もあります。
色が鮮やかで姿かたちも綺麗なので、おせち料理に加えれば見た目が一気に華やかになるでしょう。
鰤(ぶり)

鯛と並んでおせちに使われることが多い魚が鰤です。
鰤は成長するにつれて呼び名が変わるので、「出世を運んできてくれる魚」だと捉えられています。
ちなみに、関東では「ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ」となり、関西では「ツバス→ハマチ→メジロ→ブリ」と呼び名が変化します。
鰤の旬は冬なので、お正月はちょうど脂がのっていておいしい時期です。
海老(えび)

おせちの海老には、「長寿」の意味があります。
「海老」という漢字の表記からもわかるように、海老は長生きの象徴です。体が曲がった姿が老人に例えられることもあります。
また、海老の体は紅白色なので、祝いの場にふさわしい食材です。
上記のような理由から、お正月には「腰が曲がるまで長生きできますように」という願いを込めて、海老を食べるようになりました。
ハマグリ

おせちにおけるハマグリは、「夫婦円満」や「良縁」の象徴です。
ハマグリは貝同士がぴったりとくっついていますが、形がぴったり合うものは一つしかないといわれています。このことが「良縁」を連想させるのですね。
したがって、お正月には「夫婦仲良く過ごせますように」「良い縁がありますように」という願いを込めてハマグリを食べます。
おせちに入れるときは、「旨煮」にするのが一般的です。
トコブシ

トコブシには、「福がたまりますように」という願いが込められています。
トコブシはアワビの仲間ですが、アワビよりも少し小さいのが特徴。別名は「フクダメ」です。
フクダメという別名から縁起物として扱われるようになり、新年を祝うおせちにも詰められるようになりました。
アワビ

おせちのアワビには、「不老長寿」の願いが込められています。
実は、アワビは15年〜20年程度生きる長寿の貝です。強靭な生命力をもつことから、縁起が良い貝として重宝されてきました。
また、アワビは栄養価が高く日持ちもするので、高級品として扱われています。お正月のめでたい場面にぴったりの貝だといえるでしょう。
5.煮物

最後に、与の重に詰める「煮物」に込められた意味を紹介します。
さといも
おせちのさといもには、「子孫繁栄」の願いが込められています
種芋→親芋→子芋→孫芋と増えていく様子が、子孫の繁栄や子宝を連想させるからです。
また、さといもの丸い形が「家庭円満」の象徴だと捉えられることもあります。
れんこん
おせちのれんこんには、「将来の見通しがよくなるように」という願いが込められています。
れんこんの断面には多数の穴が空いており、先を見通しやすいからです。
また、れんこんは蓮の花の地下茎の部分にあたります。
蓮の花は仏教の世界では「極楽浄土に咲く花」だといわれているので、れんこんは神聖で縁起が良い食材だといえるでしょう。
にんじん
にんじんには「ん」がつくことから、運が良い食材だと捉えられています。
また、にんじんの赤色はめでたい色なので、縁起が良い食材だともいわれていますよ。
上記のような理由から、おせちの煮物にはにんじんが使われる場合が多いです。
しいたけ
昔のしいたけは高級品で、お正月などの特別な日にしか食べられない食材でした。
おせちに入れるときは、亀の甲羅に見立てて六角形に切り抜きぬくのが一般的。
亀は長寿の象徴なので、「健康に長生きできますように」という願いを込めてしいたけを食べます。
こんにゃく
おせちのこんにゃくには、「良縁」や「夫婦円満」の願いが込められています。
こんにゃくをおせちに入れるときは、中央に切れ目を入れてねじり、「手綱こんにゃく」と呼ばれる形にするのが一般的。
この手綱こんにゃくの結び目と「縁結び」をかけて、良縁の縁起物として用いられるようになりました。
また、手綱には「引き締める」「統制する」という意味合いもあるので、おせちのこんにゃくには「自分を律する」という意味も込められています。
たけのこ
おせちのたけのこには、「子供の健やかな成長」や「出世」の願いが込められています。
他の植物や野菜よりも成長が早く、天に向かってぐんぐん伸びていくのがたけのこの特徴。その様子を見て人々は、「たけのこのようにぐんぐん成長しますように」「将来出世できますように」と願ったのですね。
くわい
くわいとは、中国原産の水生野菜で、さといもに似た見た目をしています。「くわいという野菜の存在を初めて知った」という方も多いのではないでしょうか。
くわいもたけのこと同様に芽がぐんぐん伸びるので、「出世」や「向上」を象徴しています。
ホクホクとした食感と、甘みと苦みが混ざったような味わいが魅力的です。
インスタグラムの投稿から魅力的な手作りおせち料理を紹介!
インスタグラムの投稿から、魅力的な手作りおせちを紹介します。
「おせちを手作りしてみたい」と考えている方は、参考にしてみてはいかがでしょうか。
かわいいプチ門松
「おせち料理を作る時間はないけど、お正月気分を味わいたい!」
という方におすすめなのが、kanetoku_chimmiさんが紹介しているプチ門松のレシピです。
ちくわに切った食材を挿すだけなので、簡単に作れます。
とびっこのプチプチとした食感と、野菜のシャキシャキ感が相性抜群!
彩りもきれいなので、食卓が一気に華やかになりますね~!
盛り付けも素敵な手作りおせち
k.k_food_ouchigohanさんは、過去3年間の手作りおせちの振り返りをしています。
どのおせちも美味しそうですが、盛り付けも素敵!!
重箱に詰めるのではなく、ワンプレートやオードブル風にするのも雰囲気が変わって良いですね〜!
にんじんやレンコンの形が花形になっていて、手が込んでいることが伝わってきます。
おしゃれなワンプレートおせち
misamisa_1029_さんのおしゃれなワンプレートおせちを紹介します。
なんと、これが初めて作ったおせちだそう!
初めてとは思えないほど、素敵な手作りおせちに仕上がっていますね〜!
ワンプレートおせちは、お子さんがいる家庭でも食べやすそう。
おせちだけではなくお雑煮も、お餅にしっかりと焼き目がついていて美味しそうです。
おせち料理の意味に関するよくある質問

最後に、おせち料理の意味に関するよくある質問3つに回答します。
1.重箱が3段のときのおせち料理の詰め方は?
重箱を3段にする場合は、以下のように具材を詰めます。
・一の重…祝い肴・口取り
・二の重…酢の物・海の幸・焼き物
・三の重…煮物
おせちは正式には五段とされていますが、最近では三段が主流になりつつあります。
2.おせち料理を手作りするときに使ってはいけない食材はある?
原則として、おせちには四足動物(牛や豚)を使ってはいけない、とされています。
ただ最近では、牛肉や豚肉を使用した洋風のおせちも販売されるようになりました。
昔の風習に従うかどうかは、家族と相談して決めましょう。
また、お正月に包丁を使うのは「縁切り」を連想させるので、良くないと考えられています。
おせちの準備は全て大晦日に済ませておき、あとは食べるだけの状態で新年を迎えられるようにしてください。
3.おせち料理を食べるときに使う祝い箸の意味は?
祝い箸は通常の箸とは違い、箸の両端が細くなっています。
これは、祝い箸の片方を神様が、もう片方を人間が使えるようにするためです。
おせちは神様へのお供え物。祝い箸を使って神様と一緒におせちを食べることで、新年を無事に迎えられると考えられています。
おせち料理の意味を知ってお正月をお祝いしよう!

おせちに込められた意味や、重箱の詰め方、具材一つひとつに込められた願いについて解説しました。
おせちは平安時代から続く、日本の伝統料理です。込められた意味や願いを知れば、おせちを作るのも食べるのも今まで以上に楽しめるようになるでしょう。
本記事の内容を参考にしつつ、新年を手作りおせちで迎えてみてはいかがでしょうか。
おせち作りを思いっきり楽しみたいなら、大きなキッチンのあるお家に引っ越すのはいかがでしょうか。ニフティ不動産でぜひお気に入りの物件を見つけてくださいね!
アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ
部屋を借りる!賃貸版はこちら
住宅を買う!購入版はこちら


 蛇の夢は金運アップや幸運の兆し?大きさ・数・色・感情など状況別に意味を紹介
蛇の夢は金運アップや幸運の兆し?大きさ・数・色・感情など状況別に意味を紹介
 【2026年最新】チンチラの飼い方まとめ!種類ごとの価格相場や寿命、なつくコツを伝授
【2026年最新】チンチラの飼い方まとめ!種類ごとの価格相場や寿命、なつくコツを伝授
 フェネックを家で飼うには?必要な費用・防音対策・温度管理まで、後悔しないための飼育マニュアル
フェネックを家で飼うには?必要な費用・防音対策・温度管理まで、後悔しないための飼育マニュアル
 ゴミ袋がやぶれた!フローリングに残る不快な臭いを取る方法
ゴミ袋がやぶれた!フローリングに残る不快な臭いを取る方法