
この記事では、外壁の穴の種類や原因から、コーキングの正しい手順、業者に依頼すべきかの判断基準まで解説します。
外壁の穴埋めに失敗しないために、ぜひ最後まで読み進めてください。
- 外壁の穴の原因・種類
- 外壁の穴を放置してはいけない理由とリスク
- あなたの外壁の穴はDIYできる?業者に依頼するケースも紹介
- DIY補修時のコーキング材を選ぶコツと必要な道具
- DIYで外壁のコーキング補修をする手順
- 外壁の穴埋めコーキングに関するよくある質問
- 外壁の穴は早期発見・早期補修で住まいを守ろう
外壁の穴の原因・種類

家の外壁に小さな穴を見つけて、「これって大丈夫?」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。外壁に穴が空く原因はさまざまで、なかには建物の構造に影響を及ぼす危険なケースもあります。
ここでは、外壁の穴の主な原因となる4つのケースを見ていきましょう。
・施工不良によるピンホール
・エアコンや照明器具の撤去跡
・エアコン配管穴の特殊ケース
・経年劣化や災害による穴
まずは、ご自宅の外壁の穴がどのタイプなのかを確認し、適切な対処法を知ることが大切です。
施工不良によるピンホール
新築や外壁塗装の直後にブツブツとした小さな穴が無数に現れることがあります。この現象は「ピンホール」と呼ばれ、施工不良が主な原因です。
ピンホールが発生する主な原因は以下のとおりです。
・塗料の希釈ミス
・不十分な下処理による塗装
・不適切な塗装道具の使用
・塗装時の環境条件
塗料の希釈量が守られていないと密着不良が起こり、外壁と塗料の間に空気が入りやすくなります。
塗装面の下処理が不十分な場合も、水分や油、ゴミが付着してピンホールの発生につながることも。
また、不適切な塗装道具の使用や気温、湿度など、塗装時の環境条件もピンホールが発生する原因です。
【施工不良なら保証期間内は無料で補修できる】
外壁塗装には通常、数年間の施工保証が付いています。
施工直後にピンホールを見つけた場合は、あわてて自分で補修せず、まずは施工業者に相談してください。
施工不良によってピンホールが発生した場合、保証期間内であれば基本的に無償の修繕対応を受けられます。保証対象や期間は建物の種類によって異なるため、適用条件や保証範囲を確認しましょう。
エアコンや照明器具の撤去跡
エアコンや照明器具を撤去すると、ネジやビスを取り外した跡が穴として残ります。
次のような器具を設置した跡に穴が発生します。
・エアコンの室外機
・給湯器の配管
・アンテナ
器具を外した際に残る小さなネジ穴は、一見すると問題なさそうに見えますが、小さな穴でも雨水の侵入口になるため、放置するのは危険です。
DIYで補修することも可能ですが、正しい手順で補修しないと雨漏りの原因になるため、後述する方法を参考にしてください。
エアコン配管穴の特殊ケース
エアコンの室内機と室外機をつなぐ配管用の穴は、直径65mm〜70mm程度と大きいため要注意です。
多くの場合、パテ(粘土状の充填材)やプラスチック製のカバーでふさがれていますが、パテは配管と壁の隙間を一時的に埋めるためのものにすぎません。
紫外線や風雨にさらされると数年で硬化し、ひび割れや痩せによって隙間ができます。隙間ができると虫の侵入やカビの原因になる可能性も。
パテはあくまで簡易的な処理方法のため、配管穴には専用の「エアコンキャップ」を使うのがおすすめです。
経年劣化や災害による穴
長年の紫外線や雨風によるダメージ、地震や台風といった自然災害が原因で外壁に穴が空くケースもあります。
長期間メンテナンスされていない外壁は、外壁材が反って隙間ができたり、モルタル壁が剥がれ落ちたりして穴が空くことも。
特に、ひび割れ(クラック)をともなう穴や外壁材が欠け落ちている場合は、深刻な状態です。このような外壁は表面だけの問題ではなく、建物の構造部分まで影響が及んでいる可能性があります。
DIYでの修理は避け、専門業者に相談してください。
【台風や地震なら火災保険が適用される場合も】
火災保険に「風災補償」や「地震保険」が付帯していれば、以下のような事例で補償対象になる場合があります。
・台風などの強風で外壁に飛来物が衝突した
・落雷で外壁に穴が開いた
・雹により外壁がへこんだ
・屋根からの落雪により外壁がひび割れた
外壁の穴の原因はご自身で判断せず、修理を始める前にまずは被害状況の写真を撮影し、保険会社や代理店に必ず相談してください。
外壁の穴を放置してはいけない理由とリスク

外壁の穴を「わずか数ミリだから」と軽く考えていませんか?その小さな穴が、数年後に数百万円規模の修繕につながるケースも珍しくありません。
ここでは、穴を放置することで起こり得る3つのリスクについて見ていきましょう。
・雨水侵入が引き起こす構造腐食
・カビとシロアリのリスク
・害虫侵入と美観の低下
これらの危険性を知れば、小さな穴でも早めに対処する重要性がわかるはずです。
雨水侵入が引き起こす構造腐食
外壁の穴の深刻なリスクは、雨水侵入による構造材の腐食です。
外壁は本来、塗装や防水シートによって建物内部を雨水から守る役割がありますが、外壁に穴が空くと防水バリアが機能せず、隙間から壁の内部へ水分が染み込んでしまいます。
特に木造住宅では、柱や梁、土台といった重要な構造材が湿ることで腐食が進み、家全体の強度を支える力が弱まります。
この状態が数年続くと耐震性が著しく低下し、大きな地震の際には倒壊の危険性も高まるため、早めの補修が欠かせません。
カビとシロアリのリスク
外壁の穴から侵入する湿気は、カビとシロアリが発生するリスクを高めます。外壁の穴が原因で常に湿った状態になっている壁内部は、カビにとって絶好の繁殖場所です。
壁の中で発生した黒カビの胞子は、やがて室内の空気中にも飛散し、アレルギーや喘息といった健康被害を引き起こす可能性もあります。
さらに深刻なのがシロアリの発生。シロアリは湿気を含んで柔らかくなった木材を好みます。
外壁の穴から侵入した雨水が木材を腐らせると、それを目当てにシロアリが集まり、家の柱や土台を食い荒らします。気付いたときには構造がスカスカになっていた、という最悪の事態も招きかねません。
害虫侵入と美観の低下
直径数ミリの外壁の小さな穴は、害虫の侵入と美観の低下を引き起こします。
ゴキブリやムカデ、ハチなどの害虫にとって、外壁の穴は格好の侵入経路。その中でも特に注意したいのがハチです。
外壁の隙間から内部に入り込んだハチは、壁の内部(断熱材の中など)に巨大な巣を作るケースがあります。巣の駆除には、数万円の出費が発生するため注意が必要です。
また、外壁の穴を放置すると、雨水が染み込んだ跡(雨染み)や黒カビが外壁に広がる場合も。
外壁の見た目が悪化すると、住宅の資産価値にも影響するでしょう。
外壁の穴はDIYできる?業者に依頼するケースも紹介

「この穴は自分で直せるのか、それとも業者に頼むべきか」と迷う方も多いでしょう。安易なDIYで穴をふさぐと、かえって雨漏りを悪化させる恐れがあるため、慎重な判断が求められます。
ここでは、DIYで補修できるケースと業者に依頼すべきケースの判断基準、さらに費用相場について解説します。
・DIYで対応できるケース
・業者に依頼した方がよいケース
・業者に依頼した場合の費用相場
自身の状況と照らし合わせて、最適な方法を判断する参考にしてください。
DIYで対応できるケース
DIYで対応できるケースは、ごく限られています。
以下の3つの条件をすべて満たす場合のみ、DIYでの補修を検討しましょう。
・穴の直径が1cm未満である
・穴の周囲にひび割れ(クラック)がない
・地上から安全に手が届く高さ(1階部分)である
具体的には、エアコン室外機の固定ビスを外した跡など、直径が小さく手に届く高さにある穴が対象です。
上記の条件のような穴であれば、ホームセンターで必要な道具と材料を揃えても数千円~1万円程度で済むでしょう。
業者に依頼した方がよいケース
外壁の穴の状態が以下のようなケースなら、迷わず専門業者に依頼してください。
・直径が1cmを超える大きな穴
・周囲にひび割れが生じている穴
・2階以上の高所にある穴
特に2階以上での高所作業は、転落事故のリスクがあり非常に危険なため、足場を組める専門業者に依頼するのが安全です。
また、ひび割れをともなう穴は、壁内部で腐食が進んでいる可能性があります。DIYで表面だけを簡易的にふさいでも根本的な解決にはならないため、プロの診断が欠かせません。
無理なDIYは失敗やケガのリスクが高いだけではなく、結局は業者にやり直しを依頼する二度手間になりがちです。
正しく判断して、早めに適切な対応を取りましょう。
業者に依頼した場合の費用相場
業者に外壁の穴補修を依頼する場合、補修内容ごとの費用の目安は以下のとおりです。
| 補修内容 | 費用相場(目安) |
|---|---|
| 小さなビス穴の補修(1箇所) | 3,000円~10,000円 |
| サイディングの部分交換(1枚) | 10,000円~100,000円 |
| 足場が必要な高所作業 | 150,000円~200,000円(足場代含む) |
小さなビス穴1箇所の補修であれば、数千円〜1万円程度で済む場合がほとんどです。
一方、サイディングボードに空いた大きな穴は部分的な板交換が必要になるため、費用も上がります。さらに高所作業で足場を組む場合は、工事全体で15万円以上になることも。
ですが、費用がかかるからと外壁の穴を放置し被害が拡大すると、さらに高額な修繕費が必要になります。早めに対処することで被害の拡大を防ぎ、結果的に修繕費を抑えられますよ。
DIY補修時のコーキング材を選ぶコツと必要な道具

外壁の穴をDIYで補修しようと思ったとき、どのような材料を選べばいいか迷う方も多いのではないでしょうか。
ここでは、穴の大きさに合った材料の選び方と、DIY補修に必要な道具を解説します。
・直径1cm未満はコーキング(シーリング)材
・直径1cm以上はパテ
・DIY補修時に役立つ道具
適切な材料を選べば、補修を長持ちさせられます。それぞれの特徴をしっかり確認しましょう。
直径1cm未満はコーキング(シーリング)材
ビス穴やピンホールのような直径1cm未満の小さな穴には、コーキング材(シーリング材)が適しています。コーキング材はペースト状の充填材で、乾燥するとゴムのような弾力を持つのが特徴です。
コーキング材で外壁の隙間を埋めることで雨水や外気の侵入を防ぎ、防水性や気密性が高まります。
【コーキング材は「変成シリコン系」がおすすめ】
コーキング材には多くの種類があり、用途や施工箇所に適したものを選ぶ必要があります。
特に外壁で使用するコーキング材は紫外線や風雨にさらされるため、高い耐久性や防水性のある「変成シリコン系」がおすすめ。
変成シリコン系のコーキング剤は、外壁のほかにもモルタルや金属、コンクリートなど、塗装が必要な場所でも利用できます。
ホームセンターでよく見る一般的な「シリコン系コーキング材」は、塗装を弾いてしまうため外壁には適しません。
購入する際は、「塗装可」「外壁用」と書かれた変成シリコン系を選びましょう。
直径1cm以上はパテ
穴の直径が1cmを超える大きな欠損は、コーキング材では埋めきれません。
大きな穴を埋める場合は、外壁補修用「パテ」を使います。パテはペースト状の充填剤で、壁面の凹凸やひび割れを埋めて平らにすることが可能です。
パテの処理を適切にすると、きれいに仕上がるほか、外壁の耐久性が高まるでしょう。
外壁補修用のパテは、以下のようにさまざまな種類があります。
| パテの種類 | 特徴・用途 |
|---|---|
| 石膏系パテ | ・反応硬化型で下塗り用として使われる ・耐水性が低く屋外での使用は不向き |
| エポキシ系パテ | ・強度と耐久性に優れ、穴埋めやひび割れの補修に適している ・外壁の強度を補う目的でも使用される |
| 炭酸カルシウム系パテ | ・乾燥硬化型で、研磨がしやすい ・樹脂が多く配合されており、充填しやすく凹凸部分を整えられる |
| アクリル系パテ | ・水性で扱いやすくDIY初心者におすすめ ・速乾性があり、室内や小さな補修作業に使われる |
それぞれ特徴が異なるため、外壁材や用途に合わせて選びましょう。
ただし、パテは乾燥すると硬くなるため、補修後に塗装しないとひび割れを起こしやすい点に注意が必要です。
DIY補修時に役立つ道具
外壁の補修では、以下の道具を用意しておくとスムーズに作業できます。
| 道具 | 用途 |
|---|---|
| マスキングテープ | 補修箇所の周囲を保護し、仕上がりをきれいにする |
| プライマー(下塗り材) | 下地とコーキング材を接着させる |
| コーキングガン | カートリッジ式のコーキング材を押し出す |
| ヘラ | コーキング材の表面をならす |
補修の耐久性を高める上で欠かせないのが「プライマー(下塗り材)」です。
下地とコーキング材をしっかり接着させるため、省略すると補修箇所が数ヶ月で剥がれてしまう原因になります。
作業前に必要な道具は揃えておきましょう。
【100均の補修材で代用できる?】
100円ショップの補修材は外壁の補修には適していません。
安価な材料は耐久性や防水性が低く、数ヶ月から1年程度で劣化し、再び穴が開いて雨水が侵入する恐れがあります。
100均の商品は「次の雨までの応急処置」程度にとどめ、ホームセンターで専用の補修材を購入しましょう。
DIYで外壁のコーキング補修をする手順

外壁に開いた穴を「自分で補修したいけれど、どうやればいいかわからない」という方もいるでしょう。
一時的にでも雨水の侵入を防ぎたい場合、コーキング材を使った方法が役立ちます。
ここでは、コーキング補修の手順を8つのステップで紹介します。
・【補修前に】作業に適した天候を選ぶ
・STEP1:下地処理(所要時間:10分)
・STEP2:マスキング(所要時間:5分)
・STEP3:プライマー塗布(所要時間:5分)
・STEP4:コーキング材を充填(所要時間:5分)
・STEP5:ヘラで表面をならす(所要時間:3分)
・STEP6:マスキングテープを剥がす(所要時間:2分)
・STEP7:十分に乾燥させる(所要時間:24時間~)
・STEP8:塗装して仕上げ(所要時間:30分)
正しい手順で作業すれば、DIYでもしっかり穴をふさげます。一つずつ確認していきましょう。
【補修前に】作業に適した天候を選ぶ
コーキング補修で気をつけたいのが「天候選び」です。
雨の日に作業すると、充填したコーキング材が流れ出したり、水分を含んで固まらなくなったりします。
作業をする際は、最低でも施工後24時間は雨が降らない、晴れた日を選んでください。
【施工環境も仕上がりを左右する】
天候だけでなく、気温や湿度も仕上がりを左右します。
気温が低すぎると硬化が遅れ、逆に夏場の直射日光下では硬化が早すぎて作業しにくくなります。
作業時の温度や湿度の目安は以下のとおりです。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 温度 | 10℃~25℃程度 |
| 湿度 | 40~60%程度 |
作業日は、春や秋の穏やかな日を選びましょう。では、実際の外壁補修の手順を解説します。
STEP1:下地処理(所要時間:10分)
まずは、下地処理をおこないます。丁寧な下地処理が、外壁補修の耐久性を大きく左右します。
「早く穴を埋めたい」という気持ちを抑え、まずは下地をきれいに整えましょう。
穴の周囲に付いた汚れやホコリ、もろくなった古い塗膜を、ワイヤーブラシやカッターでしっかり取り除きます。下地が濡れていると接着不良の原因になるため、前日に雨が降った場合は丸一日以上おいて、完全に乾燥させてください。
STEP2:マスキング(所要時間:5分)
下地処理が終わったら、マスキングテープで補修箇所の周囲を養生します。マスキングテープを貼ることで、コーキング材や塗料がはみ出さず、きれいに仕上がります。
外壁の補修の際は、粘着性が高く面積が広い太めのマスキングテープがおすすめ。施工範囲の境界に沿って丁寧に貼ると、塗布する範囲が明確になります。
STEP3:プライマー塗布(所要時間:5分)
コーキング材を充填する前に、プライマーを塗布します。プライマーは、コーキング材と下地を強力に接着させるための下塗り材(接着剤)です。
ハケ付きの容器に入っている製品が多いため、穴の内部や周囲の下地面に薄く均一に塗ってください。
【プライマーを塗る5分の作業で耐久性が変わる】
プライマーは、コーキング補修の寿命を決める大切な工程です。
「面倒だから」と省略してしまうと補修箇所が壁から浮き上がり、そこから再び雨水が侵入してしまいます。
たった5分の作業を惜しまないことが、外壁補修を長持ちさせるポイントです。
STEP4:コーキング材を充填(所要時間:5分)
プライマーが完全に乾いたら、コーキング材を穴に充填します。
充填のコツは穴の奥から手前へ、空気が入らないようにゆっくりと材料を押し出すことです。ノズルを穴の奥に差し込み、トリガーを引きながら少しずつ引き抜くイメージで充填しましょう。
コーキング材の量は、穴から少し盛り上がるくらいが目安です。
STEP5:ヘラで表面をならす(所要時間:3分)
コーキング材の充填が終わったら、材料が乾き始める前に素早くヘラで表面を平らにならします。
コーキング材はすぐに硬化が始まる場合もあるため、段差が付かないように気をつけながらスピーディーにおこないましょう。
STEP6:マスキングテープを剥がす(所要時間:2分)
表面をならし終えたら、マスキングテープを剥がします。剥がすタイミングは、指で軽く触れて「程よく固まりコーキング材が手に付かない状態」が目安です。
早すぎるとコーキング材が糸を引いて周辺が汚れ、遅すぎるとテープの切れ端がコーキング材に挟まるため、硬化し始める前に剥がすのがポイントです。
STEP7:十分に乾燥させる(所要時間:24時間~)
補修が完了したら、あとは触らずに十分に乾燥させましょう。
コーキング材の表面は数時間で乾きますが、変成シリコン系コーキング材の場合は内部まで完全に硬化するには約3日かかります。
この期間は指で触ったり、雨に濡れたりすると形が崩れる原因になります。
雨が降りそうな場合は、雨よけシートで覆って保護すると安心ですよ。
STEP8:塗装して仕上げ(所要時間:30分)
コーキング材が完全に硬化したら、最後に塗装をして仕上げます。
「変成シリコン系」のコーキング材やパテを使った場合は、塗装が必須です。
無塗装のままだと紫外線による劣化が早まるため、丁寧に塗料を塗り紫外線から守りましょう。
【外壁塗装とコーキング補修を同時にするメリット】
近い将来に外壁の全面塗装を予定している場合は、穴の補修も同時にすると効率的です。
塗装工事では必ず足場を組みます。そのタイミングで穴の補修もまとめて依頼すれば、高所の補修であっても足場代を節約できます。
さらに、補修箇所も全体の塗装と一緒に仕上げられるため、色ムラがなく新品同様の外観に仕上げることが可能です。
外壁の穴埋めコーキングに関するよくある質問

外壁の穴埋めコーキングに関するよくある3つの質問にお答えします。
賃貸物件の場合の費用負担は?
賃貸物件で外壁に穴を見つけたら、勝手に補修せずまず管理会社や大家さんに連絡してください。
経年劣化による損傷は大家(貸主)の負担で修繕されます。ただし、借主の不注意で開けた穴(エアコンのビス穴など)は、退去時に原状回復費用を請求される可能性があります。
無断で補修するとトラブルの原因になるため、穴の原因がわからない場合でも管理会社に報告し、指示を仰ぎましょう。
コーキングの寿命はどのくらい?
プロが正しい手順で施工した場合、コーキングの寿命は5年から10年程度が目安です。
一方、DIYで補修した場合は数年で劣化するケースもあります。
DIYでの補修はあくまで本格的な外壁塗装までの「応急処置」と考えておきましょう。
コーキングの劣化サインは?
コーキングの劣化サインでもっとも見分けやすいのは「ひび割れ(クラック)」です。表面に細かなひび割れが見られたら、劣化の初期兆候と考えてよいでしょう。
さらに劣化が進むと、コーキングが痩せてへこんだり(肉痩せ)、壁との境目から剥がれて隙間ができたり(剥離)します。
隙間ができると雨水が侵入するため早急な対応が必要です。
年に1〜2回は自宅の外壁をチェックし、ひび割れが起きていないか確認しましょう。
▶関連記事
外壁コーキングのひび割れはDIYで直せる?補修費用の相場とおすすめのコーキング剤を紹介
外壁の穴は早期発見・早期補修で住まいを守ろう

外壁の穴の原因からDIY補修の手順、業者依頼の判断基準まで詳しく解説しました。
外壁の穴はたとえ小さなビス穴であっても、雨漏りや腐食につながるため放置は危険です。DIYで対応できるのは「1cm未満・ひび割れなし・手の届く範囲」の条件が揃ったときのみで、それ以外は専門業者への依頼が必要です。
ただし、安さだけで施工店を選ぶと手抜き工事や不当な追加請求のリスクがあるため、慎重に進める必要があります。
外壁補修や外壁塗装を検討している方は、相談から見積もりまで完全無料で利用できる、外壁塗装の適正価格診断サイト「外壁塗装の窓口」をぜひご活用ください。
全国4000社以上の優良店から、あなたの地域に合った施工店を無料で紹介します。見積もり依頼後でも料金や施工店の対応に納得がいかなければ断れるので、気軽にご利用いただけます。
信頼できる施工店を見つけて、外壁の心配に悩まされない安心・快適な暮らしを実現しましょう。
アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ
部屋を借りる!賃貸版はこちら
住宅を買う!購入版はこちら
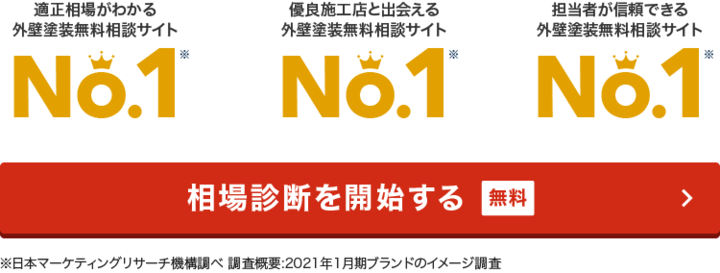
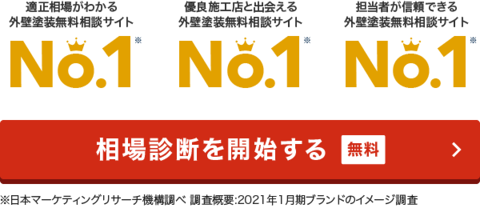


 【2025年最新】加古川市で外壁塗装の助成金・補助金は使える?申請手順や業者の選び方を解説
【2025年最新】加古川市で外壁塗装の助成金・補助金は使える?申請手順や業者の選び方を解説
 【2025年最新】神戸市で外壁塗装の助成金・補助金は使える?申請手順や業者の選び方を解説
【2025年最新】神戸市で外壁塗装の助成金・補助金は使える?申請手順や業者の選び方を解説
 サイディング外壁はDIY塗装できる?手順・費用・失敗を防ぐコツを解説
サイディング外壁はDIY塗装できる?手順・費用・失敗を防ぐコツを解説
 屋根修理はDIYでできる?自分で直せる範囲と屋根材別の手順・安全対策を解説
屋根修理はDIYでできる?自分で直せる範囲と屋根材別の手順・安全対策を解説










