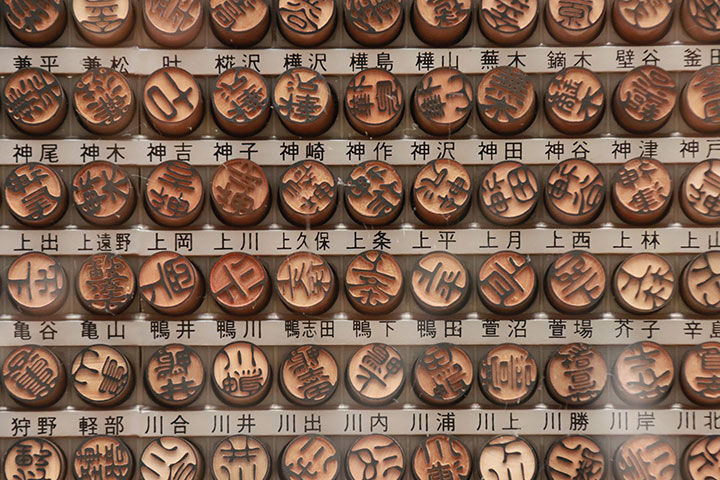そしてそんな七夕にも、正月や節分と同じように「行事食」があります。
七夕ならではの食事でお祝いをすれば、1年に1度しかない七夕の日をさらに楽しめるようになるでしょう。
そこで本記事では、七夕ならではの食べ物と込められた意味を紹介します。お子さんが喜ぶお菓子やデザート、アレンジレシピも取り上げるので、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
- 七夕定番の食べ物と込められた意味
- 七夕定番のお菓子・デザート
- 七夕によく食べられる地域別の行事食
- そもそも七夕とは?意味や由来を解説
- 笹や短冊、七夕飾りに込められた意味
- 【子どもにもおすすめ】七夕の食べ物アレンジレシピをインスタグラムから紹介!
- 七夕ならではの食べ物を用意して楽しい1日を過ごそう!
七夕定番の食べ物と込められた意味
それでは、七夕に食べる定番の行事食と込められた意味を紹介していきます。
・そうめん
・オクラ
・ちらし寿司
・たけのこ料理
今まで何となく食べていたそうめんやちらし寿司も、込められている意味を知れば、さらに美味しく楽しめるようになりますよ。
以下で詳しく解説していきます。
そうめん

七夕で最も有名な食べ物といえば「そうめん」ですよね。
七夕にそうめんが食べられるようになった起源は、中国の伝説にあります。
はるか昔の中国で、7月7日に帝の子どもが亡くなり、その子が鬼神となって熱病を流行らせていました。そこで人々は、その子の好物だった「索餅(さくべい)」というお菓子をお供えします。
すると熱病が収束したため、7月7日には索餅を食べて無病息災を願う、という風習が広まりました。
索餅は、別名で「索麺(さくめん)」とも呼ばれています。そして、時代が変化するとともに「さくめん」ではなく同じ小麦粉で作られた「そうめん」が食べられるようになりました。
したがって、七夕に食べる「そうめん」には健康祈願の意味が込められています。
オクラ

そうめんと一緒に食べたい食材が「オクラ」です。「オクラ」は断面が星型なので、織姫や彦星、天の川などが連想できますよね。
オクラには、ビタミンやミネラルなどのさまざまな栄養素が含まれているので、夏バテ予防にもつながるでしょう。
ちらし寿司

日本の行事食の定番といえば「ちらし寿司」ですよね。寿司は「寿を司る」と書くので、祝いの席でよく食べられるようになりました。
華やかな見た目のちらし寿司は、七夕にもぴったり。お寿司を星型にしたり、オクラで天の川を再現したりなど、アレンジしやすいところも魅力的です。
お子さんと一緒に作るのもおすすめですよ。
たけのこ料理

あまり知られていませんが、「たけのこ料理」も七夕にぴったりの食べ物です。
竹は雨風に強く、天に向かってまっすぐに伸びていきます。その様子から、神聖な植物として扱われてきました。
したがって、「七夕にたけのこを食べると縁起が良い」とされています。
煮物はもちろん、ご飯に混ぜて炊き込みご飯にするなど、アレンジを楽しんでみてください。
七夕定番のお菓子・デザート
次に、七夕定番のお菓子・デザートを紹介します。
・索餅(さくべい)・麦縄(むぎなわ)
・金平糖
・水ようかん
・ゼリー
・甘酒
七夕の日に特別なお菓子やデザートを用意してあげると、お子さんも喜ぶはずですよ。
以下で詳しく解説していきます。
索餅(さくべい)・麦縄(むぎなわ)

七夕でもっとも有名なお菓子といえば「索餅(さくべい)」です。「麦縄(むぎなわ)」と呼ばれる場合もあります。
縄のように細くねじった形が特徴。小麦粉と米粉を使用して作ります。
先述したように、七夕に索餅を食べる風習の起源は中国の伝説です。奈良時代に、中国から日本に索餅が伝わり、のちにそうめんを食べる風習へと変化していきました。
したがって、索餅は「そうめんの先祖」ともいわれています。
金平糖

七夕は「星祭」と呼ばれる場合もあるので、星のような形をしている金平糖は七夕にぴったりのお菓子です。
カラフルな金平糖を用意すれば、お子さんも喜んでくれるでしょう。手作りお菓子やゼリーの飾りつけにも使用できます。
水ようかん
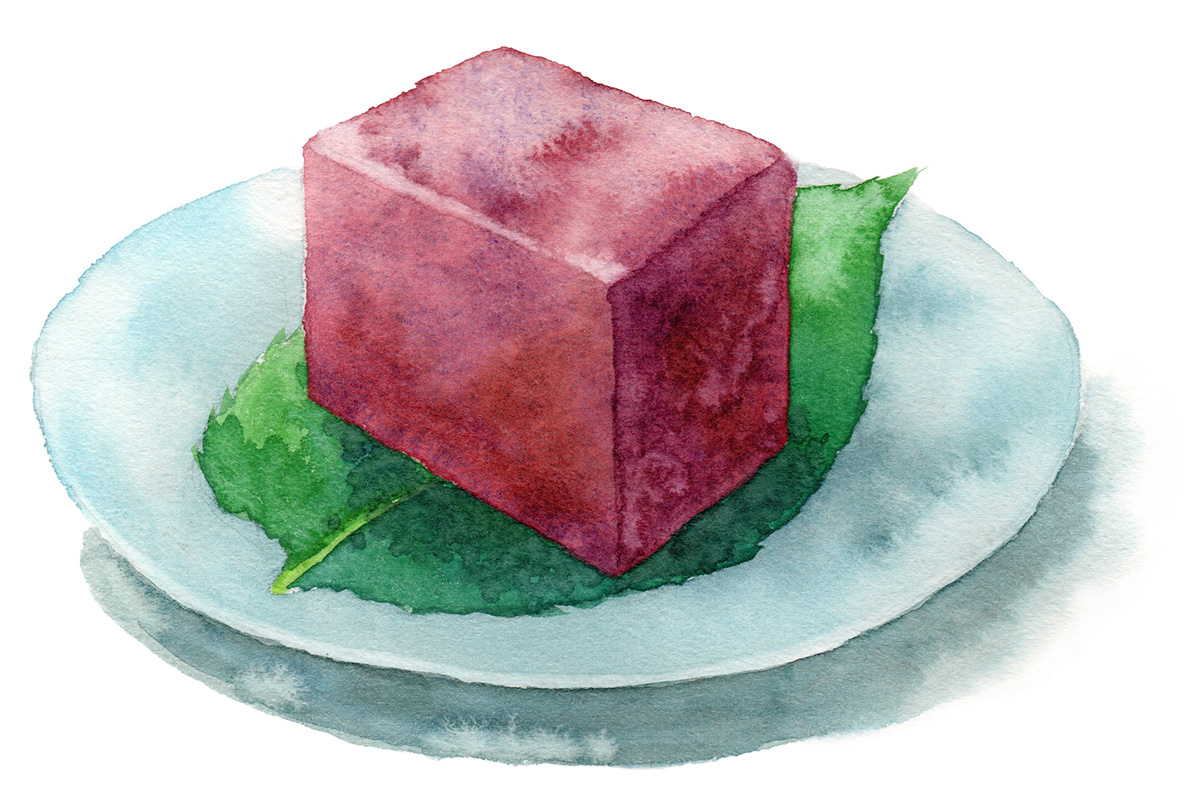
水ようかんは、七夕の行事食というわけではありません。
しかし近年、七夕や天の川をモチーフにした水ようかんが販売されるようになり、人気を集めています。
カキ氷用のシロップやアラザンを使用すれば、自宅で手作りすることもできますよ。
本記事の後半でレシピを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
ゼリー

ゼリーも七夕の行事食というわけではありませんが、手作りしやすく見た目が可愛いのでおすすめです。
星形にくり抜いたり、カキ氷用のシロップで色をつけたり、果物をトッピングしたりなど、アレンジも自由自在。
お子さんも喜んで食べてくれるでしょう。
こちらも本記事の後半でレシピを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
甘酒

昔の日本では、七夕の時期に甘酒を楽しんでいたそう。夏は時期的な問題もあり、お酒の保存がうまくいかない場合が多かったからです。
甘酒といえば寒い時期に飲むイメージが強いですが、実は夏の季語。栄養素が豊富で「飲む点滴」とも呼ばれているので、夏バテ防止にも役立ちます。
七夕には、食べ物やお菓子と一緒に甘酒を楽しんでみてはいかがでしょうか。
七夕によく食べられる地域別の行事食
次に、七夕によく食べられる地域別の行事食を紹介します。
・笹団子(新潟県)
・笹寿司(新潟県)
・七夕ほうとう(長野県)
・笹かまぼこ(宮城県)
「こんな食べ物があるんだ」と驚く方もいるはず。気になる方はチェックしてみてください。
笹団子(新潟県)

新潟県の名物お菓子である「笹団子」。あんこをヨモギ餅でくるみ、笹の葉で包んで蒸したお菓子です。
笹にまつわる食べ物なので、七夕の日にもよく食べられます。
笹の葉には殺菌効果があるので、「邪気を祓う縁起が良い食べ物」だと捉えられていますよ。
笹寿司(新潟県)

新潟県上越地方の名物「笹寿司」。七夕やお盆、お祭りの日などに食べるハレの日の食べ物です。
笹の葉の上に、酢飯と具材がのっているのが特徴。地元でとれた山菜や海の幸を使用します。
良く使われる具材は、鮭・野沢菜・ワラビ・錦糸卵などです。
笹の葉には防腐・殺菌効果があるので、戦のときの携帯食として広まったといわれています。
七夕ほうとう(長野県)

長野県松本市の名物「七夕ほうとう」。山梨県の名物「ほうとう」とは異なります。
小麦で作った太い麺の上に、小豆や胡麻、きな粉をのせた和風デザートです。
長野県松本市周辺では、旧暦の七夕である8月7日に七夕ほうとうを食べてお祝いします。
笹かまぼこ(宮城県)

宮城県仙台市の名物「笹かまぼこ」。笹と関りが深い七夕の日によく食べられています。
かまぼこが笹の葉のような形をしているのが特徴。表面はきれいなきつね色で、歯切れがよく食べやすいです。
明治時代、ヒラメが大量に捕れた時期に、魚肉を活用して作られるようになったといわれています。
そもそも七夕とは?意味や由来を解説

「そもそも七夕ってどのような行事なの?」と疑問に思っている方に向けて、七夕の意味や由来を解説します。
七夕という行事ができた経緯には、主に2つの説があります。
以下でそれぞれを詳しく解説していくので、目を通してみてください。
七夕伝説がもとになっている
1つ目が、「中国の七夕伝説がもとになっている」という説です。
七夕伝説とは、有名な織姫と彦星の物語のこと。
得意な機織りで、天の神様たちの服を作る仕事をしていた織姫。しかし、彦星という若者と結婚すると、2人での生活に夢中になり、機織りの仕事を怠るようになってしまいました。
その様子を見て怒った天の神様は、天の川を隔てた東西に織姫と彦星を引き離します。
悲しみに暮れた2人はますます仕事をしなくなり、困り果てた天の神様。
そして、1年に1度だけ、7月7日に再会させると約束をしました。
2人は、1年に1度の再会を楽しみにして真面目に働くようになり、天の神様たちも服に困ることはなくなったのです。
この伝説が由来となり、織姫と彦星が再会する7月7日は「七夕」としてお祝いされるようになりました。
棚機津女(たなばたつめ)の伝説
2つ目が、「棚機津女(たなばたつめ)の伝説がもとになっている」という説です。
日本では、旧暦の7月15日には水の神が天から降りてくるといわれていました。その7月15日に、村で選ばれた穢れを知らない乙女(棚機津女)が、水辺で衣服を織って神様に捧げます。
そして神様の一夜妻となり、神の子を身ごもって、彼女自身も神になるという伝説です。
七夕の行事の内容とはあまり関係がありませんが、「機を織って神様に捧げる」という行為が七夕伝説と似ています。
そのことから、棚機津女(たなばたつめ)の名前が「七夕(たなばた)」の由来になったといわれています。
笹や短冊、七夕飾りに込められた意味

「笹に短冊を吊るすのはなぜ?」と疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。
実は笹は、昔から神聖な植物として崇められています。天に向かってまっすぐ伸びていくので、「神様が寄ってくる」と考えられているからです。
また、笹の葉には殺菌効果もあるので、「邪気を祓ってくれる」とも考えられています。
その笹の葉に願いを込めた短冊を吊るせば、天の神様やご先祖様に願いが届きやすくなる、と信じられているのです。
ちなみに、代表的な七夕飾りには以下のような意味が込められています。
・五色の吹流し…織物の上達、魔よけ
・千羽鶴…長寿、家内安全
・紙衣(かみこ・かみごろも)…魔よけ、子どもの健康
・巾着…金運上昇、商売繁盛
七夕の日には笹を用意して、短冊や七夕飾りを吊るしてみてください。
【子どもにもおすすめ】七夕の食べ物アレンジレシピをインスタグラムから紹介!
最後に、七夕の食べ物を使用したアレンジレシピを取り上げます。
aya_gohan49さんの投稿から、「お星さまチーズフォンデュ」のレシピの紹介です。
みんなで楽しみながら食べられるチーズフォンデュ。
赤色や黄色、緑色など、カラフルな野菜を選択しているので、食卓が一気に華やかになりますね。
お星さまの形に切ったパプリカやハムもすごく可愛いです!
小さいお子さんがいる家庭だと、きっと喜んでくれるでしょう。
豪華な料理に見えますが、材料を茹でて並べるだけなので、そこまで手間もかかりません。
七夕のランチやディナーに、ぜひ取り入れてみてください。
七夕ならではの食べ物を用意して楽しい1日を過ごそう!

織姫と彦星が1年に1度再会する「七夕」。七夕ならではの食べ物やお菓子、デザートを用意すれば、家族みんなで楽しくお祝いできるでしょう。
本記事で紹介したレシピは見た目が華やかなので、七夕の日の食卓を美しく彩ってくれるはずです。
健康や長寿を願いながら、ぜひ手作りの七夕行事食にも挑戦してみてください。
アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ
部屋を借りる!賃貸版はこちら
住宅を買う!購入版はこちら


 風水で玄関の鏡はNG?位置、大きさ、形のおすすめと運勢上昇のポイント
風水で玄関の鏡はNG?位置、大きさ、形のおすすめと運勢上昇のポイント
 略語早わかり62選!ビジネスシーン・若者間で使われる必須略語一覧
略語早わかり62選!ビジネスシーン・若者間で使われる必須略語一覧
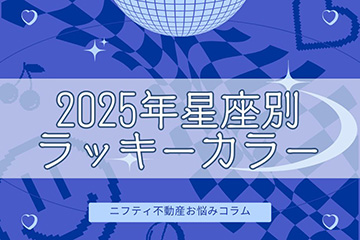 【2025年版】今年のラッキーカラーまとめ|星座別に運気が上がる色を紹介
【2025年版】今年のラッキーカラーまとめ|星座別に運気が上がる色を紹介
 【決定版】家相の基本と間取り図の正しい見方!鬼門・NG配置の対策まで徹底解説
【決定版】家相の基本と間取り図の正しい見方!鬼門・NG配置の対策まで徹底解説