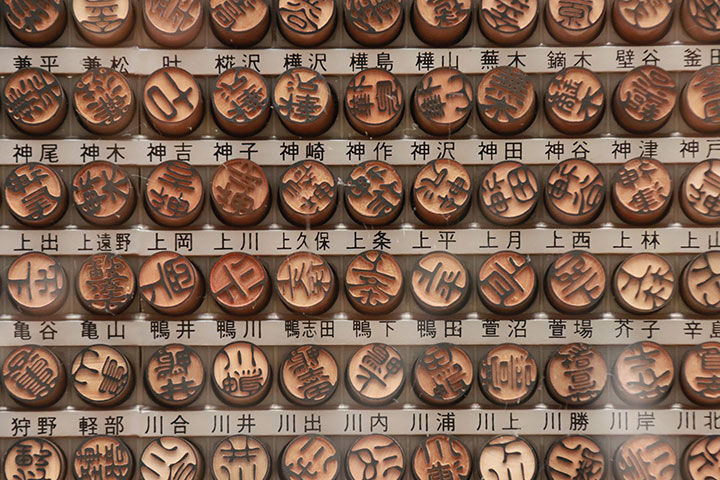法律婚とは異なり、事実婚では姓を変える必要がありません。
一方で、事実婚は「相続権がない」や「税制上の優遇を受けられない」などのデメリットもあります。
今回は事実婚の定義や、事実婚と同棲・法律婚との違い、必要な手続きを紹介します。
事実婚のメリットやデメリットも解説するので、事実婚を検討している方の参考になれば幸いです。
事実婚の体験談も紹介します!
パートナーとの事実婚を考えている人は、要チェックですよ!
- 事実婚とは?何年同居すれば認められる?
- 事実婚と法律婚で変わること一覧
- 事実婚と法律婚で同じこと一覧
- 事実婚のメリット
- 事実婚のデメリット
- 事実婚に必要な手続き4つ
- 経験者に聞く!事実婚をしてみてどうだった?
- 事実婚と法律婚それぞれにメリット・デメリットがある
事実婚とは?何年同居すれば認められる?

「事実婚」とは、婚姻届を提出しないまま、夫婦同然の共同生活を送る関係です。
一方で、婚姻届の提出により戸籍上の夫婦となる状態を「法律婚」といいます。
そもそも事実婚に明確な定義はありません。
事実婚と認められやすい条件は、次のとおりです。
・互いに婚姻の意思を持つ
・社会的に夫婦として認識される
・夫婦同然の共同生活を送っている
なお「同居△年ならOK」などの決まりはありませんが、同居期間が2〜3年以上だと事実婚と認識されやすいですよ。
事実婚は法的な権利や義務に関して、法律婚と異なる点が多々あります。
そのため、事実婚を選択する際は、法的な影響や手続きを理解しておくことが重要です。
具体的な手続きについては「事実婚に必要な手続き4つ」も参考にしてみてください。
事実婚と法律婚・同棲との違い
事実婚と法律婚・同棲との違いを表にまとめました。
| 同棲 | 事実婚 | 法律婚 | |
|---|---|---|---|
| お互いへの認識 | 恋人 | 夫婦 | 夫婦 |
| 住民票の続柄 | 同居人 ※2人それぞれが世帯主となることも可 |
夫(未届) 妻(未届) 同居人 |
夫 妻 |
| 婚姻届 | 提出しない | 提出しない | 提出する |
| 戸籍 | 別の戸籍 | 別の戸籍 | 同一戸籍 |
| 姓 | 別姓 | 別姓 | どちらかの姓 |
※事実婚で夫(未届)・妻(未届)と表記されるには、世帯変更届の提出が必要
事実婚と同棲との大きな違いは「お互いを夫婦と認識しているか」です。
事実婚と法律婚に関しては「事実婚と法律婚で変わること一覧」や「事実婚と法律婚で同じこと一覧」で詳しく解説していきます。
事実婚と法律婚で変わること一覧

事実婚と法律婚で変わることを一覧表にしました。
| 法律婚 | 事実婚 | |
|---|---|---|
| 配偶者の相続権 | あり | なし ※遺言書や生前贈与という形式で財産を渡すことは可 |
| 相続税の配偶者の税額軽減 | あり | なし |
| 所得税の配偶者控除 | あり | なし |
| 父子関係の成立 | 婚姻中に妻が妊娠した子どもを、原則として夫の子ども(嫡出子)とみなす | 非嫡出子となる ※親子関係を示すには「認知」手続きが必要 |
| 親権 | 夫婦共同親権 | 単独親権(原則母親) |
| 父母の一方が死亡したときの親権 | 生存している親権者がそのまま単独で親権を行う | 父母のうち親権者のほうが死亡した場合には、未成年後見が開始する ※他方の親が親権者になるには親権者変更等の審判が必要 |
| 特別養子縁組 | 可能 | 不可 |
| 住宅ローンの収入合算 | 可能 | 一部の金融機関で可能 |
参考URL:いわゆる事実婚※に関する制度や運用等における取扱い
事実婚と法律婚で同じこと一覧

事実婚と法律婚で同じことを、以下にまとめました。
・社会保険……認められる
・国民年金の第3号被保険者……認められる
・公的年金制度の給付(遺族基礎年金・寡婦年金など)……認められる
・育児・介護休業法にもとづく各種制度(介護休業・介護休暇など)……可能
・生活保護制度における世帯認定……認知される
・保育料算定の際の世帯認定……認知される
・児童扶養手当……支給されない
・労働災害の遺族補償年金……受給可能
・犯罪被害者遺族給付金……給付される
事実婚と法律婚で変わること・同じことを把握した上で、どのような夫婦関係を築くかを検討しましょう。
参考URL:いわゆる事実婚※に関する制度や運用等における取扱い
事実婚のメリット

事実婚のメリットは、主に3つあります。
・姓を変更する必要がない
・関係を解消しても戸籍に記録が残らない
・親戚付き合いの負担が軽減される
以下で詳しく説明していきます。
姓を変更する必要がない
事実婚では婚姻届を提出しないため、姓を変更する必要がありません。
法律婚では夫婦同姓が原則であり、改姓すると以下のような名義変更手続きが生じます。
・転入届
・健康保険や年金
・銀行口座やクレジットカード
・マイナンバーカードや運転免許証、パスポート
それぞれの窓口に出向いて手続きを進めるのは、時間と手間がかかりますよね。
会社によっては入籍を報告した後に、書類提出などが求められることも。
事実婚なら姓を変更せずに済むため、このような面倒な手続きを避けられます。
関係を解消しても戸籍に記録が残らない
婚姻関係を解消しても、戸籍に記録が残らない点が事実婚のメリットのひとつです。
法律婚では、離婚すると戸籍に記録が残ります。
対して、事実婚の場合はもともと入籍していないため、戸籍上の変更がありません。
離婚歴を気にする人にとっては、事実婚という形式を選ぶことで、心理的な負担を減らせるでしょう。
また、事実婚では「離婚届の提出」や「裁判や調停」といった手続きを行わずに、法律婚よりもスムーズに関係を解消できますよ。
親戚付き合いの負担が軽減される
法律婚では、法律上で相手の親戚と家族関係が結ばれます。
義理の父母・兄弟姉妹ができることで
・冠婚葬祭に出席する
・長期休暇に親戚の集まりに参加する
などの親戚付き合いが発生するでしょう。
事実婚では法的な親族関係が生じないため、親戚付き合いにおける負担を避けやすいです。
ただし、事実婚でも家族ぐるみの関係を築くことは可能ですよ。
「親戚だから仲良くしなければ」という概念にとらわれず、柔軟な付き合い方を選べる点が事実婚のメリットといえます。
事実婚のデメリット

事実婚のデメリットを3つ紹介します。
・税金の配偶者控除が受けられない
・遺産の相続権がない
・子どもが「非嫡出子(婚外子)」となる
事実婚を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。
税金の配偶者控除が受けられない
事実婚の夫婦は、税金の配偶者控除が受けられません。
税制上の優遇を受けられなければ、世帯全体の税負担が増える可能性があります。
そもそも配偶者控除とは、控除対象となる配偶者がいる場合に、納税者が受けられる控除を指します。
パートナーを持つ人が活用できる節税対策のひとつです。
「収入が少ないので税制上のメリットを得たい」という人は、法律婚も検討してみては。
参考URL:No.1191 配偶者控除
遺産の相続権がない
事実婚のパートナーに認められないものとして「遺産の相続権」が挙げられます。
法律婚の配偶者であれば、遺産の一定割合を相続できます。
しかし、事実婚では遺言書がない限り、相手の遺産を受け取れません。
事実婚を選択する際は、万が一の事態に備えて「遺言書を残す」または「生前贈与する」といった相続対策が重要です。
子どもが「非嫡出子(婚外子)」となる
事実婚の両親の間に生まれた子どもは、法律上「非嫡出子(婚外子)」として扱われます。
法律上で父親と親子関係が認められるには、役所への「認知届」の提出が必要です。
また、現在の法律では事実婚における共同親権は認められていません。
原則として子どもの親権は母親にあります(2025年2月時点)。
2026年5月までに施行される改正民法では、非嫡出子の共同親権も認められる予定です(改正民法819条4項)。
参考URL:いわゆる事実婚※に関する制度や運用等における取扱い
参考URL:民法の一部を改正する法律等(案)【逐条解説】
事実婚に必要な手続き4つ

事実婚に必要な手続きを4つピックアップしました。
・世帯変更届を提出する
・公正証書を作成する
・パートナーシップ制度を利用する
・認知や養子縁組をする【子どもがいる場合】
ひとつずつみていきます。
世帯変更届を提出する
事実婚を公的に証明するには、世帯変更届の提出が重要です。
同居する二人の世帯を合併するための手続きで、完了すると住民票の続柄表記が
・夫(未届)
・妻(未届)
に変更されます。
ただし、自治体によって事実婚の扱いは異なります。
手続きを終えても「同居人」と書かれるケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。
公正証書を作成する
事実婚のパートナーと法的な権利・義務を明確にするには、公正証書の作成が有効です。
なお、公証人が法律にもとづいて作成する文書を「公正証書」といいます。
事実婚は婚姻届を提出しないため、二人の合意を第三者に証明することは困難です。
「二人が事実婚である」という契約書を作ることで、関係性や合意事項を形に残せます。
公正証書に記すとよい内容を、いくつかピックアップしました。
・婚姻意思の合致
・財産やお金に関する約束事
・今後出生する子を認知すること
・医療行為への同意を相手に任せること
・離婚時の財産分与
公正証書は第三者である公証人が関与するため、証明力が高い点もメリットですよ。
パートナーシップ制度を利用する
一部の自治体では、事実婚や同性カップル向けに「パートナーシップ制度」を導入しています。
この制度を利用すると、自治体が発行する証明書を通じて、各種手続きがスムーズになりやすいです。
たとえば、病院での面会が認められやすかったり、賃貸契約で家族扱いになりやすかったりします。
ただし、法的拘束力はなく、自治体ごとに適用範囲が異なる点には注意しましょう。
認知や養子縁組をする【子どもがいる場合】
事実婚のカップルに子どもがいる場合、父親が認知手続きを行わないと、法律上の親子関係が成立しません。
認知された子どもは法律婚と同じように、母親と父親の遺産を相続する権利が発生します。
また、事実婚を結ぶパートナーに連れ子がいるならば、養子縁組をすると実子と同様の親子関係が生じます。
認知や養子縁組には法的な影響があるため、手続き前に専門家へ相談するのがおすすめです。
経験者に聞く!事実婚をしてみてどうだった?

最後に、事実婚をしている人の体験談をまとめたので、参考にしてみてください。
実際の口コミはこちらです。
【事実婚を決めたタイミング:同棲1年目】
相手に離婚歴があり子どももいるので、わざわざ籍を入れる必要がないと考えました。
親戚間のしがらみがなく、自由に過ごせています。 ななさん・接客業・大阪府・20代・女性
【事実婚を決めたタイミング:交際5年目】
妻の実家が入籍に反対していたため、事実婚を決めました。
離婚しても戸籍に傷がつかない点がメリットだと思います。
「住民票などの書類を提出する際の説明が面倒」または「物件を借りるときは事実婚に理解のある家主を探さないといけない」などのデメリットもありますね。 TETETE・会社員・大阪府・50代以上・男性
【事実婚を決めたタイミング:交際4年目、同棲2年目】
形式にこだわらなくても、一緒にいられると感じたことが事実婚を選んだ理由です。
結婚に伴うさまざまな手続きが面倒ですし、仕事への影響を考えて苗字を変えたくありませんでした。
パートナーも「結婚にこだわる必要はない」という考えです。
「結婚したからこうしなきゃ」という固定観念にとらわれず、二人で納得のいく関係を作れています。
一方で、親の理解を得るのはなかなか大変でしたね。
特に私の両親は「結婚=入籍が当たり前」という考えだったので、説得には時間がかかりました。 N° 秋・会社員・秋田県・30代・女性
【事実婚を決めたタイミング:交際1年目】
私とパートナーは同性で、日本の法律ではまだ結婚ができません。
「法律が改正されるまでは事実婚という扱いになるね」と話しています。
事実婚という形をとると、パートナーの緊急時(怪我や病気のとき)に一緒にいられる点がありがたいです。
「同棲する家を借りる際は書類を連名にする」など、書類上の小さなところに既成事実を積み上げていきました。 あひんさー・学生・神奈川県・20代・女性
【事実婚を決めたタイミング:交際5年目】
私は結婚をしようと思っていたのですが、彼女が「親戚付き合いが嫌だ」と主張したため事実婚となっています。
相手家族へ気を遣う必要がないのは自由でよいのですが、事実婚で困ることも……。
たとえば、彼女が入院したときに「同意書は家族でないと不可」といわれ、遠方の親を呼んだことがあります。
面会でも「どのようなご関係ですか?」と聞かれるたびに、説明に困ってしまいます。 boing・自営業・北海道・40代・男性
事実婚と法律婚それぞれにメリット・デメリットがある

今回は事実婚の定義や、事実婚と同棲・法律婚との違い、必要な手続きを解説しました。
事実婚は法律婚と異なり、姓を変更する必要がなく、戸籍に記録が残りません。
ただし、税制や相続の面では制約を受けやすいです。
法律婚との違いを理解し、自分たちに合った選択をしましょう。
事実婚に向けて新居を探しているならば、ニフティ不動産を利用するのがおすすめです。
ニフティ不動産は大手不動産サイトでまとめて物件を探せて、複数条件で絞りこめます。
「ニフティ不動産」で理想の物件を探しましょう!
▶▶家を売りたい方はこちらをチェック!
アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ
部屋を借りる!賃貸版はこちら
住宅を買う!購入版はこちら


 風水で玄関の鏡はNG?位置、大きさ、形のおすすめと運勢上昇のポイント
風水で玄関の鏡はNG?位置、大きさ、形のおすすめと運勢上昇のポイント
 略語早わかり62選!ビジネスシーン・若者間で使われる必須略語一覧
略語早わかり62選!ビジネスシーン・若者間で使われる必須略語一覧
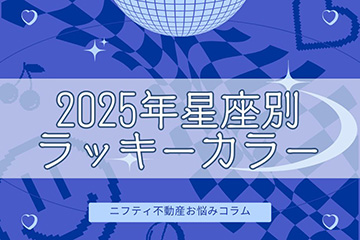 【2025年版】今年のラッキーカラーまとめ|星座別に運気が上がる色を紹介
【2025年版】今年のラッキーカラーまとめ|星座別に運気が上がる色を紹介
 【決定版】家相の基本と間取り図の正しい見方!鬼門・NG配置の対策まで徹底解説
【決定版】家相の基本と間取り図の正しい見方!鬼門・NG配置の対策まで徹底解説